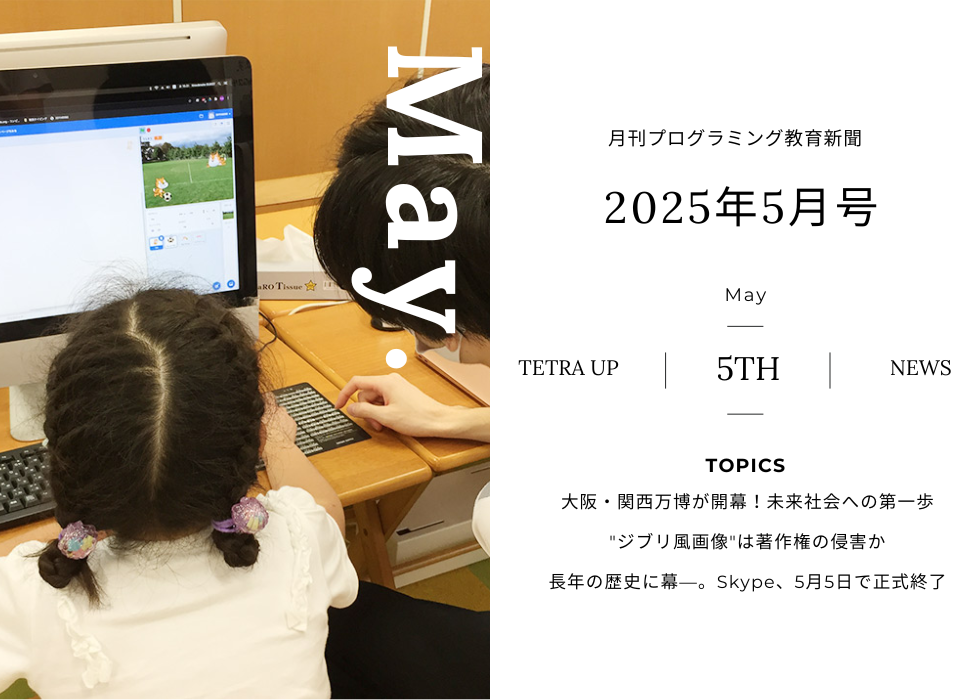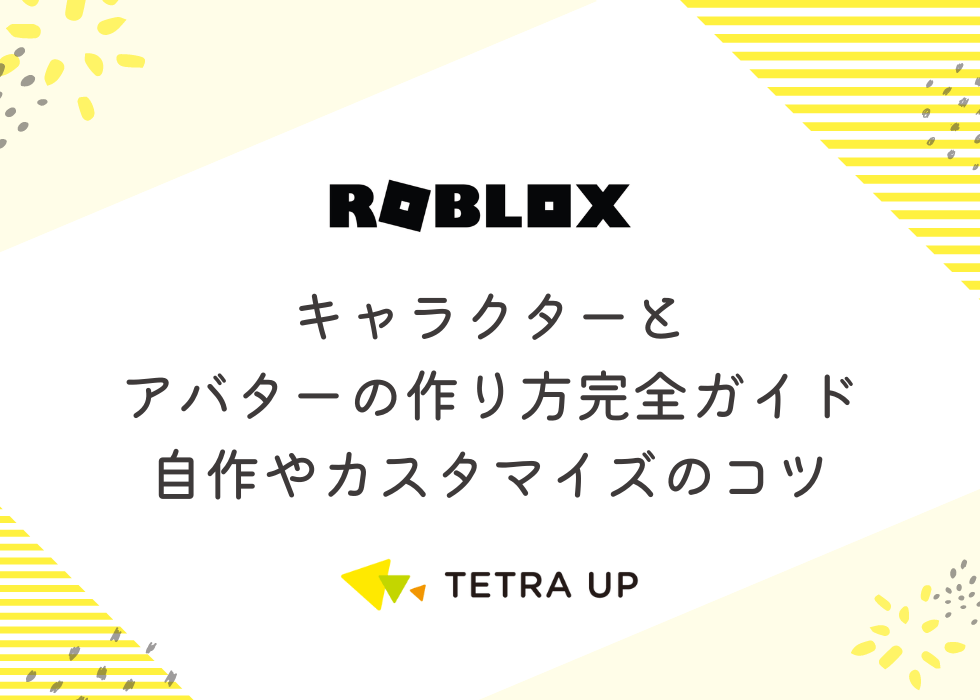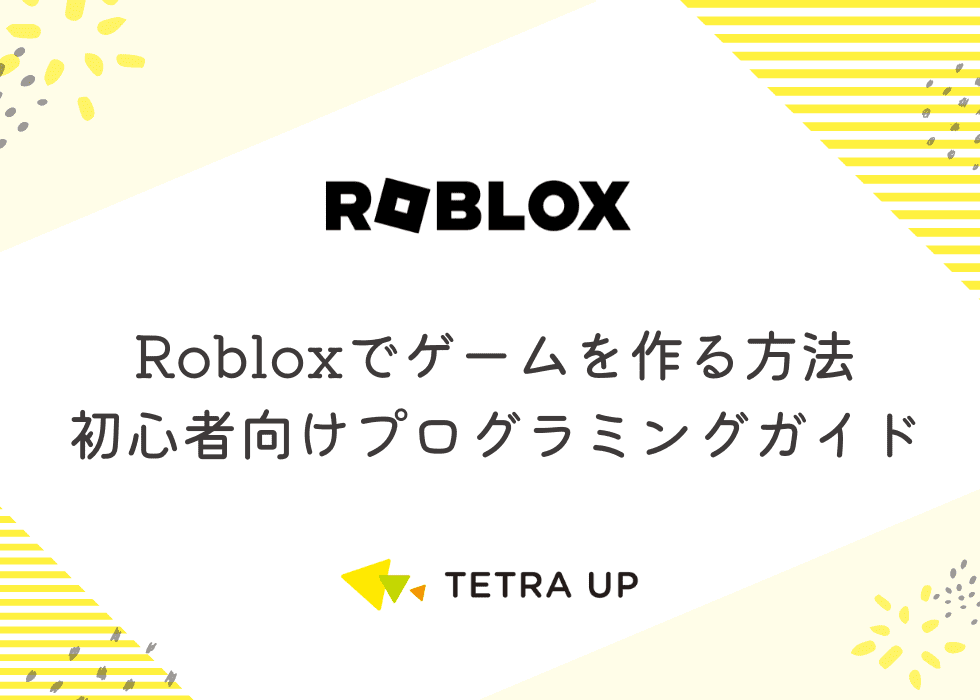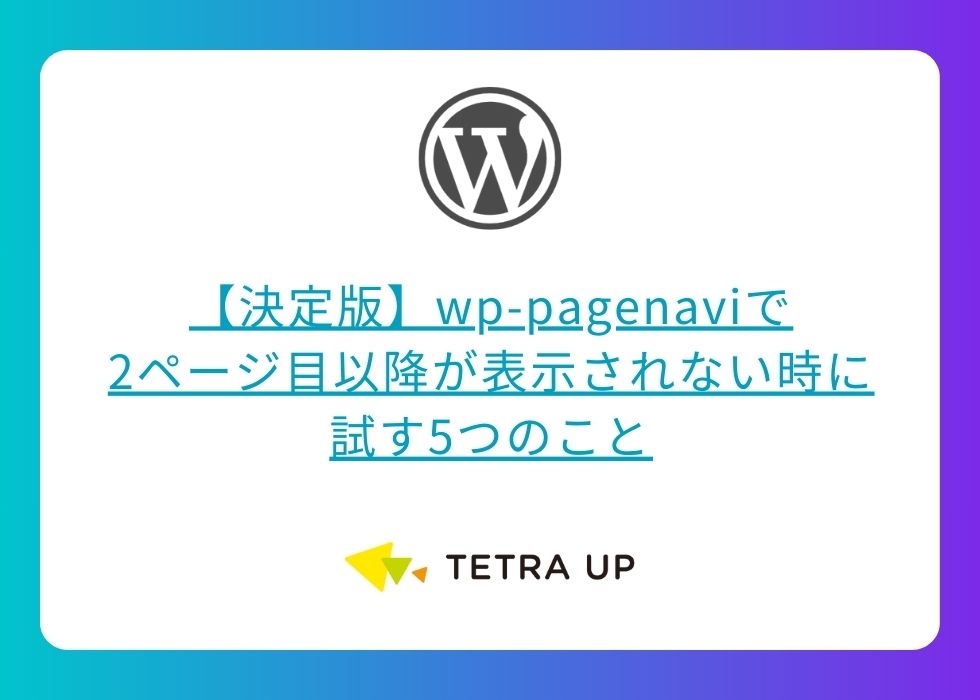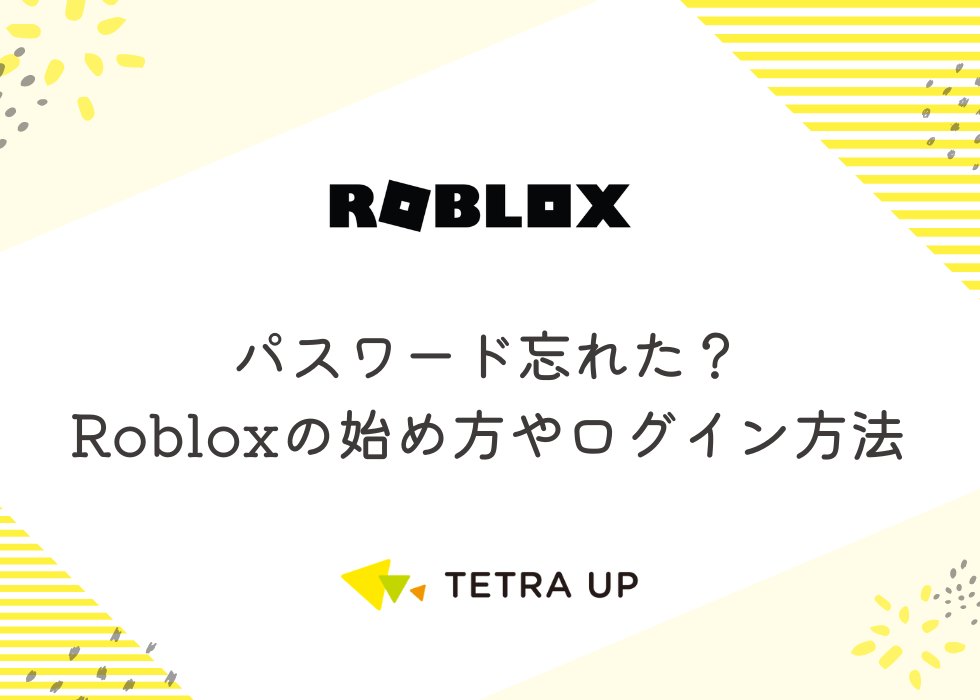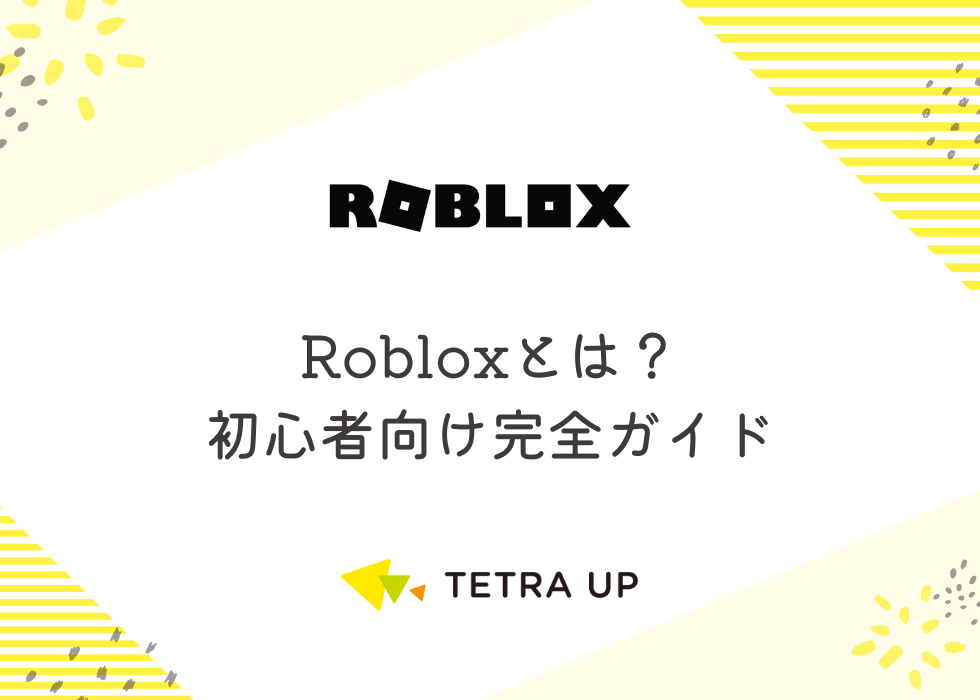-
プログラミング教育新聞 2025年11月号|TETRA UP
お知らせ詳細を見る▶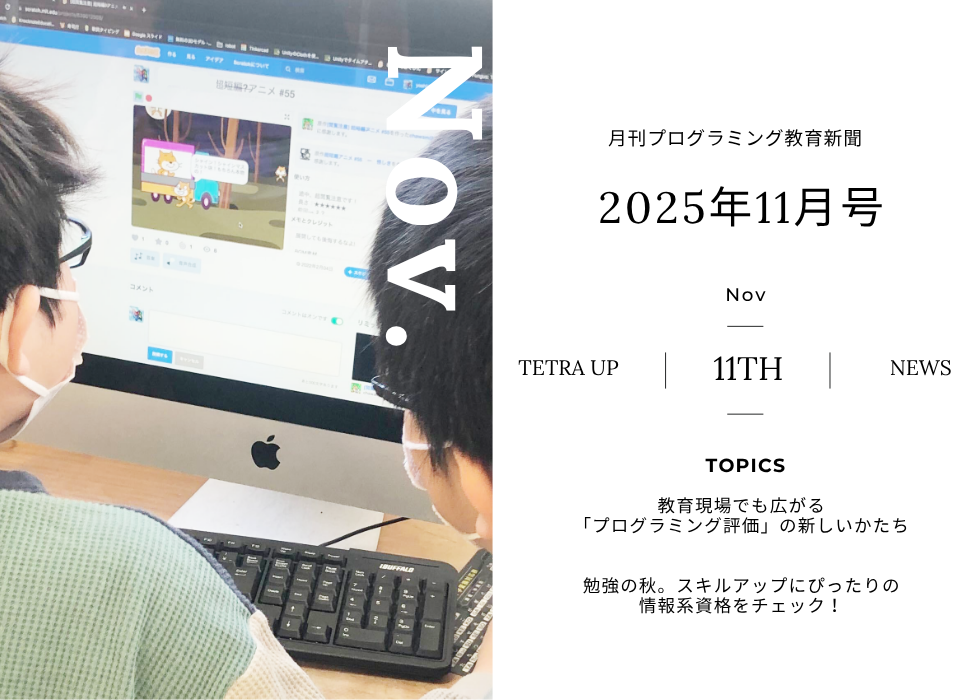
-
【現役講師が解説】子どものゲーム依存を防ぐ方法と健全なデジタル活用のヒント
コラム詳細を見る▶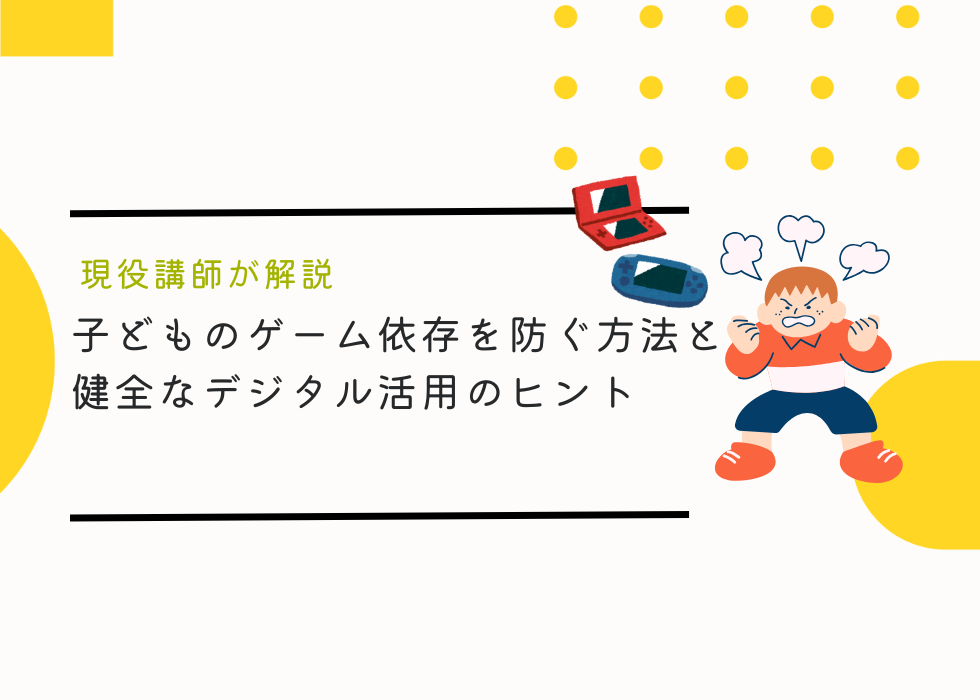
-
“イタリアンブレインロット”とは?AI×ミーム×中毒性が生んだ2025年のネット現象と闇
コラム詳細を見る▶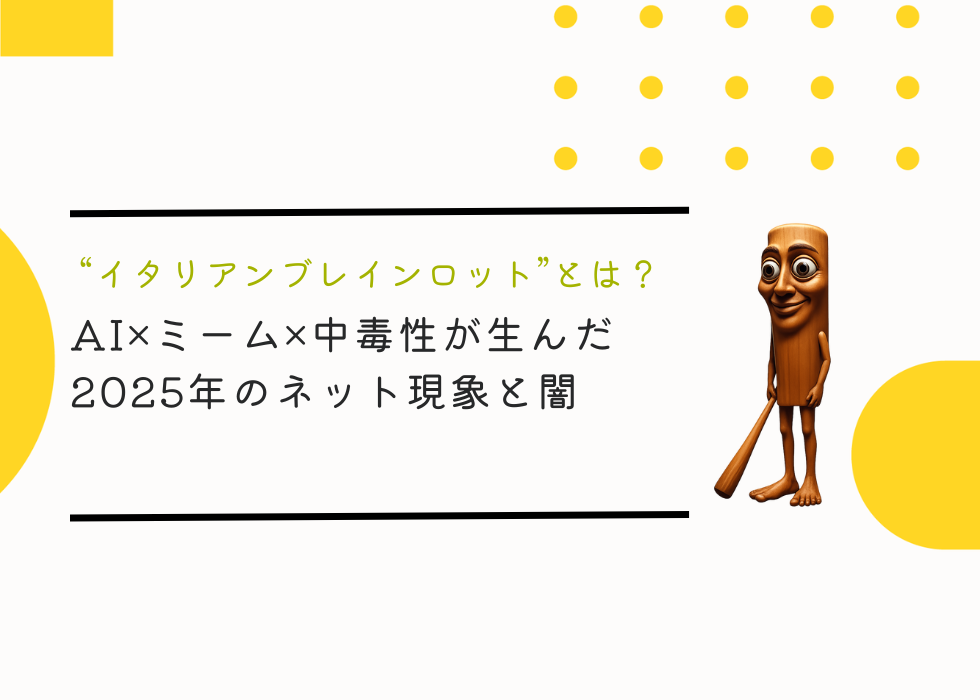
-
ロブロックス 99日生き残るとは?初心者でも楽しめる遊び方・攻略・魅力を解説
コラム詳細を見る▶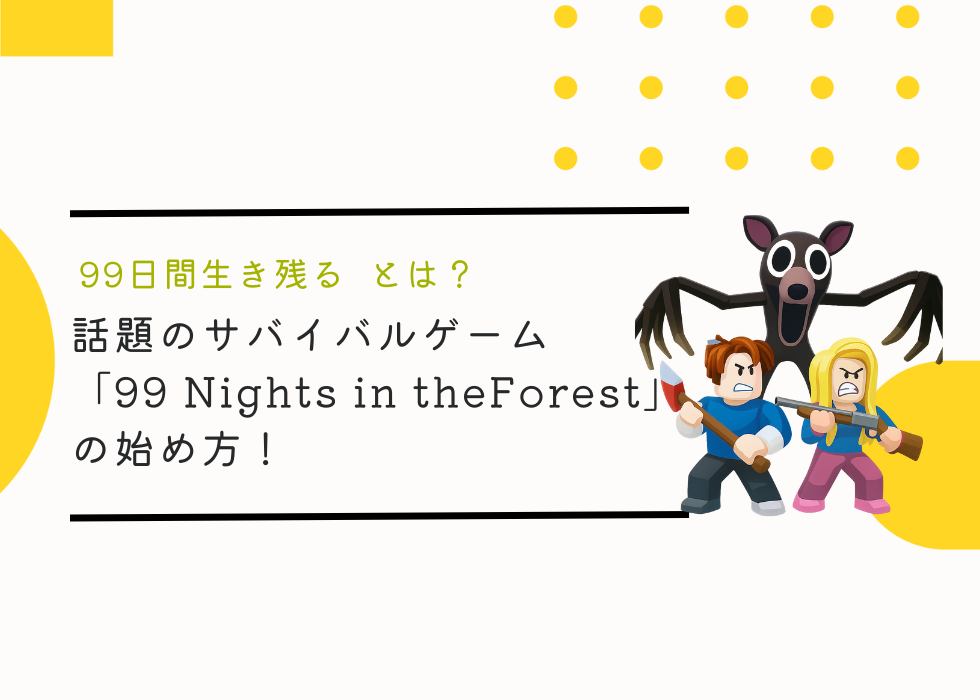
-
プログラミング教育新聞 2025年8月号|TETRA UP
お知らせ詳細を見る▶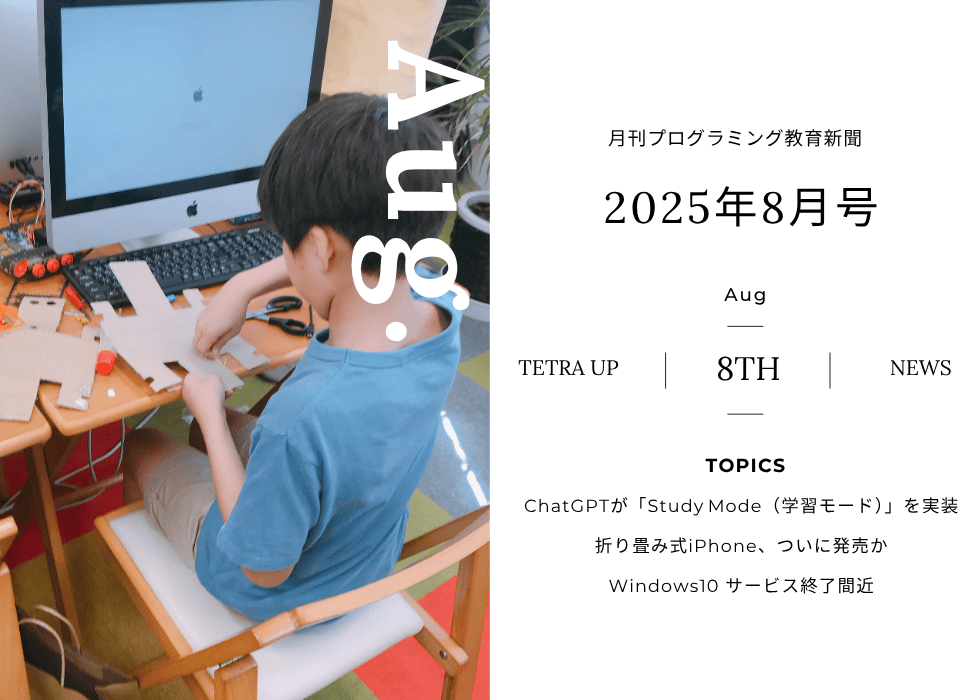
-
【初心者向け】Roblox Studioでアニメーションを作成してプレイヤーを動かす方法を徹底解説!
コラム詳細を見る▶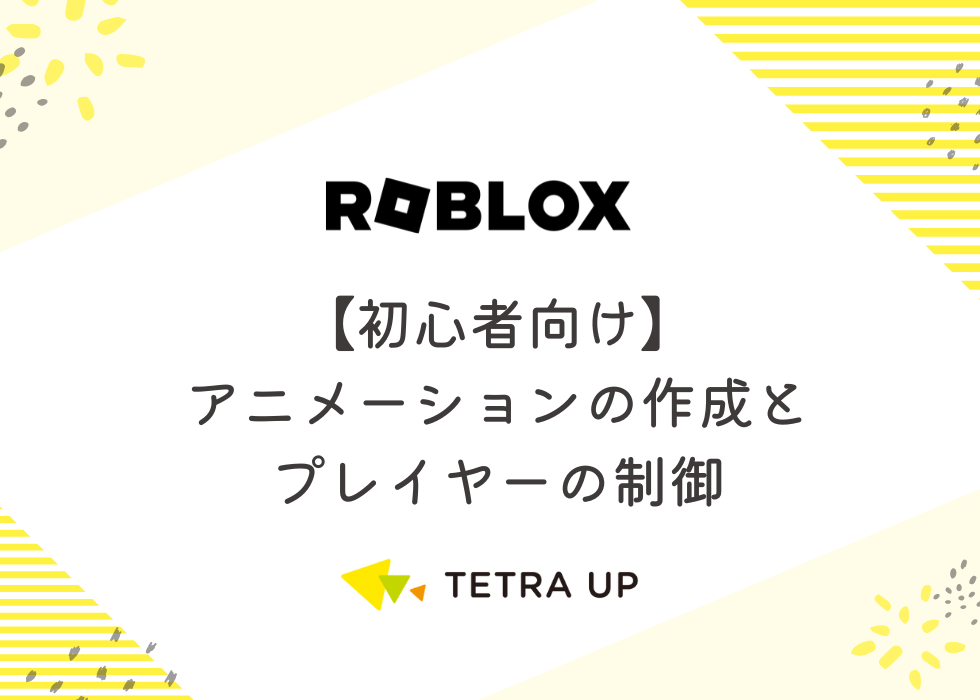
-
ロブロックス 庭を成長させるゲームとは?初心者でも楽しめる育成ゲーム「Grow a Garden」完全攻略!
コラム詳細を見る▶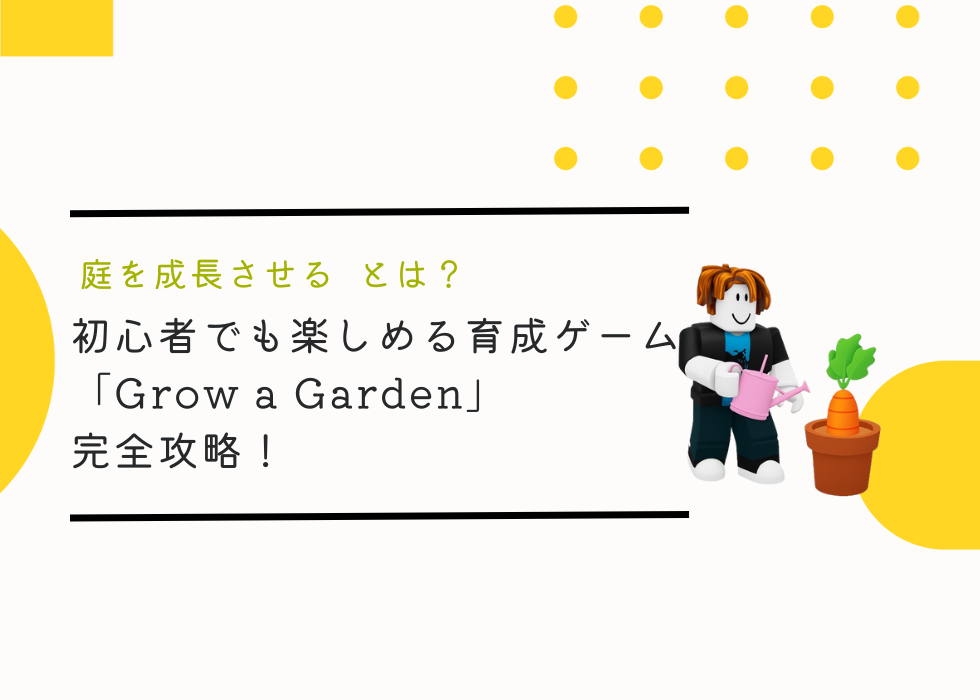
-
【5分で作れる!】Roblox(ロブロックス)アイテムの作成入門
コラム詳細を見る▶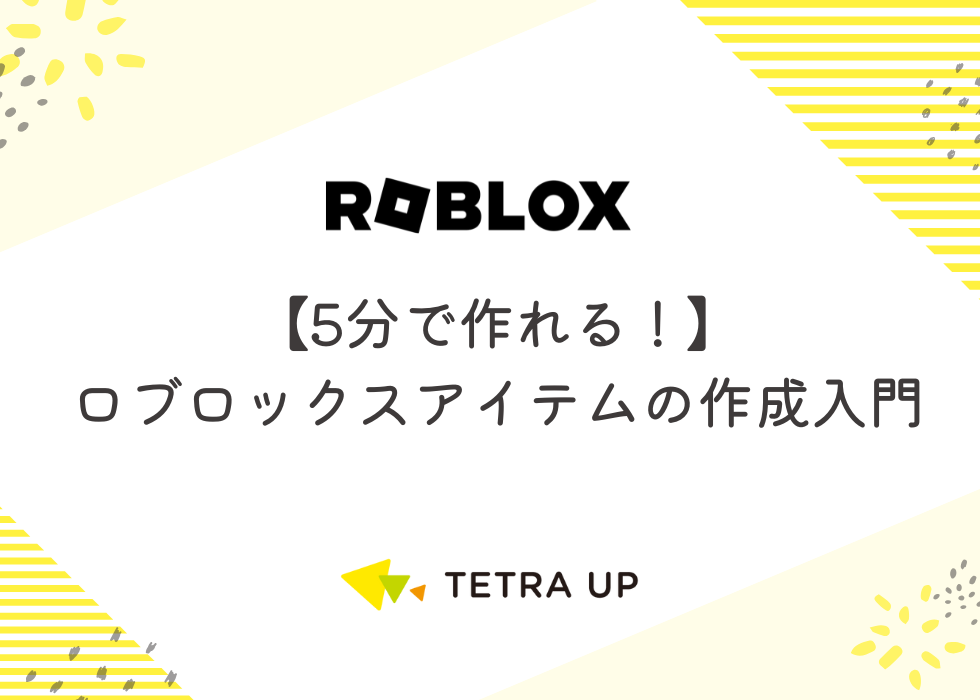
-
Roblox Studioはタブレットで使える?対応端末を解説
コラム詳細を見る▶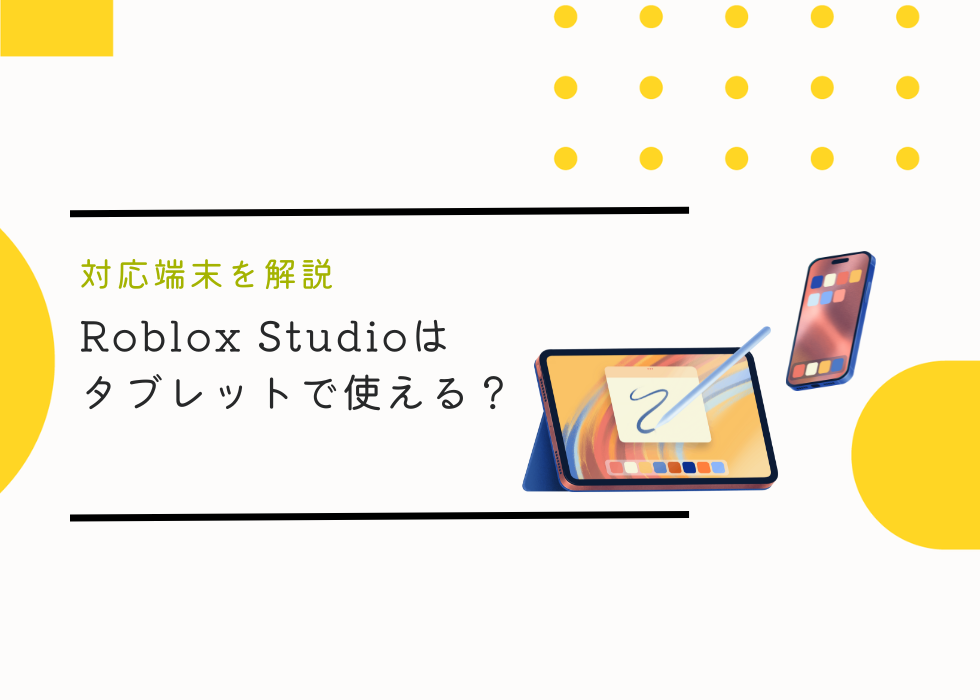
-
プログラミング教育新聞 2025年5月号|TETRA UP
お知らせ詳細を見る▶