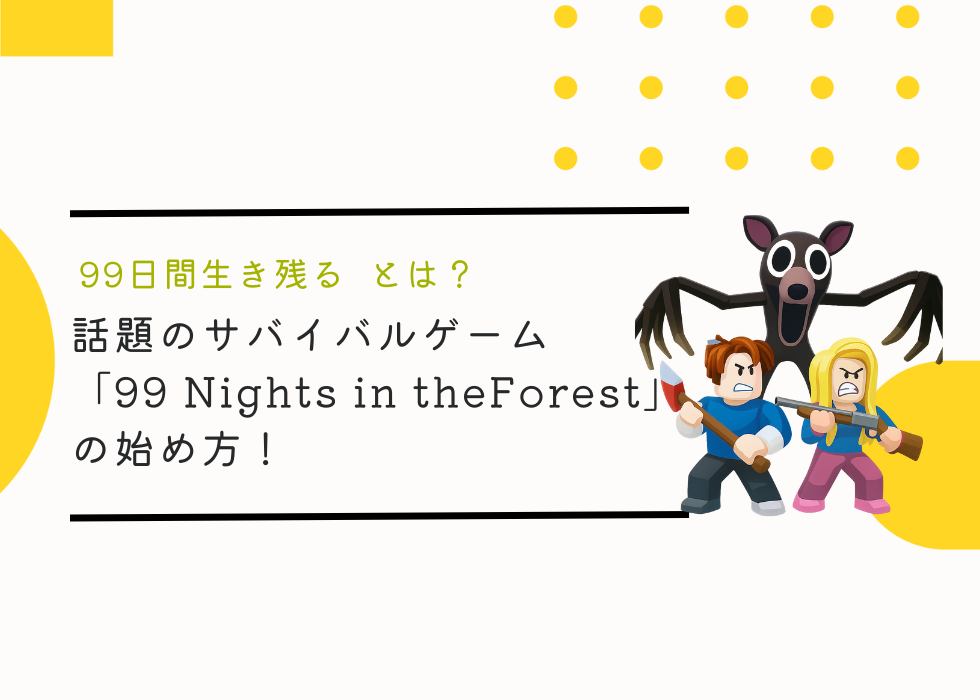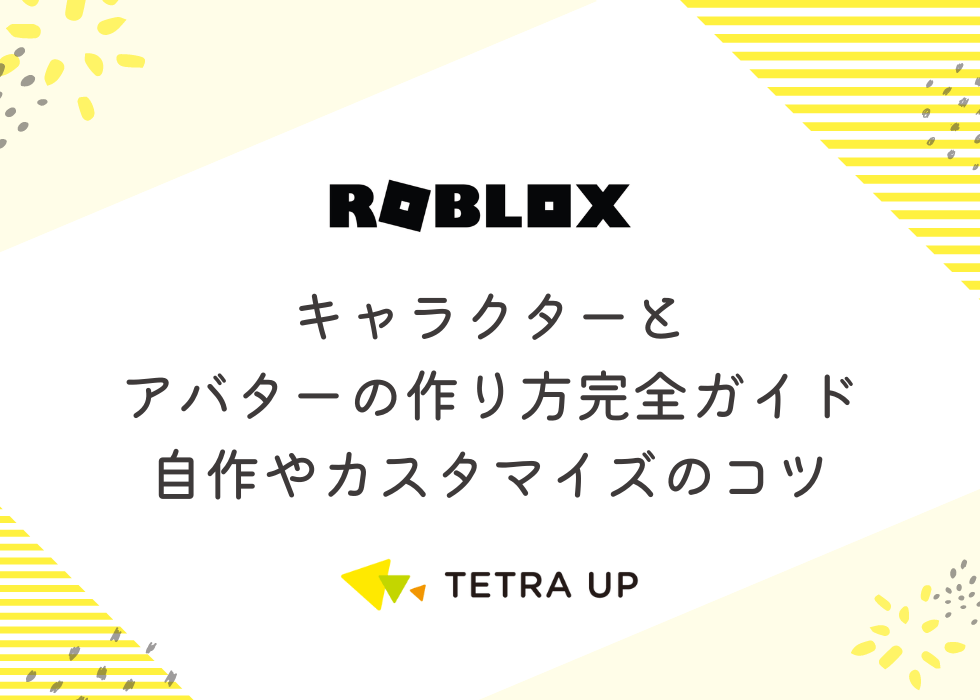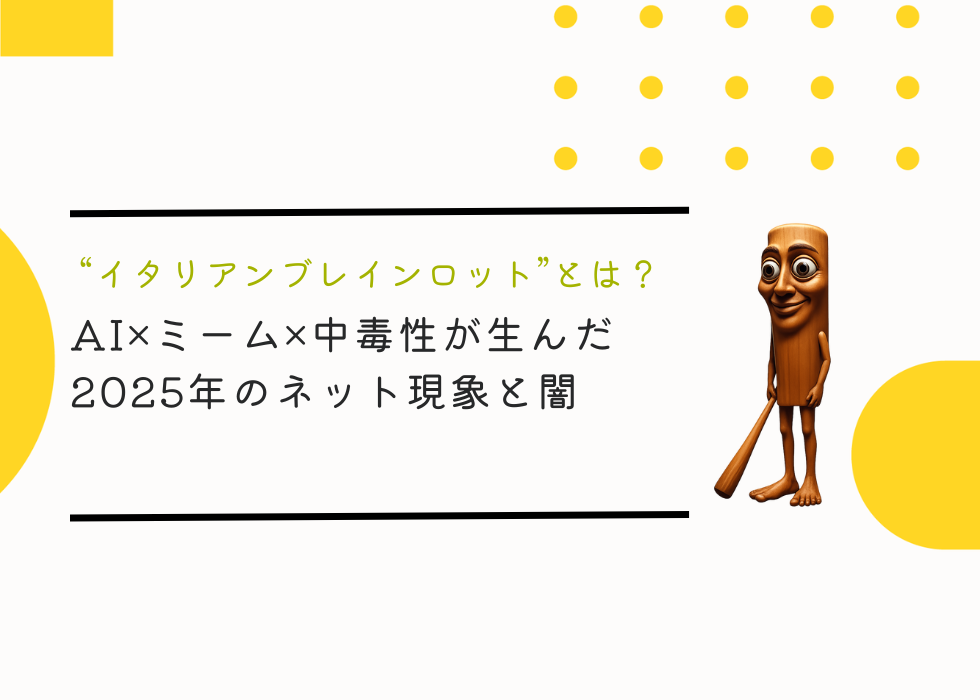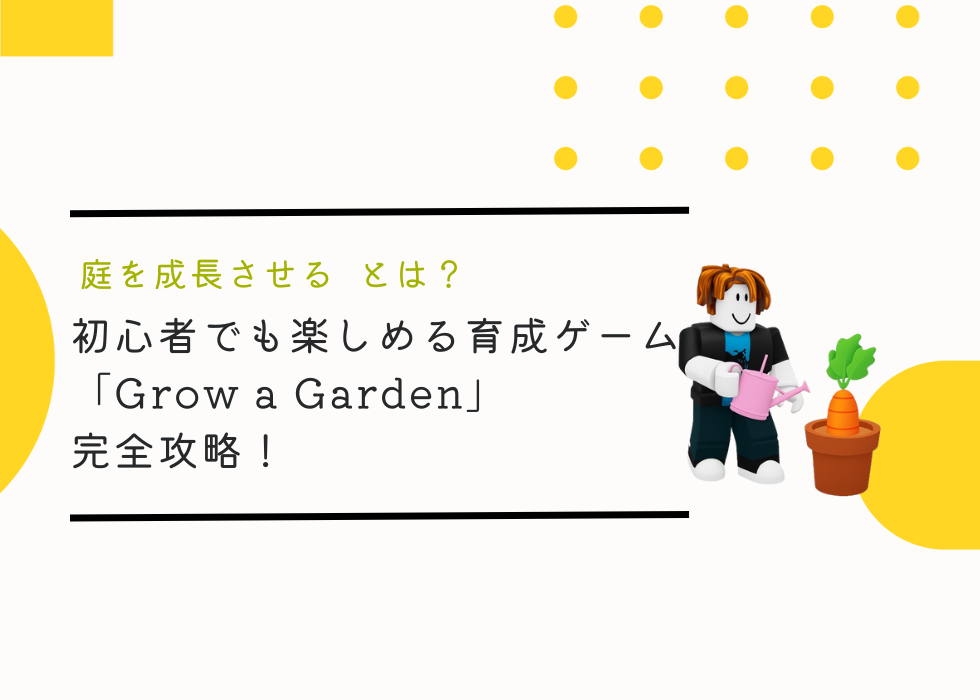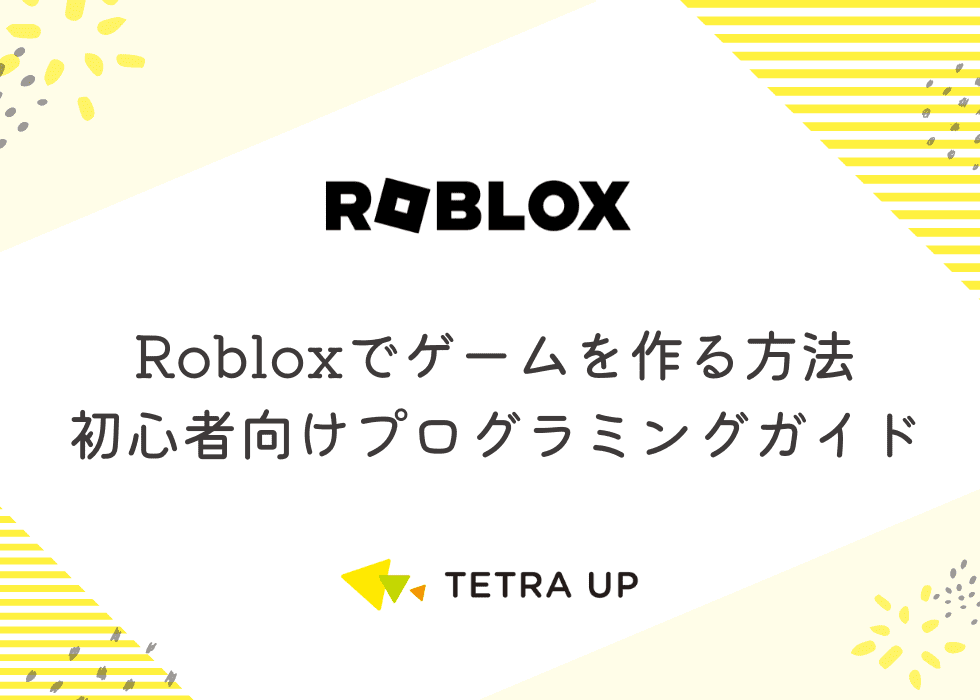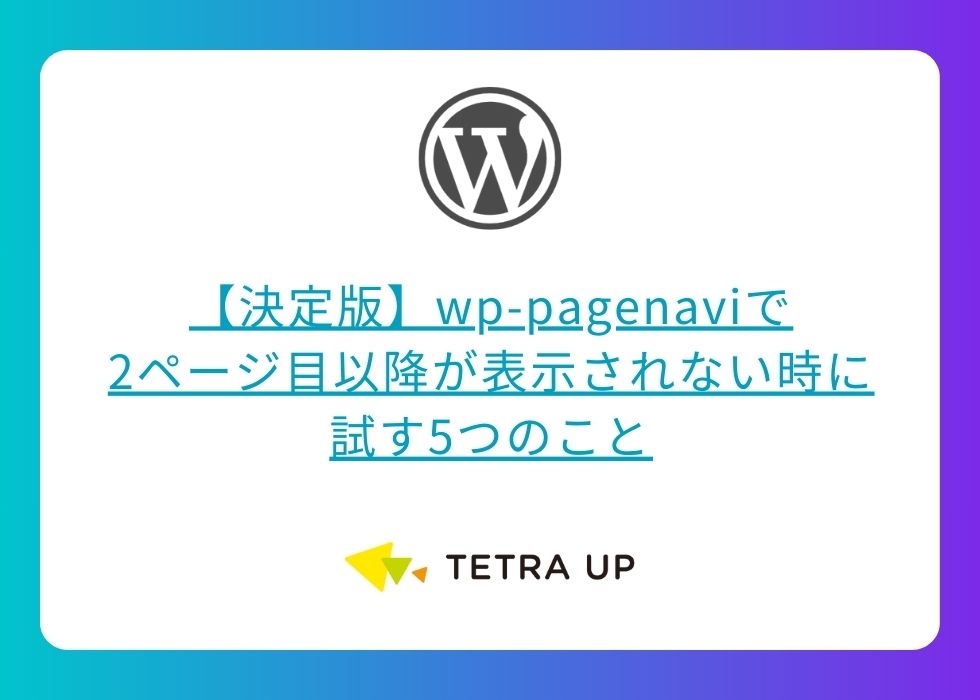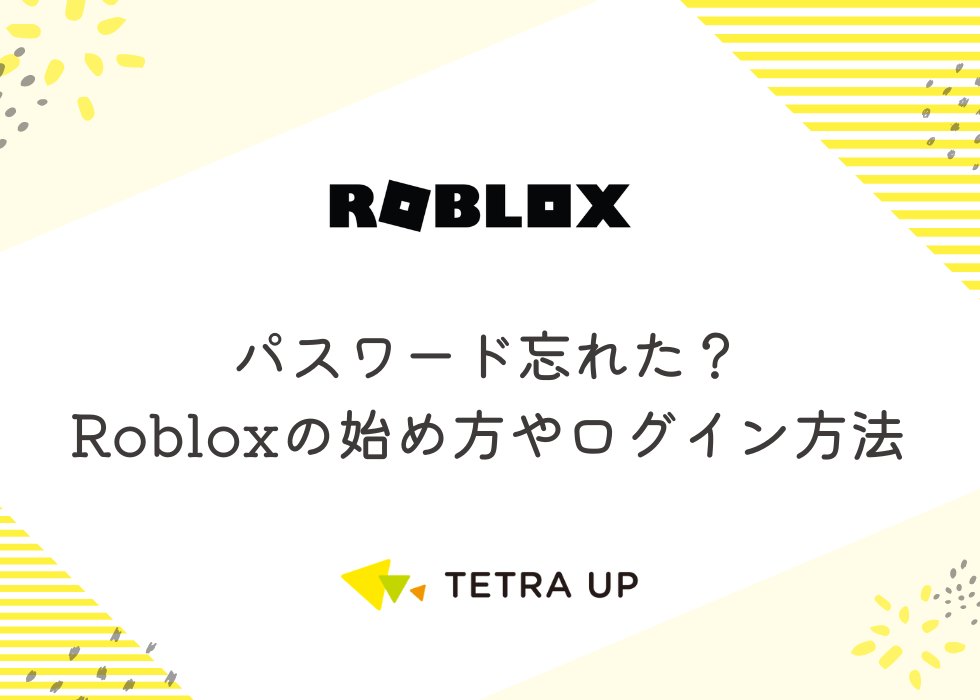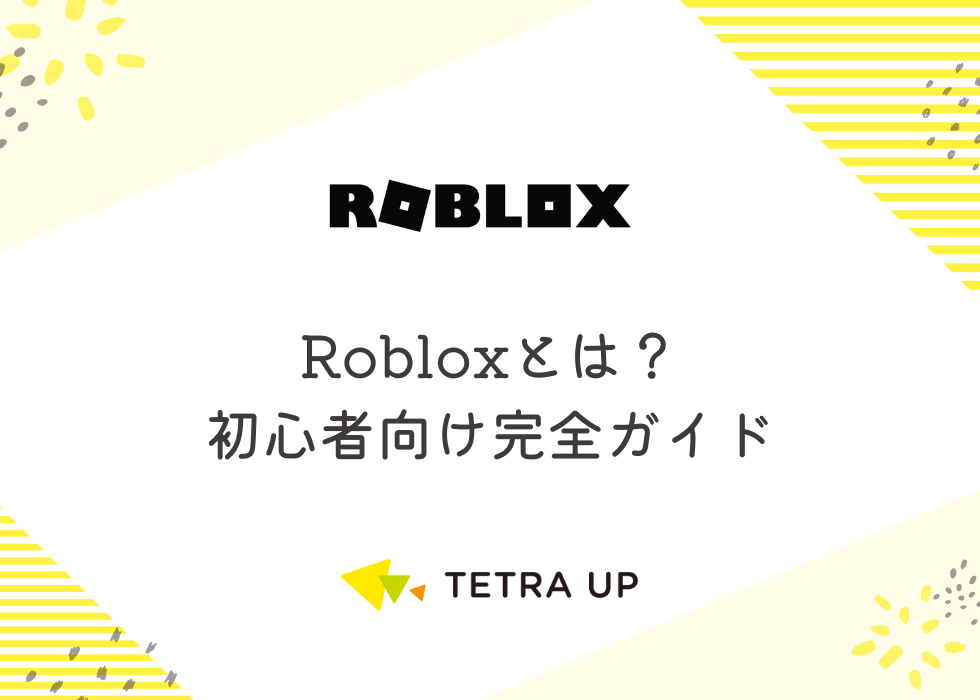【現役講師が解説】子どものゲーム依存を防ぐ方法と健全なデジタル活用のヒント
コラム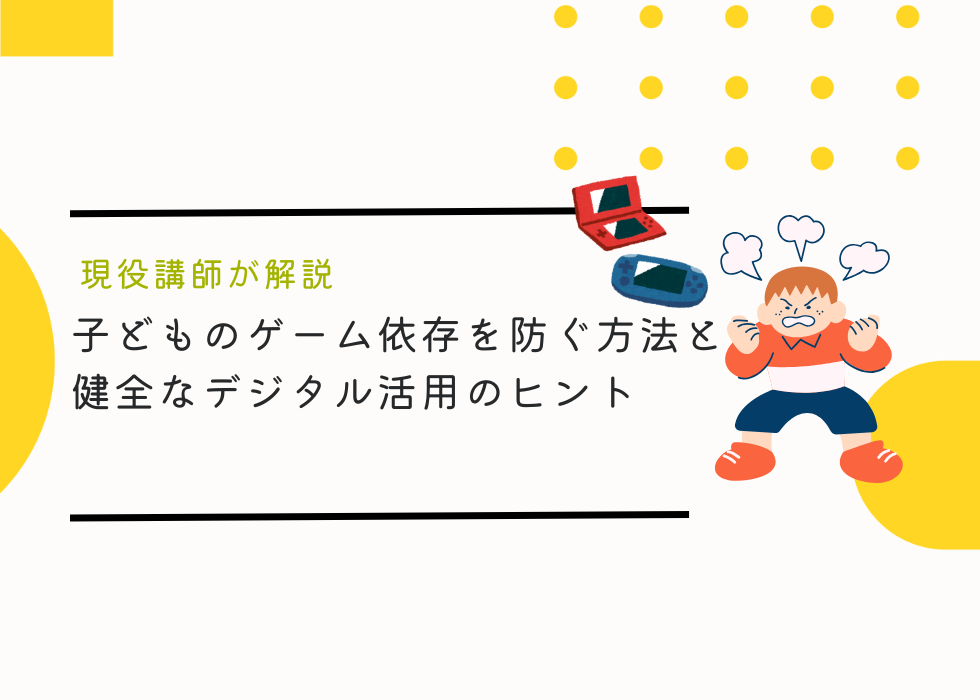
近年、スマホやタブレット、家庭用ゲーム機の普及により「子どものゲーム依存」が社会的な課題として注目されています。
「やるべきことをしないでゲームばかり」「約束の時間を守れない」と悩む保護者からの相談も少なくありません。
しかし、ゲームは必ずしも悪いものではありません。使い方次第で子どもの集中力や論理的思考を伸ばすきっかけになります。
本記事では、子どものゲーム依存の特徴や家庭でできる対策、そして“遊び”を“学び”に変える方法を詳しく解説します。
子どものゲーム依存とは?
世界保健機関(WHO)も「ゲーム障害」を正式に認定
世界保健機関(WHO)は「ゲーム障害(Gaming Disorder)」を正式に認定しました。
ゲーム依存の特徴は、生活に支障が出てもゲームを優先してしまうことです。
- 学校の宿題やテスト勉強を後回しにする
- 家族や友達との関係が悪化する
- 夜遅くまで遊んで生活リズムが乱れる
こうした状態が続く場合、単なる「ゲーム好き」ではなく依存の傾向があると感じたほうがよいでしょう。
「ただゲームが好き」と「依存」を見極めるポイント
保護者が早めに気づけるよう、チェックしたいポイントを挙げます。もし複数当てはまる場合は、生活習慣を見直すタイミングかもしれません。
- ゲームをやめるよう言っても強く反発する
- ゲーム以外の遊びや学習に興味を示さない
- 怒りっぽくなる、感情の起伏が激しい
- 睡眠不足で朝起きられないことが増える
子どもはまだゲームとの付き合い方を知りません。
出来るだけ早めに対処して、大人になってもゲームとうまく付き合っていける力を伸ばしていきたいですね。
家庭でできるゲーム依存対策
子どものゲーム依存を防ぐには、禁止ではなく「ルール」と「代替体験」が大切です。
1.時間のルールを決める
「平日は1時間まで」「夜8時以降は遊ばない」など、親子で話し合って決めると効果的です。
決めるときにも、一方的に親が決めるのではなく、なるべく子どもの意見を聞きとりいれていきましょう。
2.代替アクティビティを用意する
スポーツや工作など、夢中になれる別の体験を見つけることで「ゲーム以外の楽しみ」が広がります。
意識を逸らすというのも1つの手ですね。
3.一緒に遊ぶ・学ぶ
保護者も一緒に関わると、ゲームが家族コミュニケーションのきっかけや、子ども達が遊ぶゲームやオンラインの世界を知るきっかけになります。
最近のゲームはチームを組んでクリアしたり、1時間では完結できないゲームもたくさんあります。
保護者がそれを知っていると「確かにあのゲームだと1時間では、終わらないよね。じゃあ休日だけ2時間にするのはどうかな」などの提案が出来るでしょう。
また子ども達がどのようにオンラインでやりとりしているかを知ると、「この子はきちんと”寝るからやめるね”と言えているよ。」と事実を伝えることが出来ます。
当教室では、ただ「ゲームをやめさせる」のではなく、プログラミングを通じて“ゲームを作る側”の視点を育てています。
お子さまが夢中になるゲームを「学びの入り口」に変えてみませんか?
プログラミング教育がゲーム依存を防ぐ理由
ゲーム依存の背景には「受け身で遊ぶだけ」という特徴があります。
一方、プログラミングはゲームを「作る体験」に変えることができます。
- ゲームの裏側を知ると、仕組みに興味を持つ
- 「遊ぶ側」から「作る側」へと意識が変わる
- 自分で作ったゲームを家族に見せることで、自己肯定感や達成感が育つ
当プログラミング教室では、小学1年生からゲーム制作を体験できます。
「ただ遊ぶ」から「作って発表する」へ。お子さまのデジタルとの関わり方が大きく変わります。
まとめ
子どものゲーム依存は、完全にゲームを取り上げるのではなく、健全なルールと新しい選択肢を与えることで解決に近づきます。
もし「ゲームばかりで心配…」と感じているなら、ゲームを学びに変える一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
お子さまの「ゲーム好き」を「学び好き」へ変えるチャンスです。お気軽にお問い合わせください。
国内外の幼児~小学校教育に携わり、現在子ども向けプログラミング講師として従事。
ただプログラミングを教えるだけではなく、子ども1人1人と保護者、そして教室と相互に関わり合い成長していけるように日々取り組んでいます!