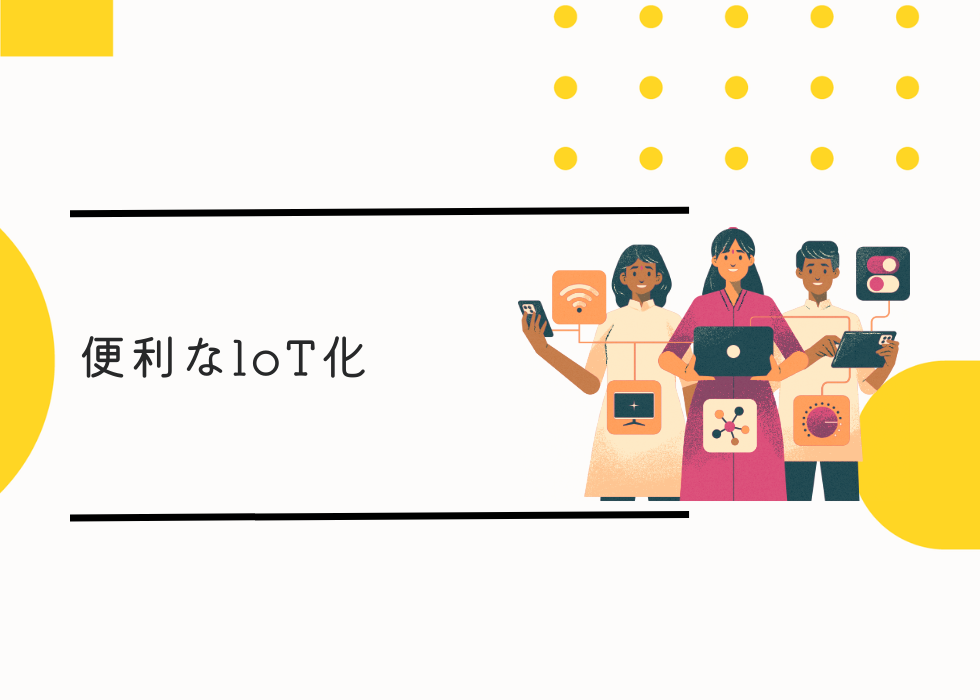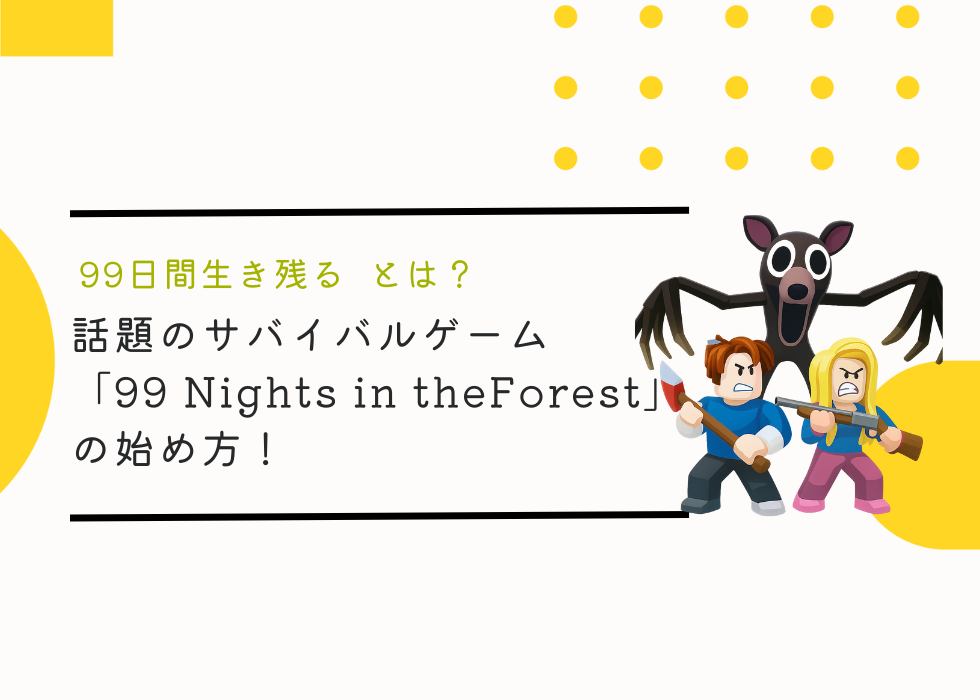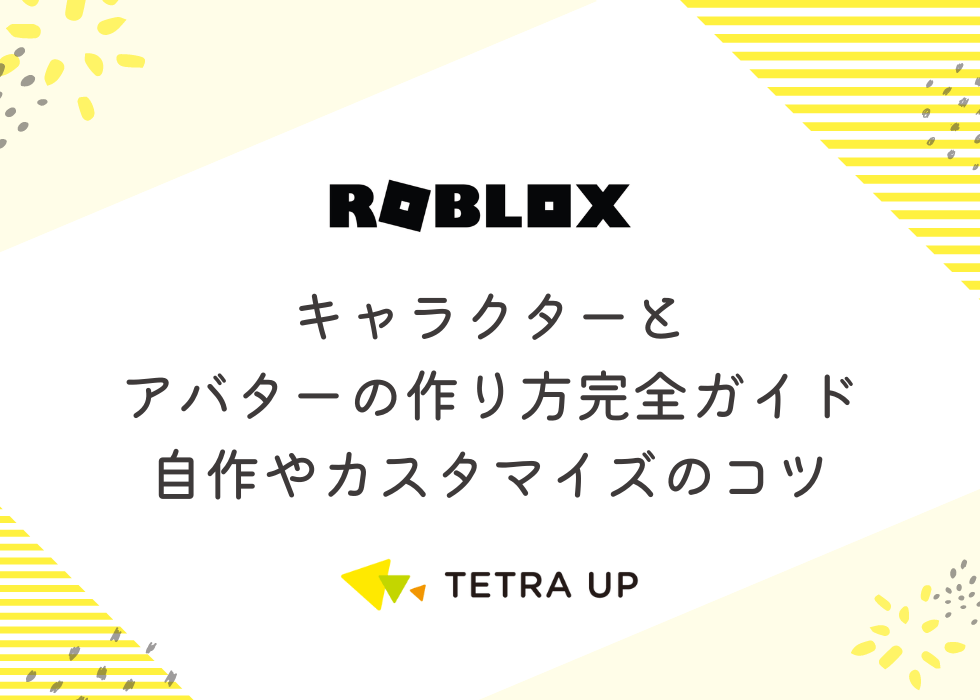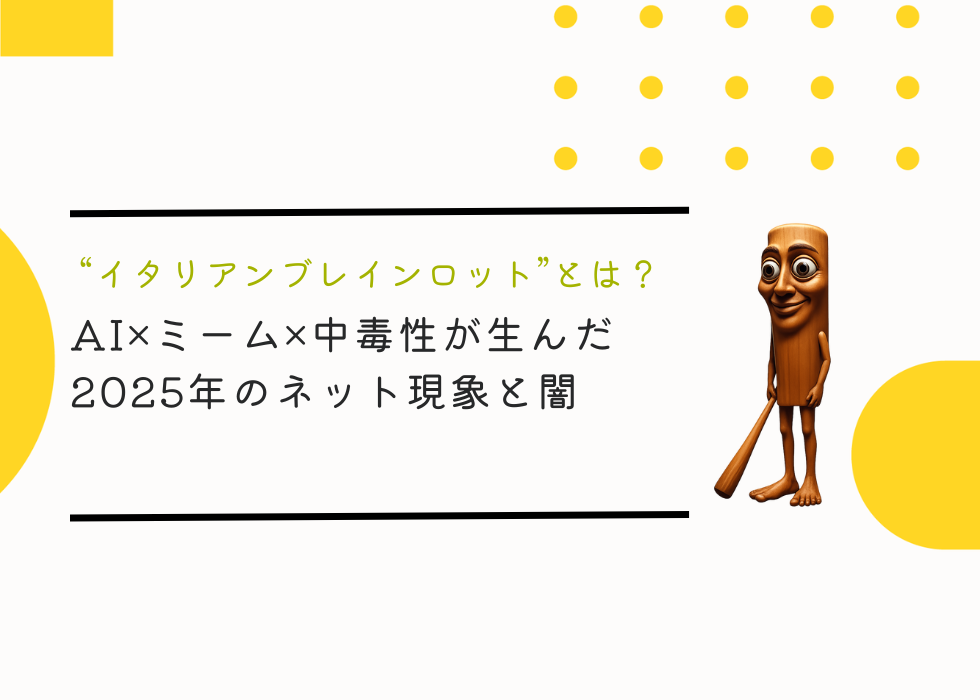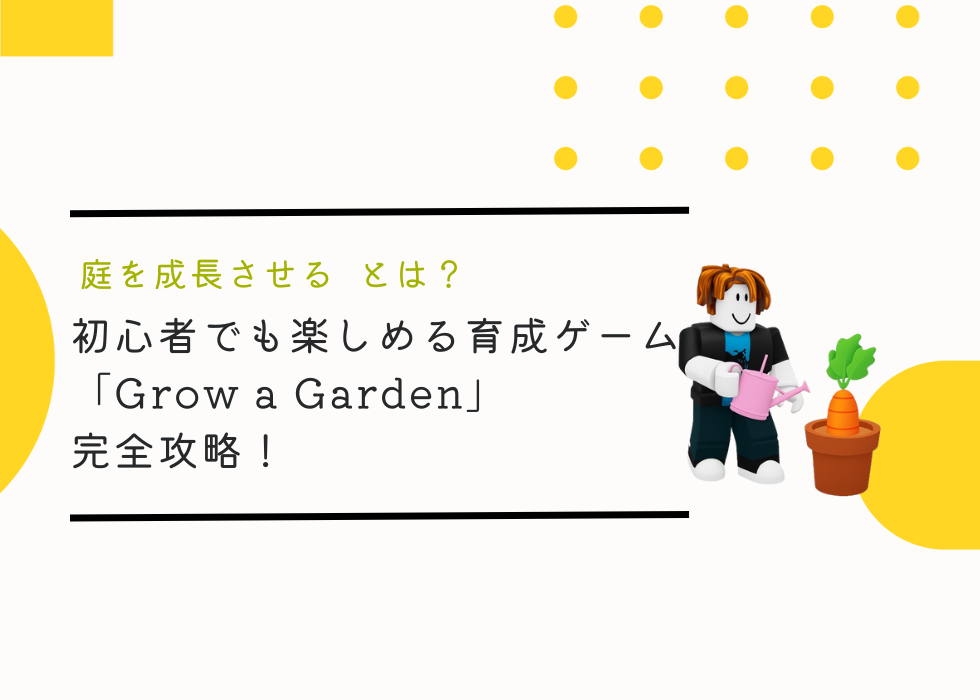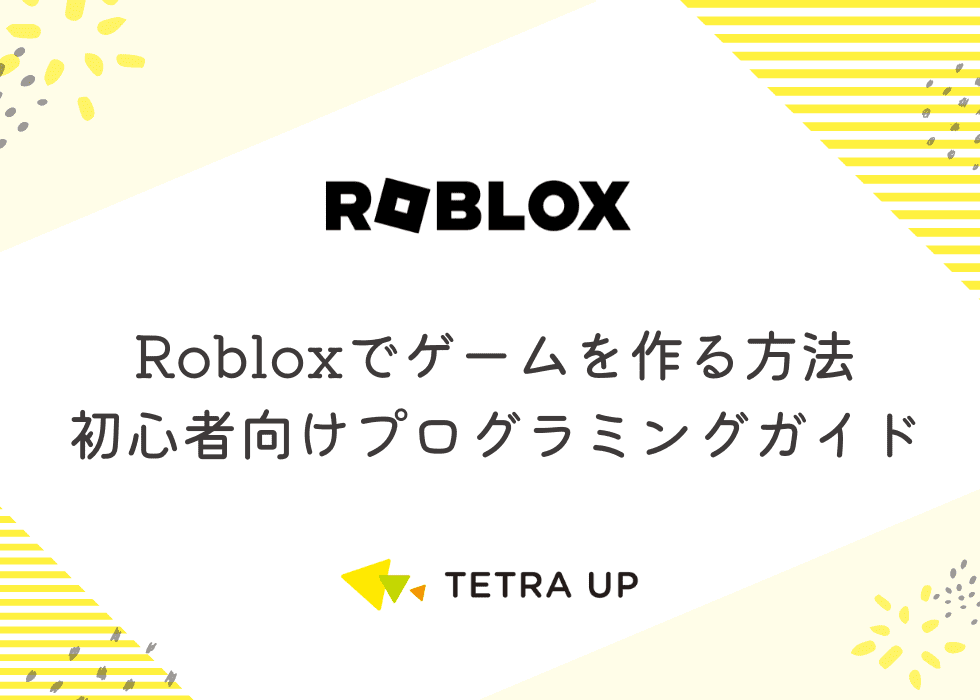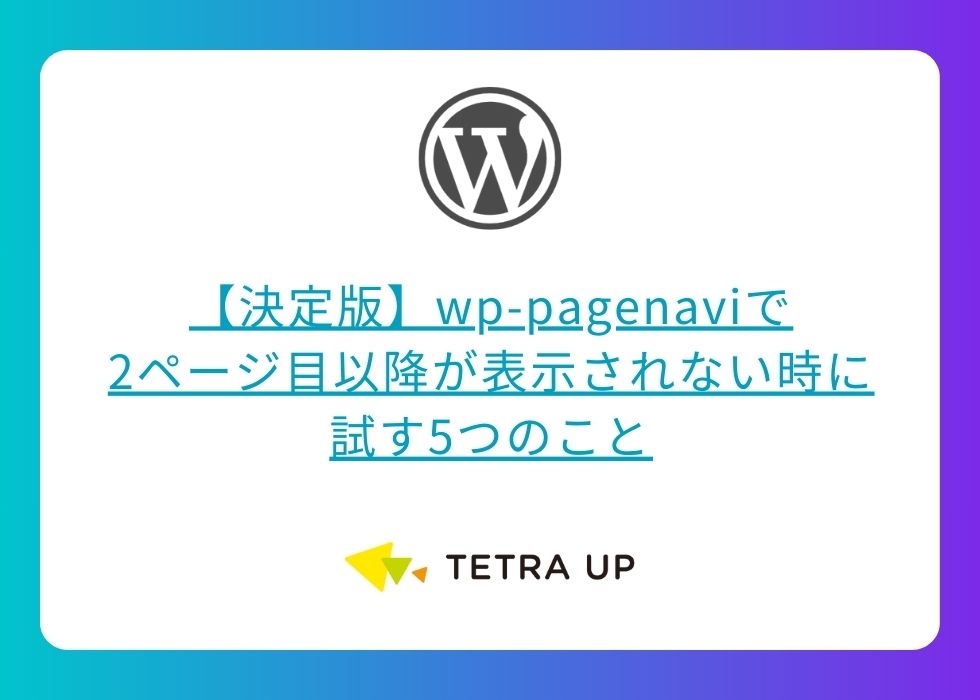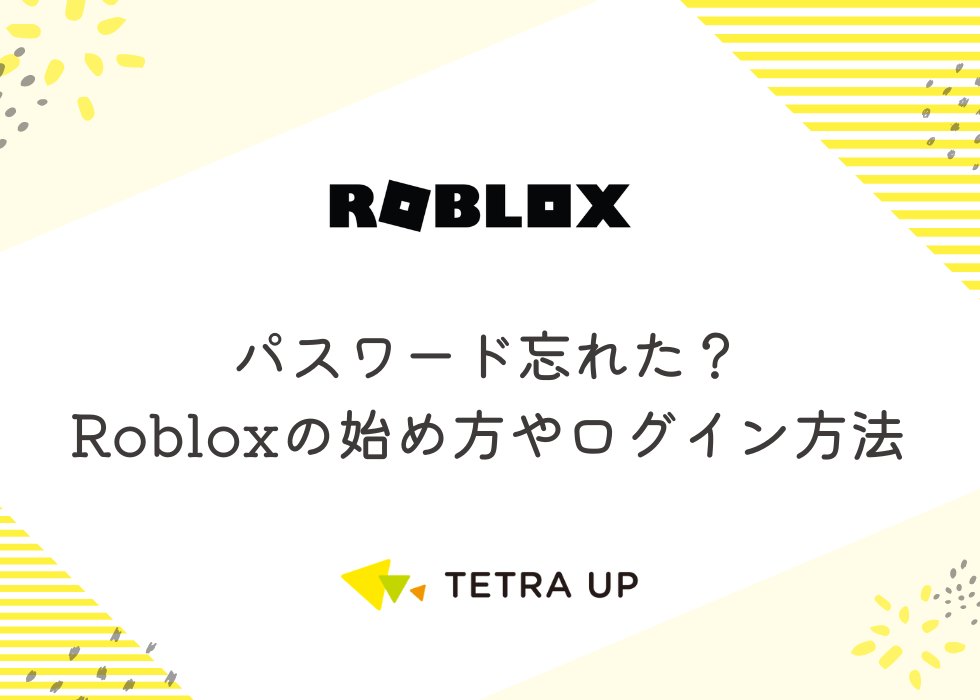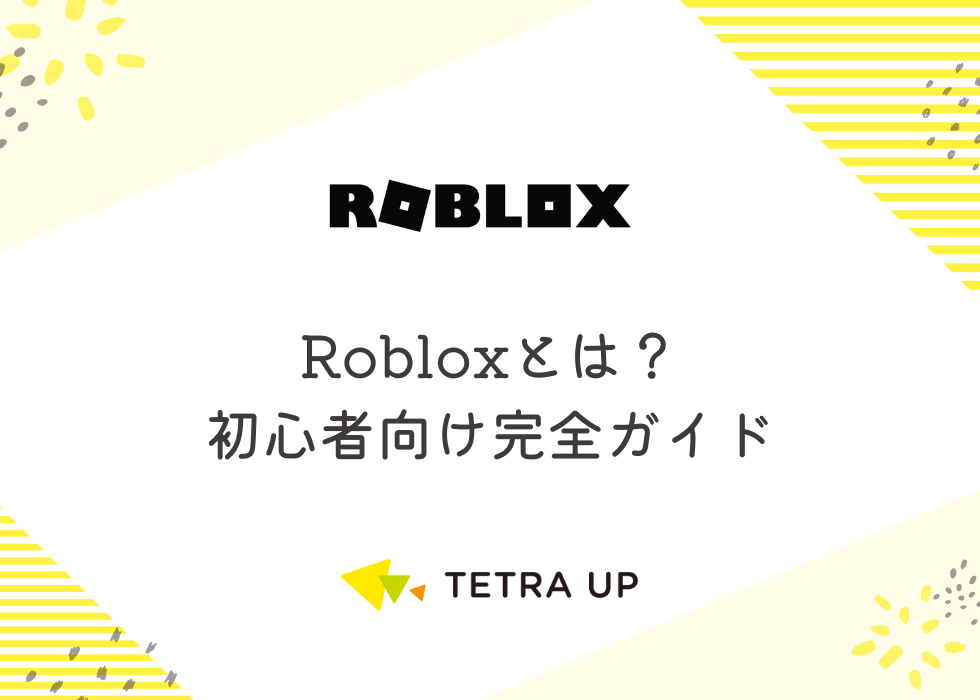-
ドローンの有効活用
コラム詳細を見る▶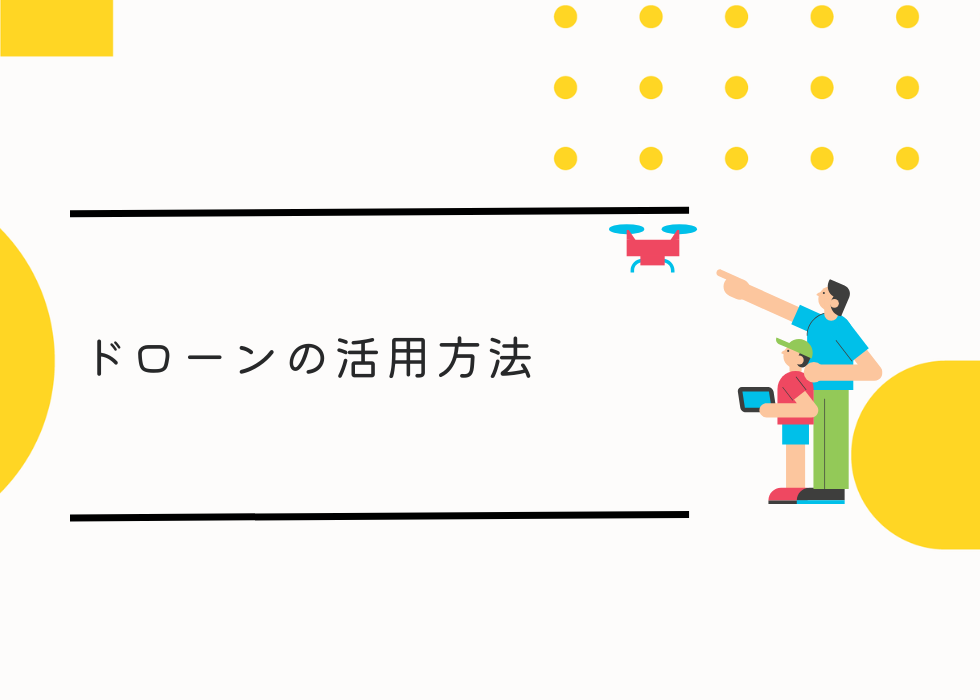
-
ロボット活用ナビ
コラム詳細を見る▶
-
ビデオゲームの墓場 -1980年代のゲーム市場-
コラム詳細を見る▶
-
ハンバーガーショップで働くロボットさん。
コラム詳細を見る▶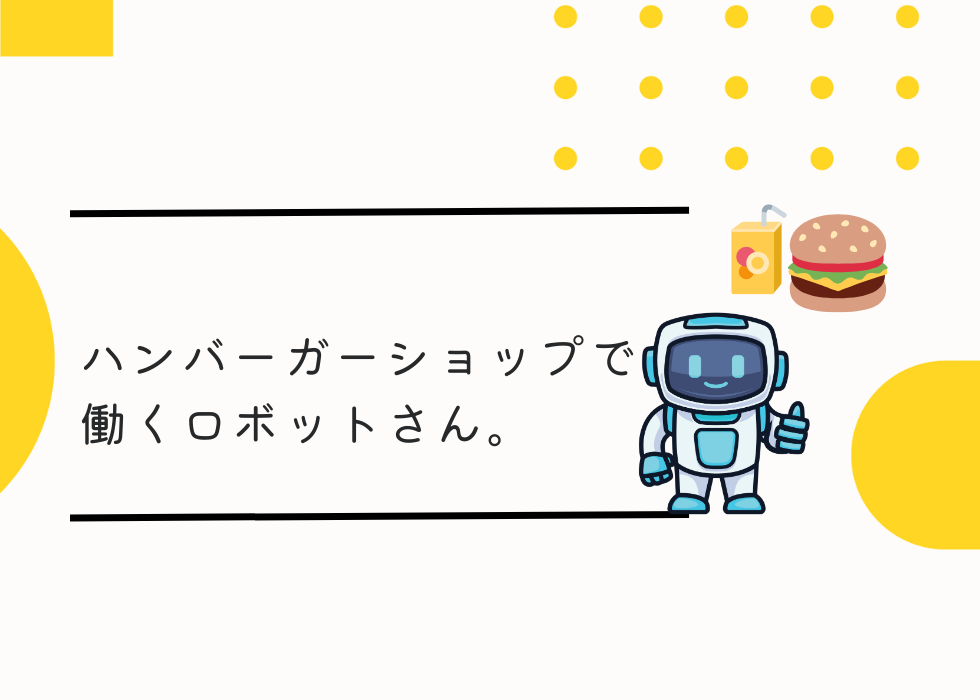
-
子供の頃に夢見たロボット
コラム詳細を見る▶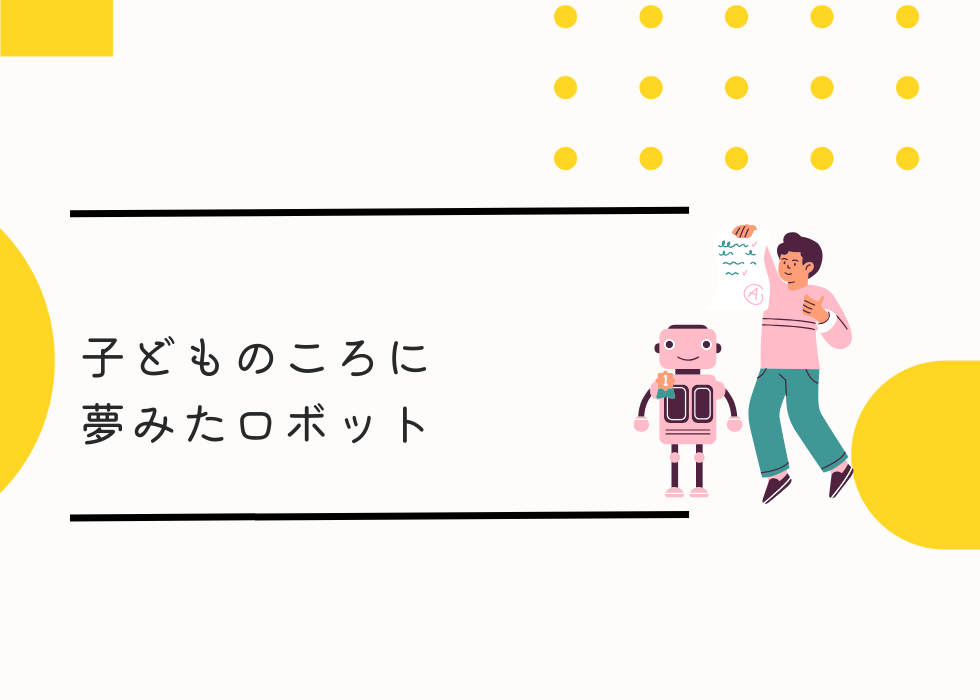
-
ウェブサイトを認知してもらう為に
コラム詳細を見る▶
-
プログラミング教室を知ったきっかけの40%が口コミか紹介
コラム詳細を見る▶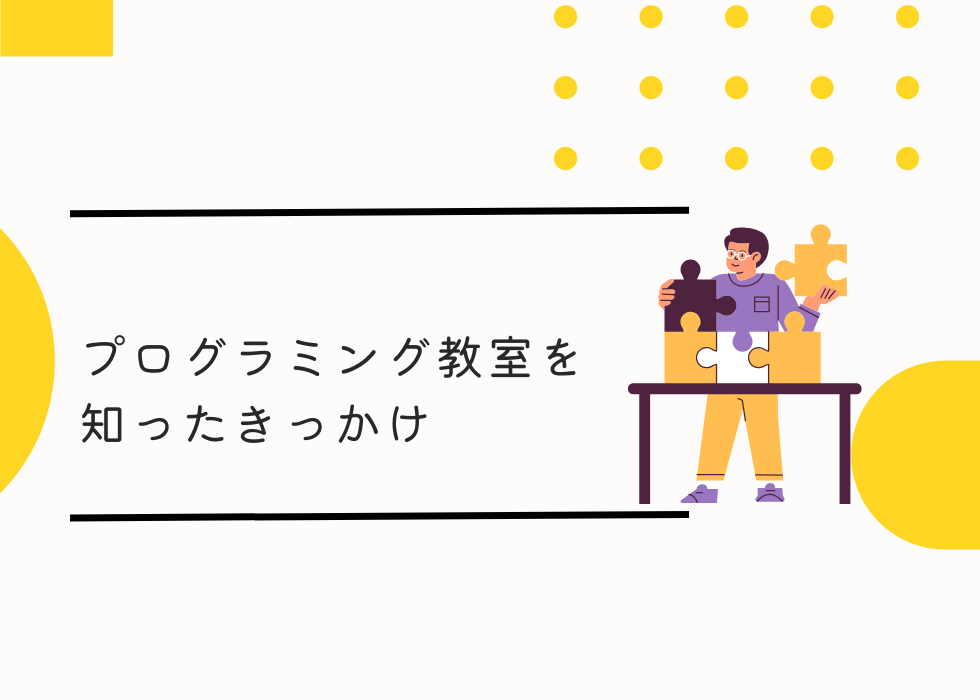
-
車の自動運転レベル
コラム詳細を見る▶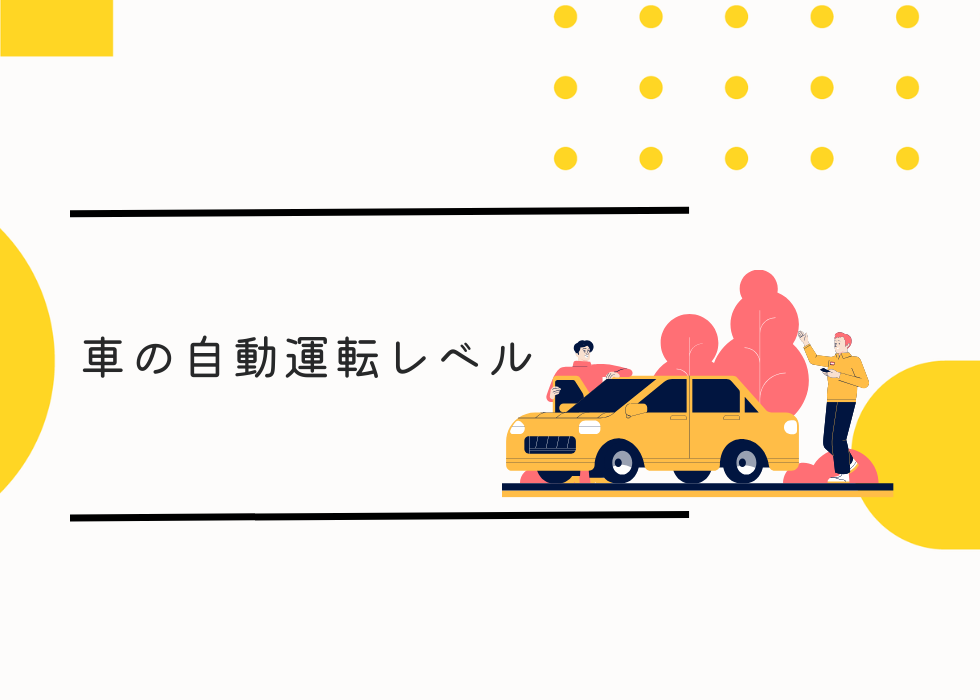
-
e-ラーニングのメリット・デメリットと今後
コラム詳細を見る▶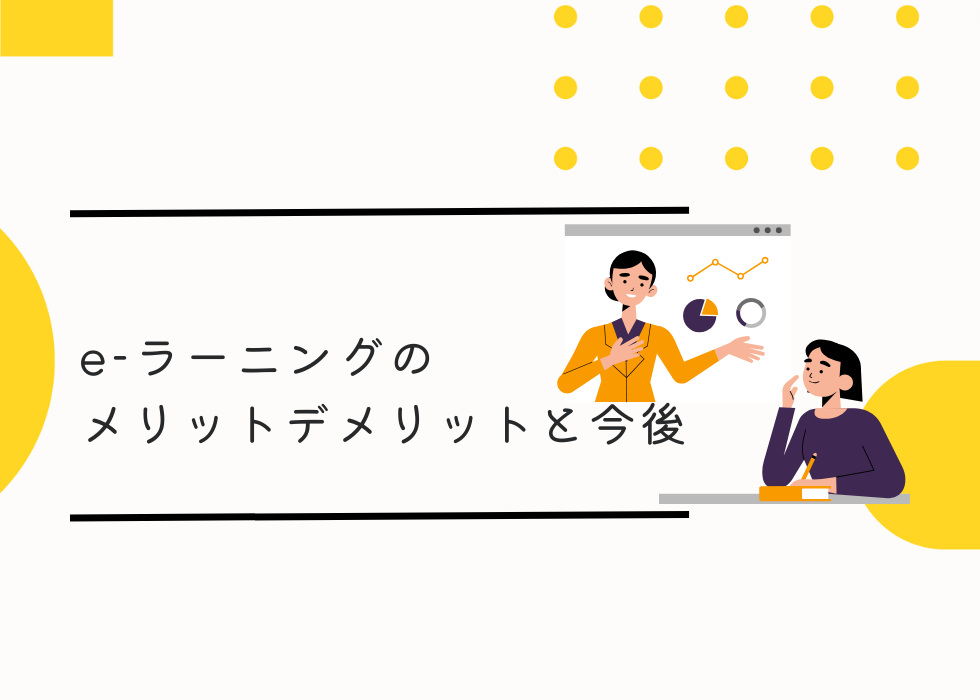
-
便利なIoT化
コラム詳細を見る▶