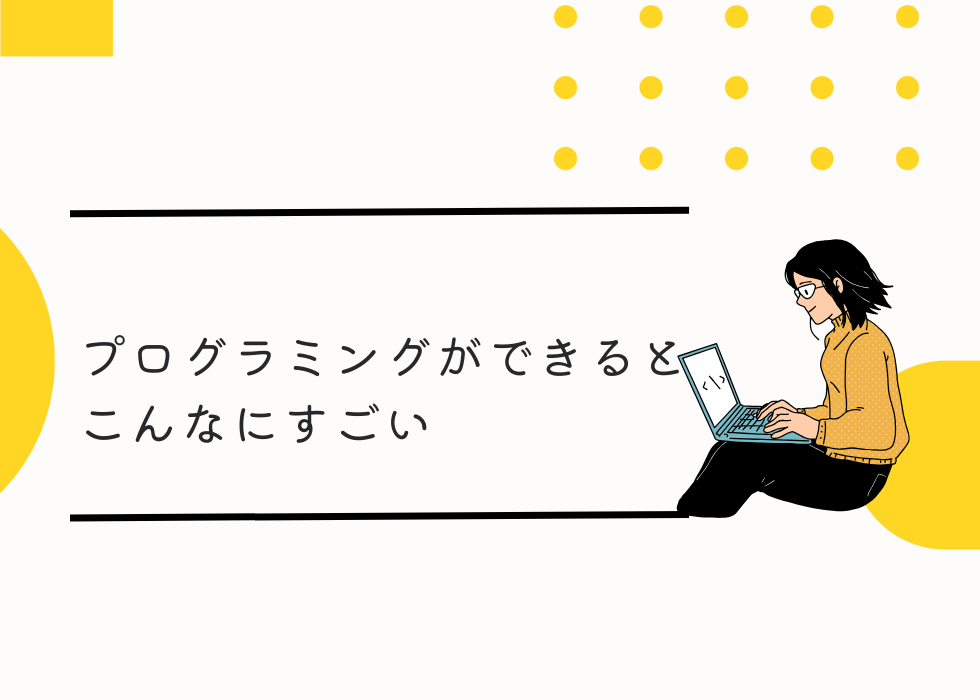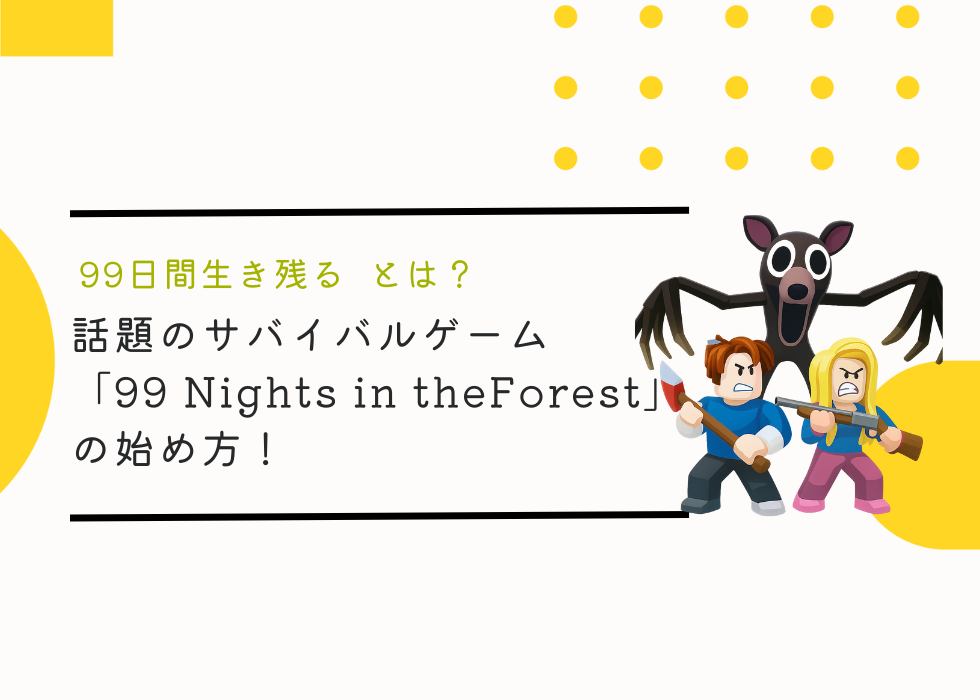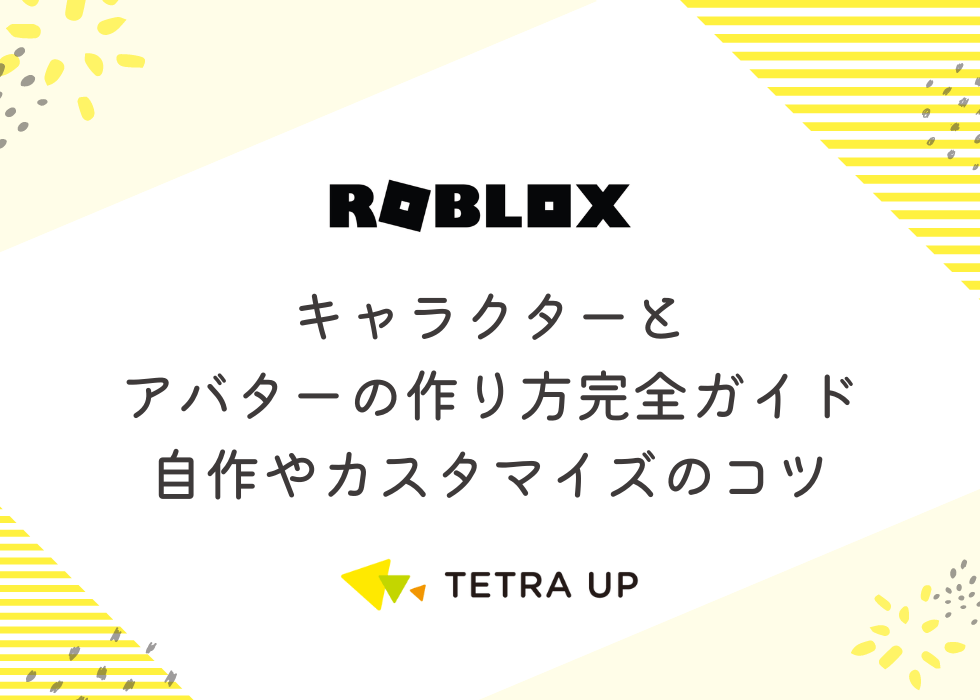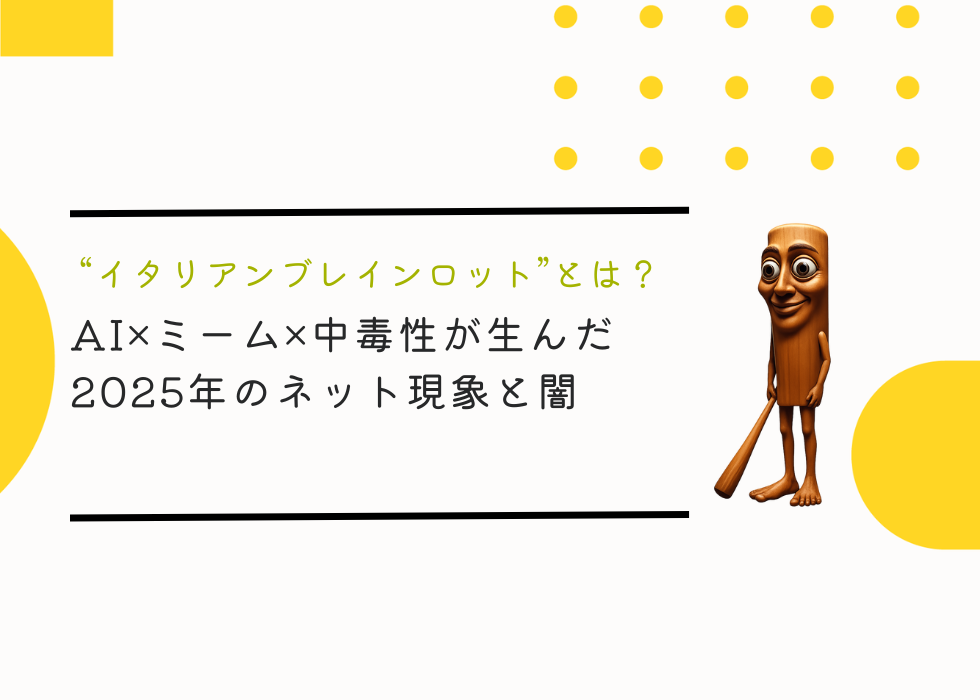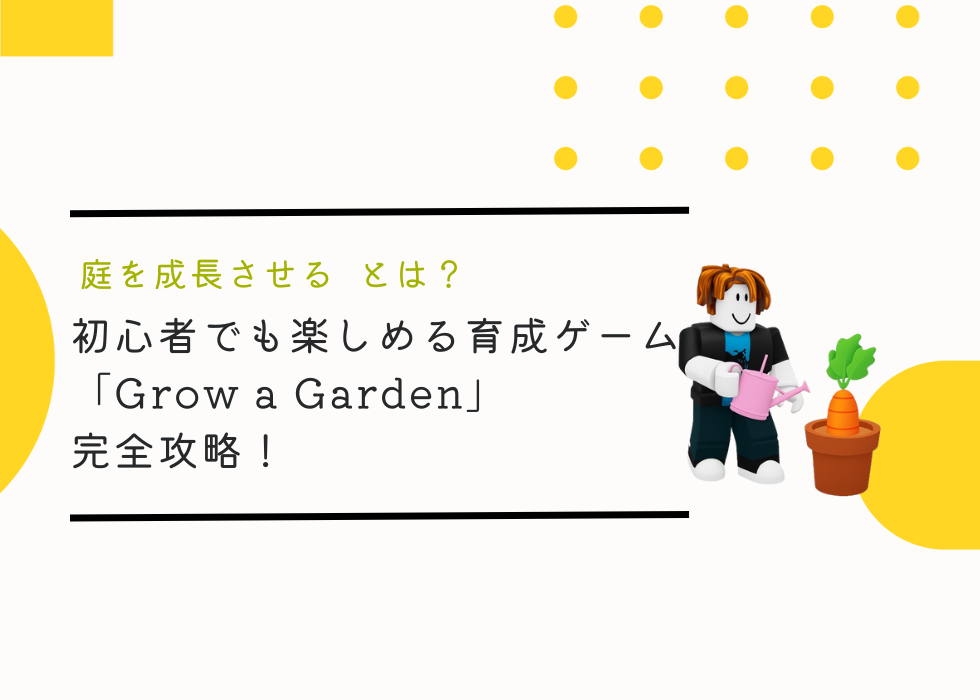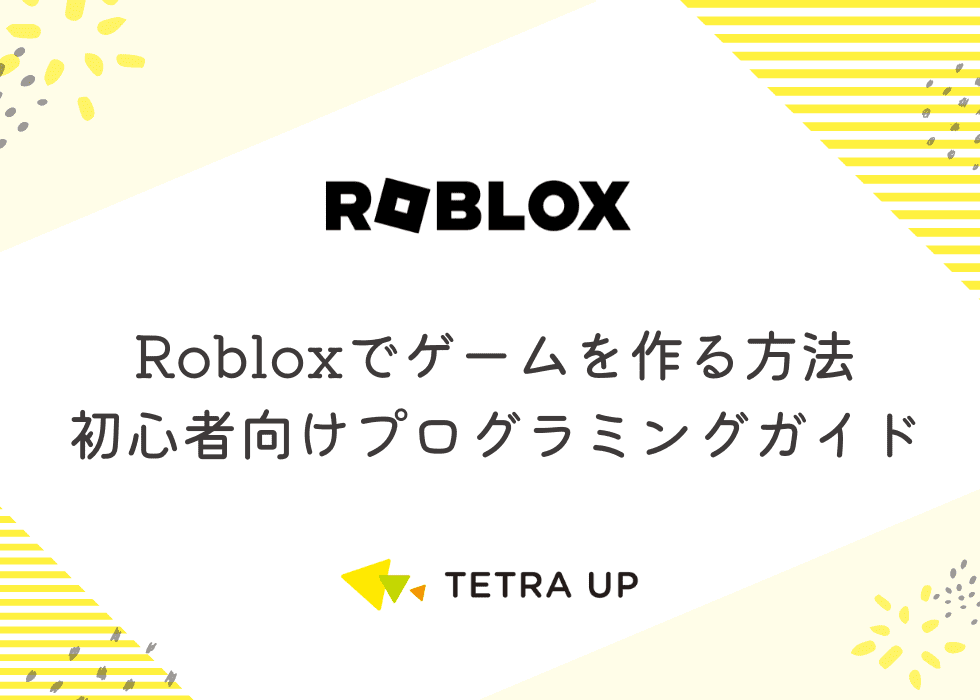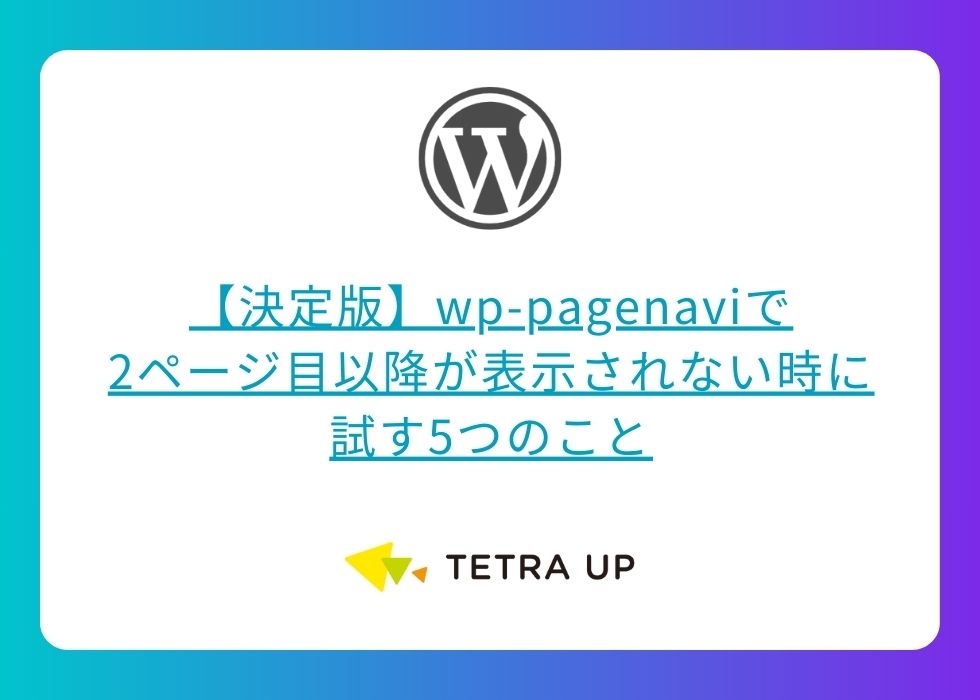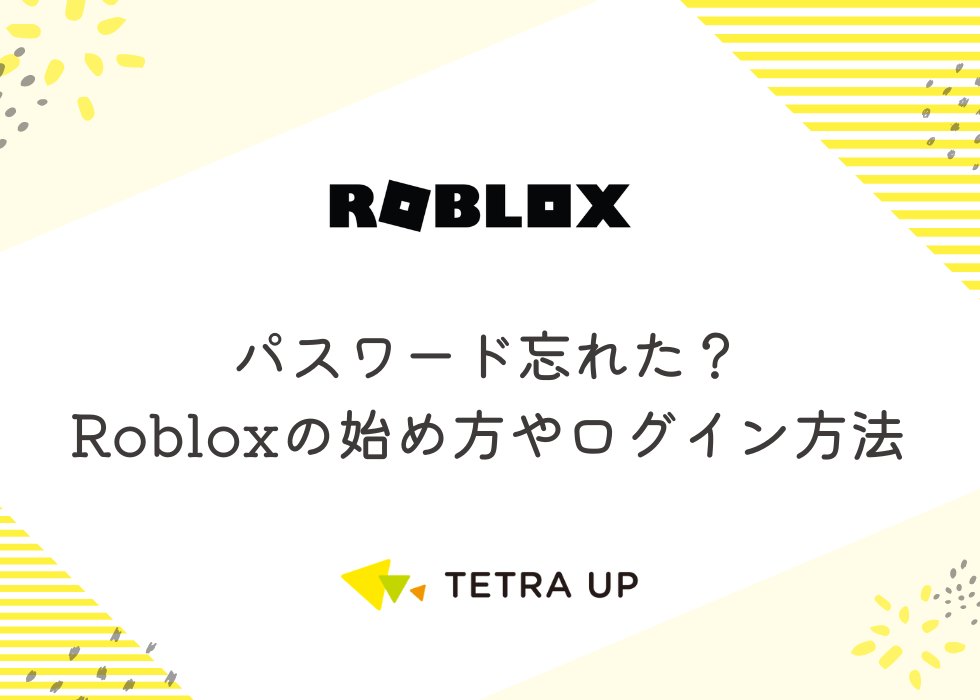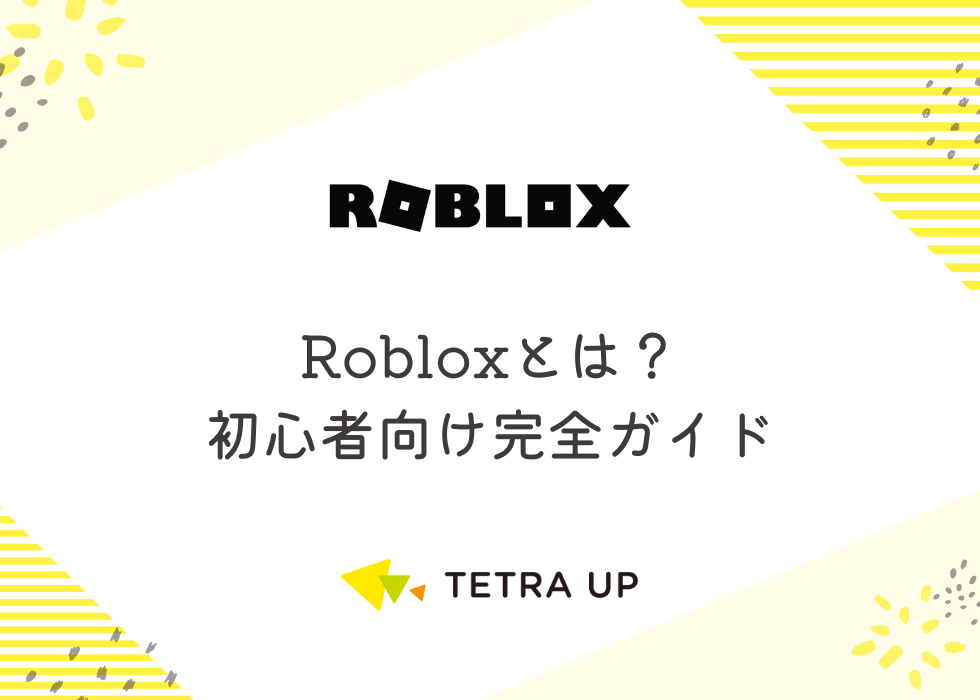-
サイバーセキュリティ月間
コラム詳細を見る▶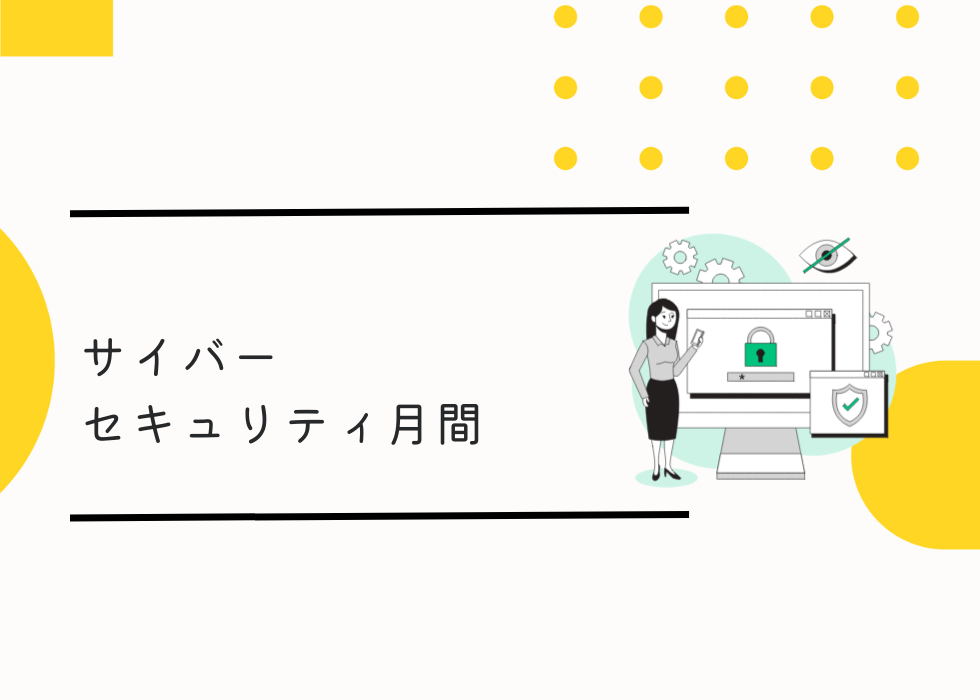
-
医療のICT化
コラム詳細を見る▶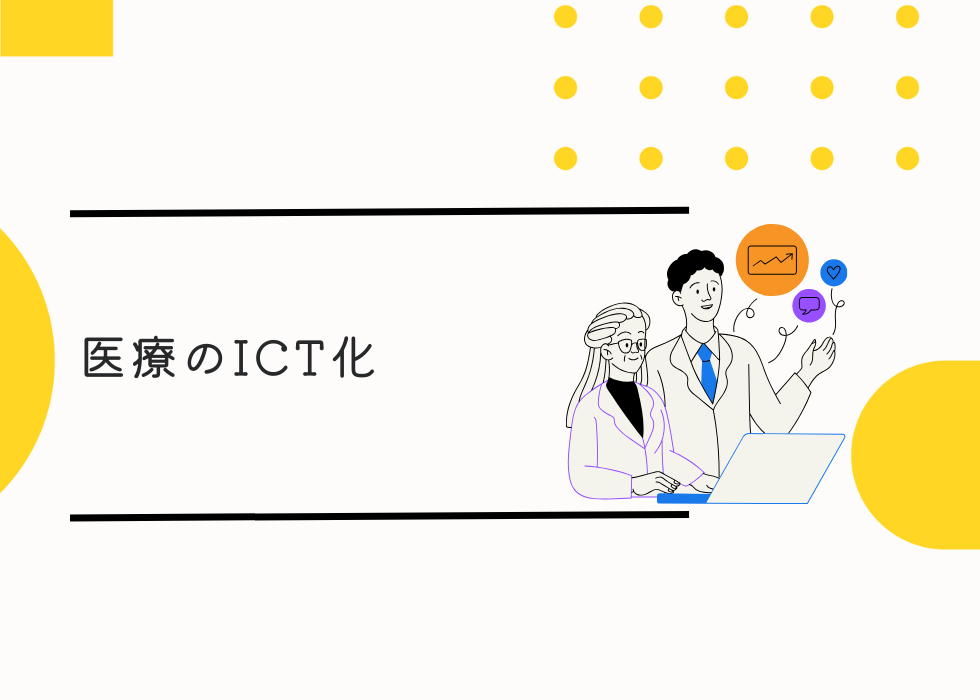
-
エンジニアも非エンジニアも。 IPAの情報処理技術者試験
コラム詳細を見る▶
-
シンギュラリティ(技術的特異点)とレイ・カーツワイル氏
コラム詳細を見る▶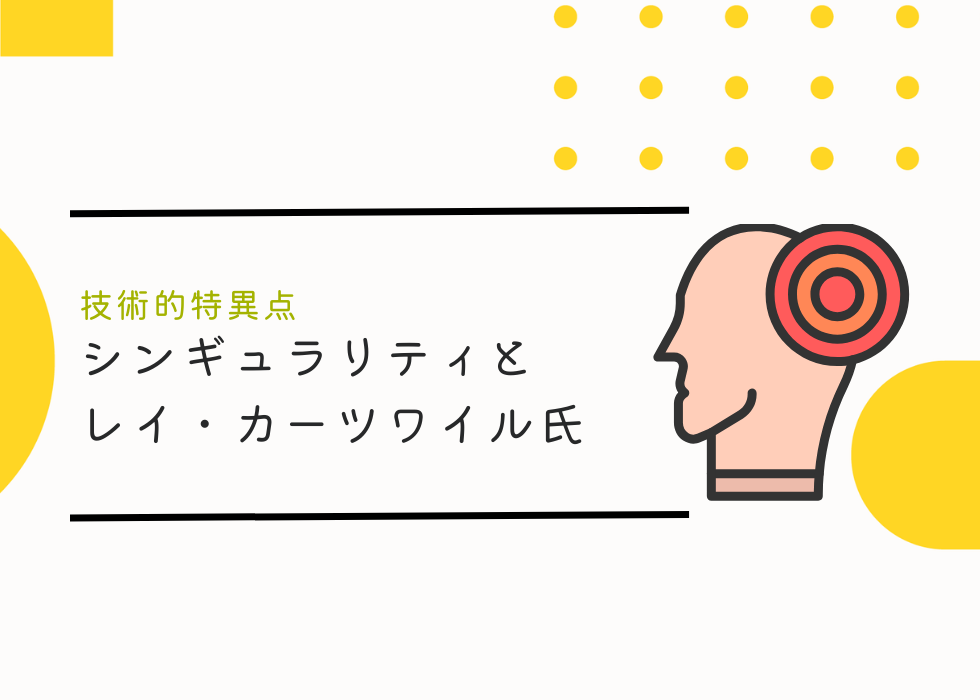
-
プログラミング必修化目前。小学生向けプログラミング入門3選
コラム詳細を見る▶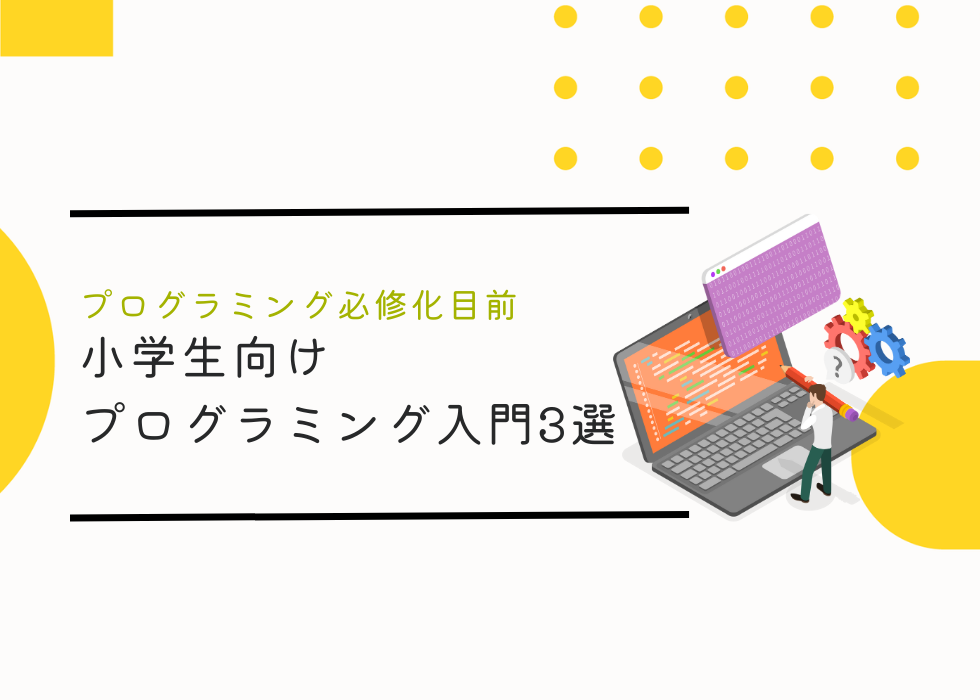
-
有意義なネットサーフィン
コラム詳細を見る▶
-
マルウェアとその脅威
コラム詳細を見る▶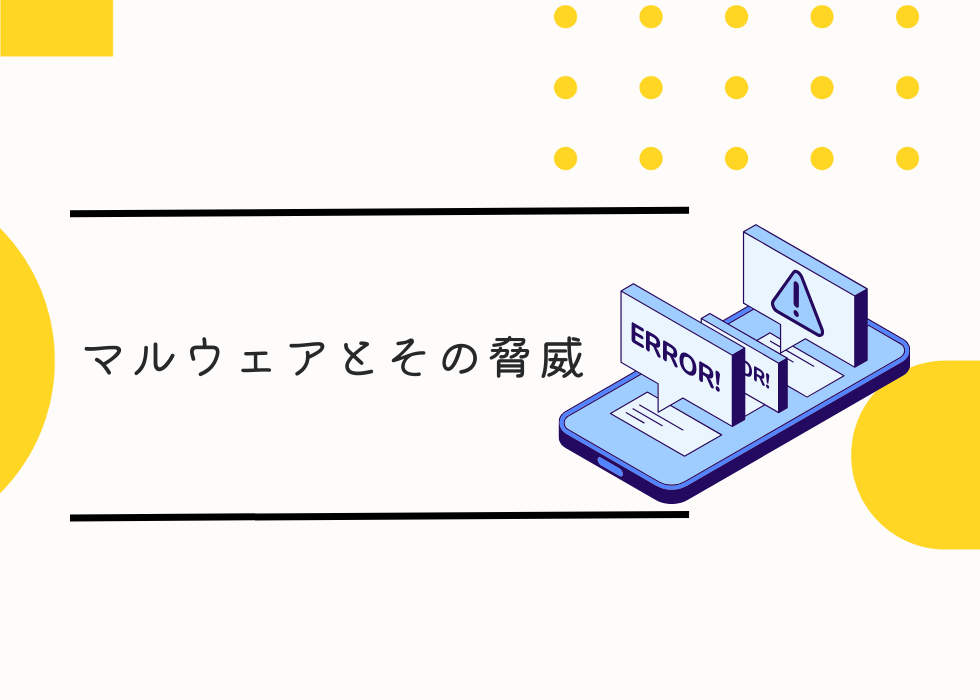
-
LINEブログがもたらす革命
コラム詳細を見る▶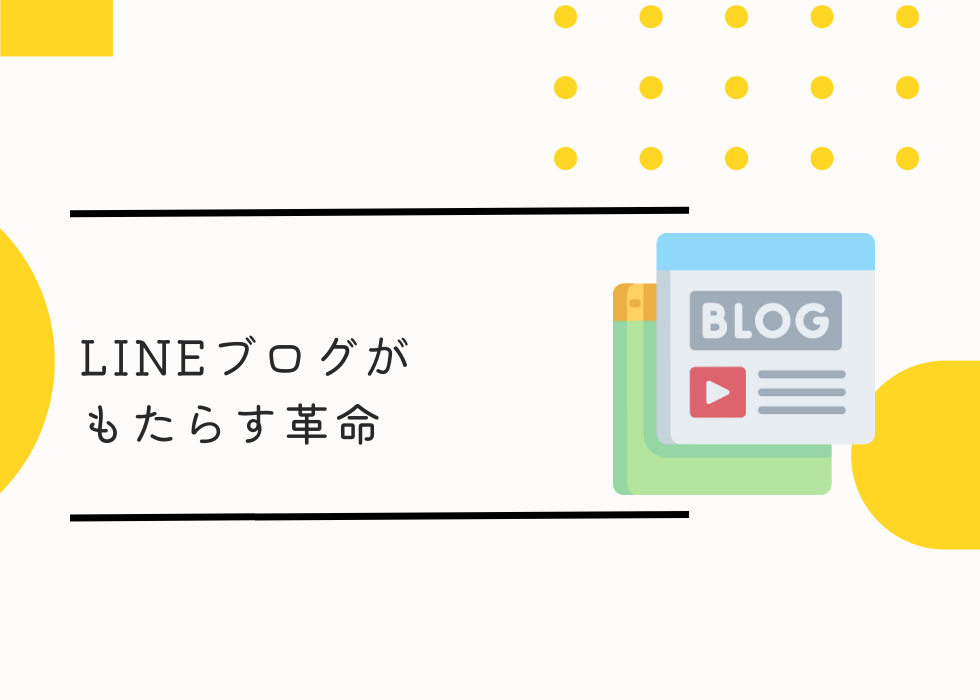
-
Scratch(スクラッチ)の拡張性
コラム詳細を見る▶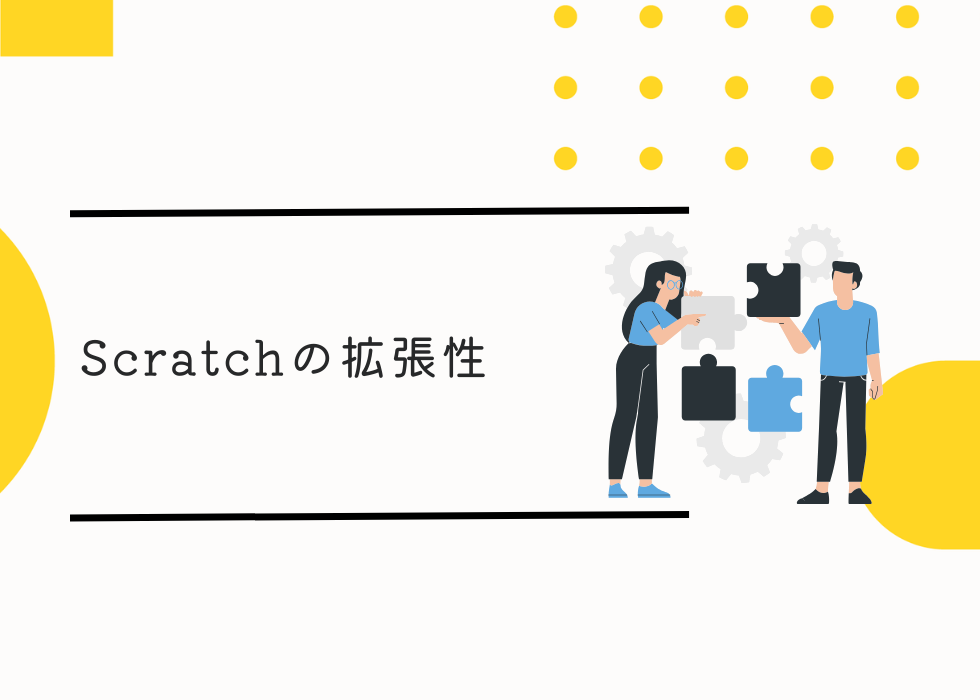
-
プログラミングができるとこんなに凄い
コラム詳細を見る▶