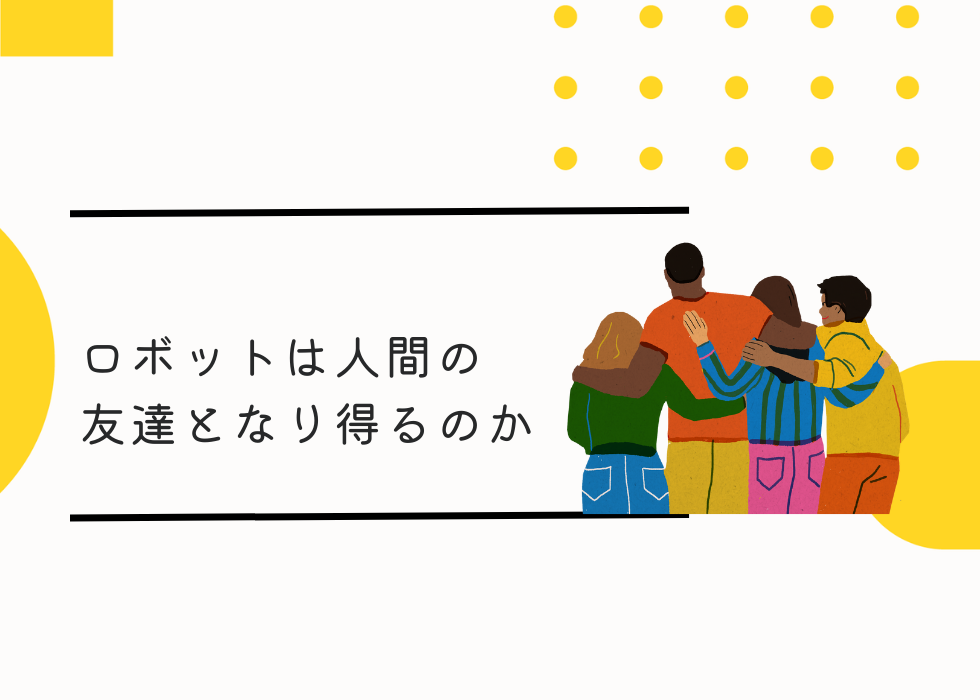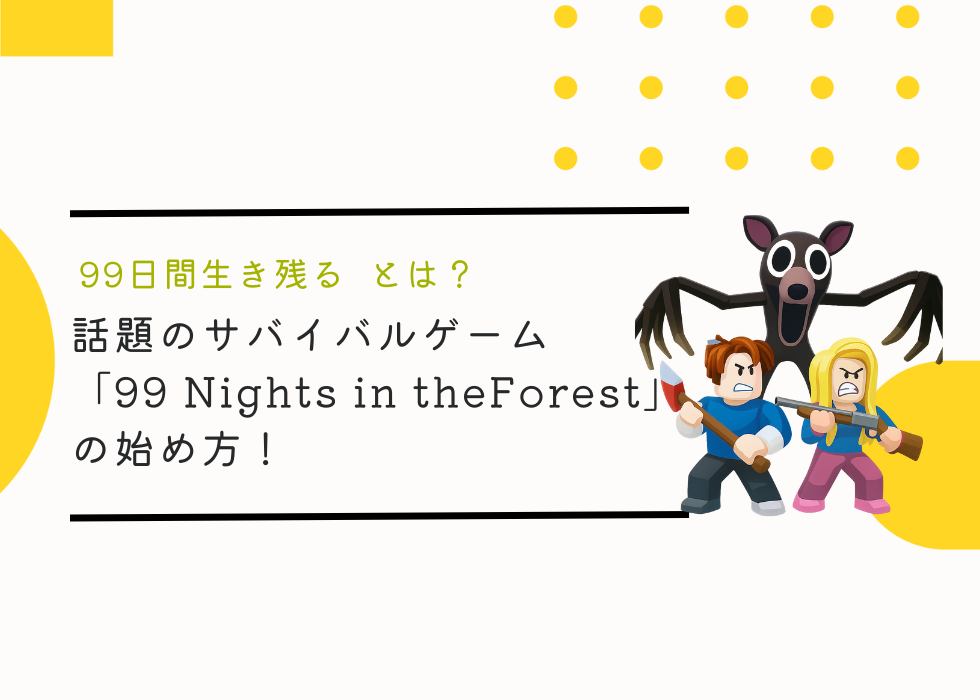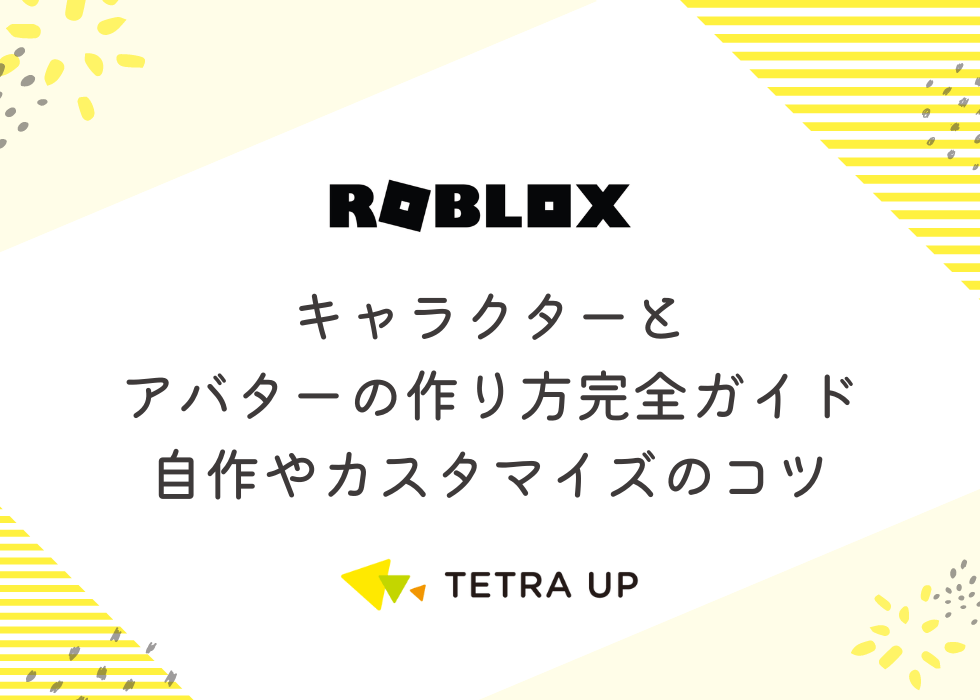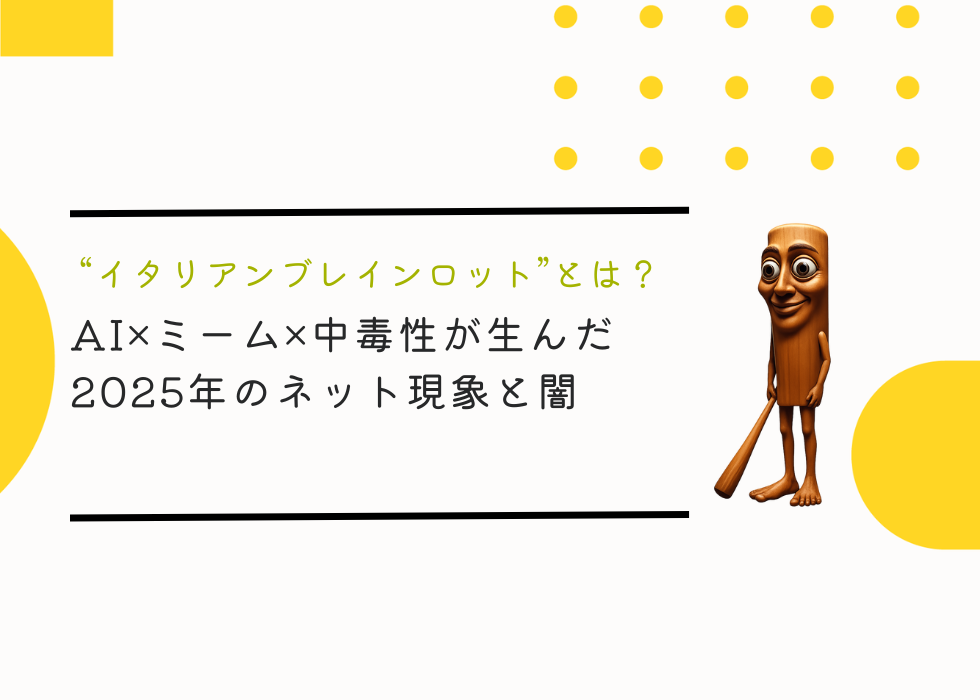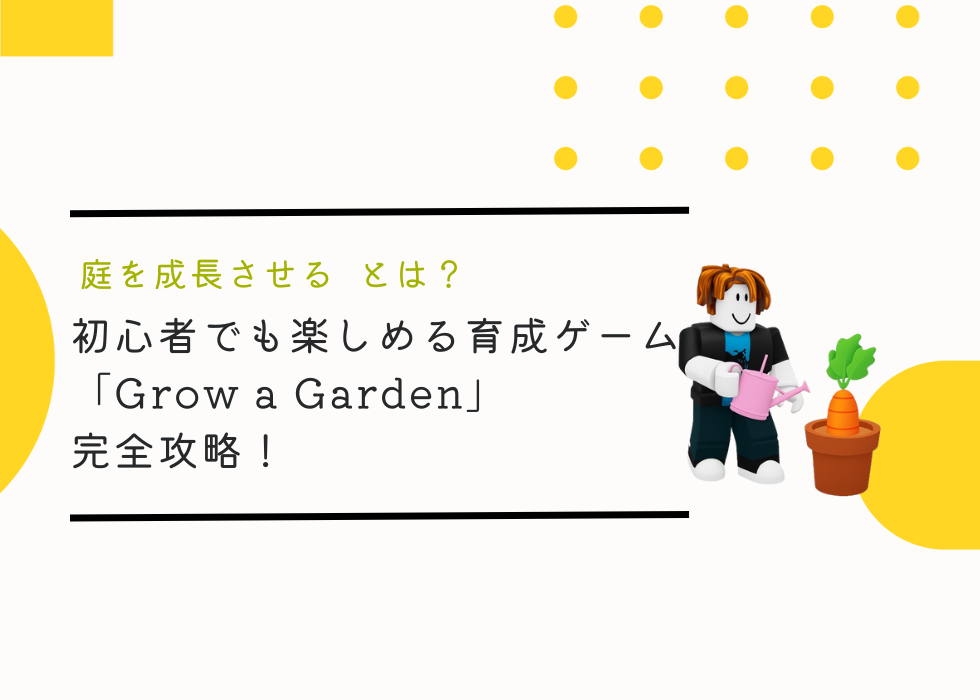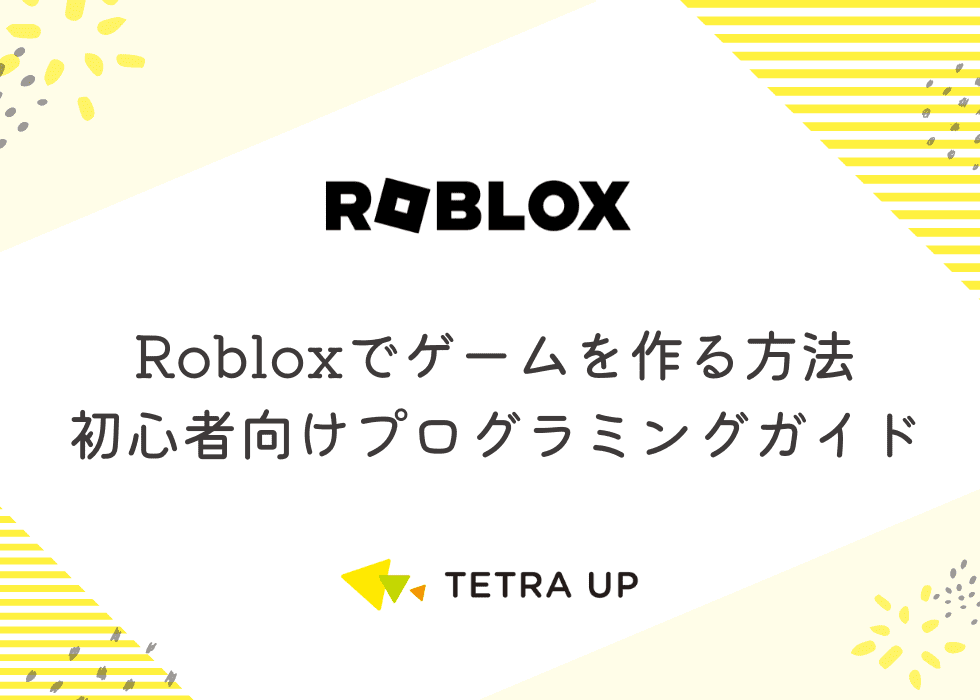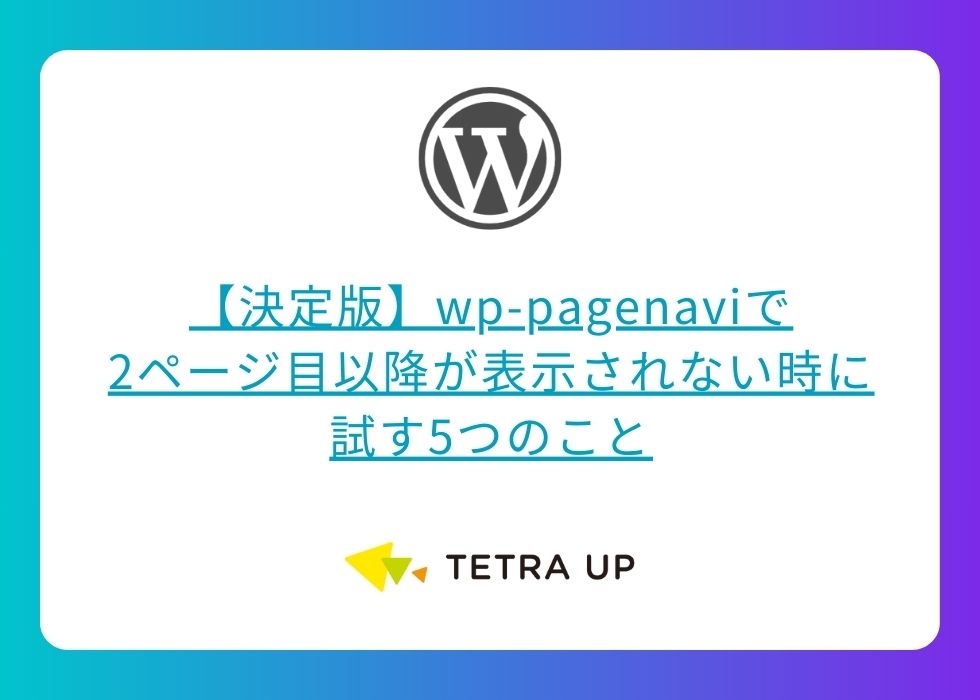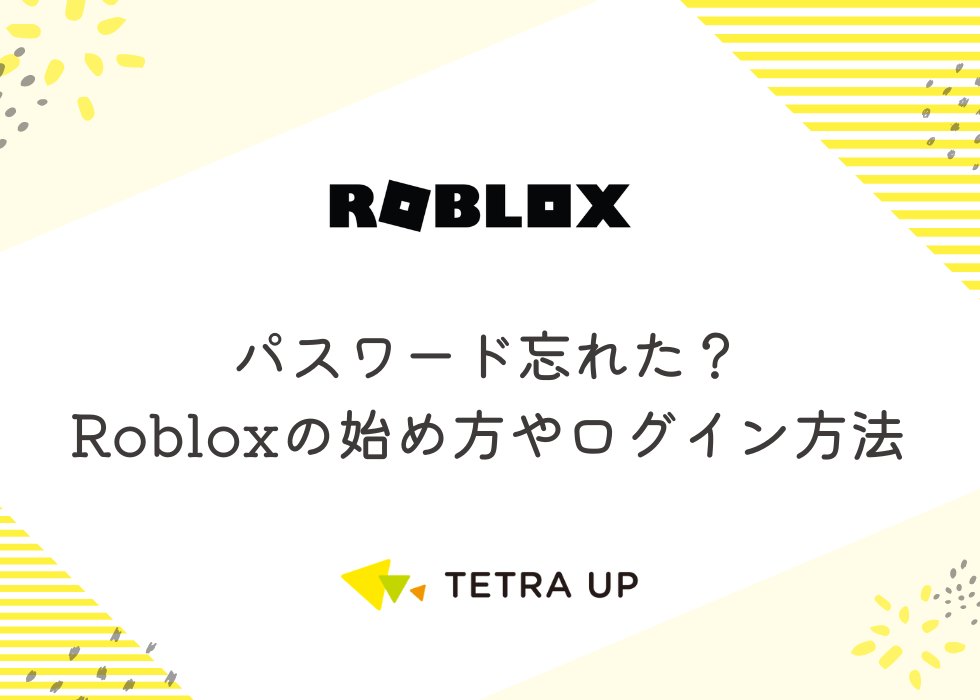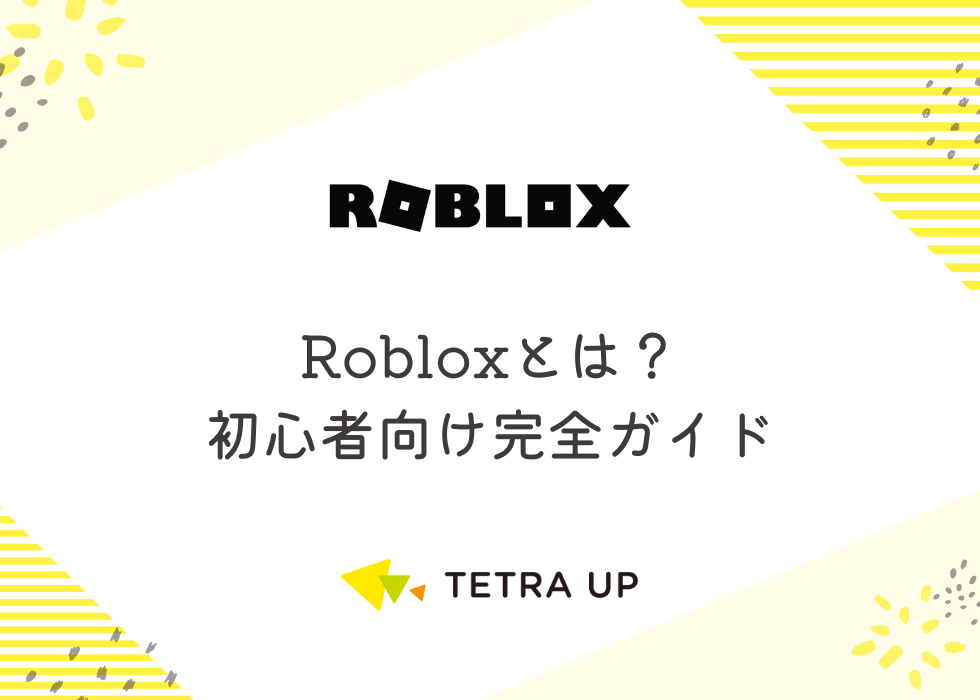-
アマゾンによる実店舗運営「Amazon Go」
コラム詳細を見る▶
-
キュレーションメディアの現状と今後
コラム詳細を見る▶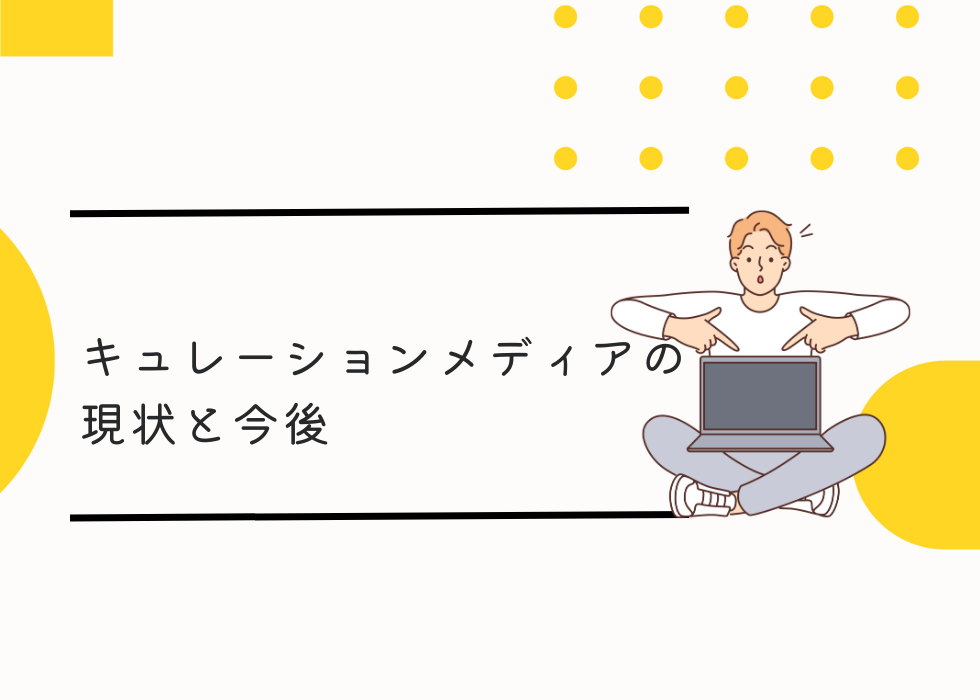
-
医療もIT化
コラム詳細を見る▶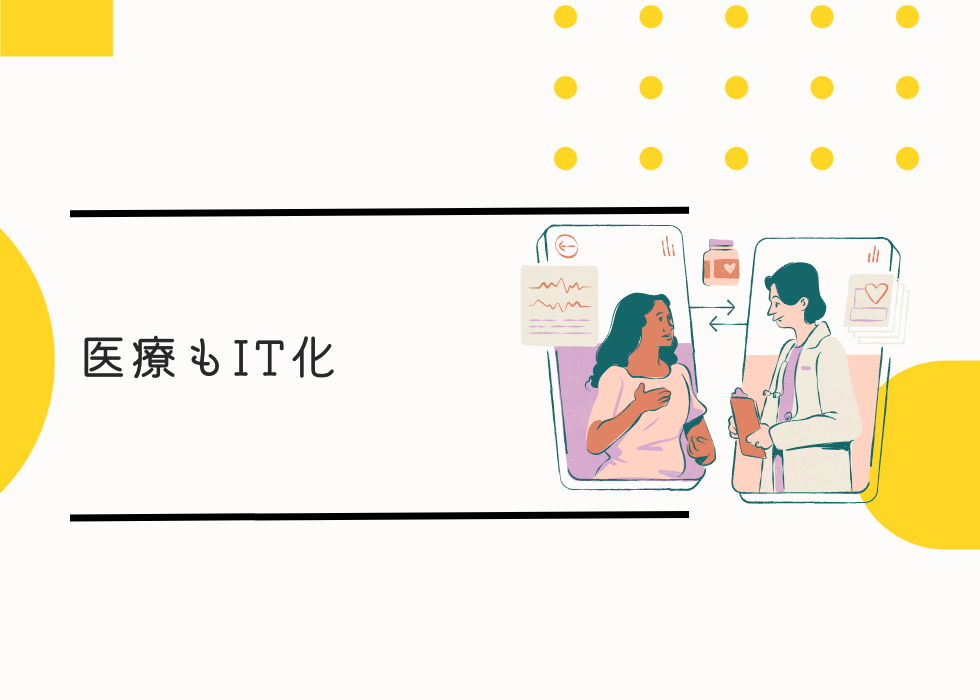
-
Pepperにできること、できないこと
コラム詳細を見る▶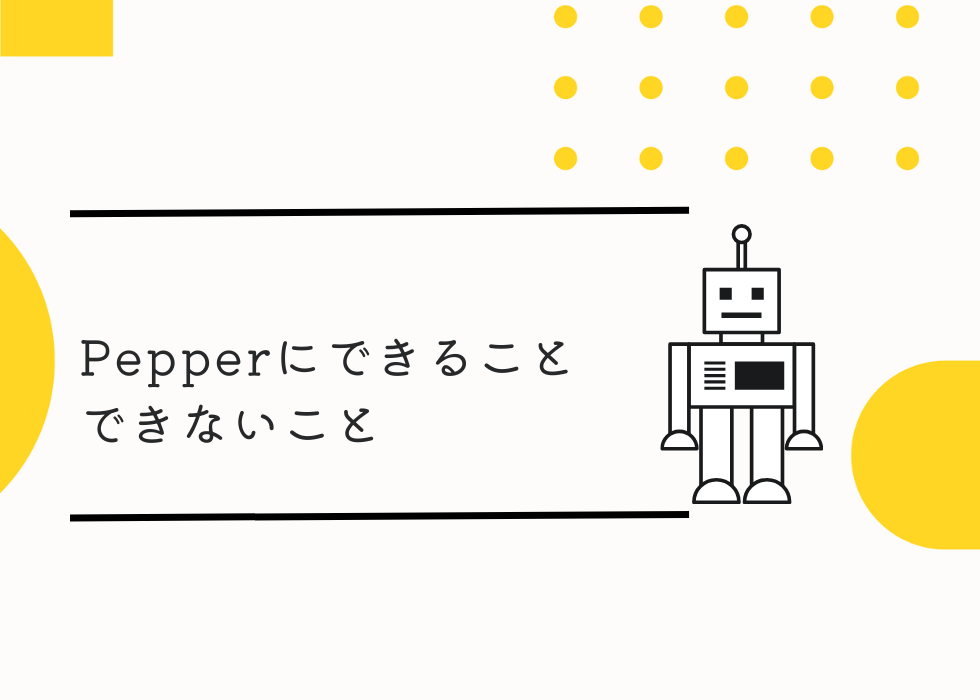
-
幼稚園年代からプログラミング学ぶ必要ってあるの?
コラム詳細を見る▶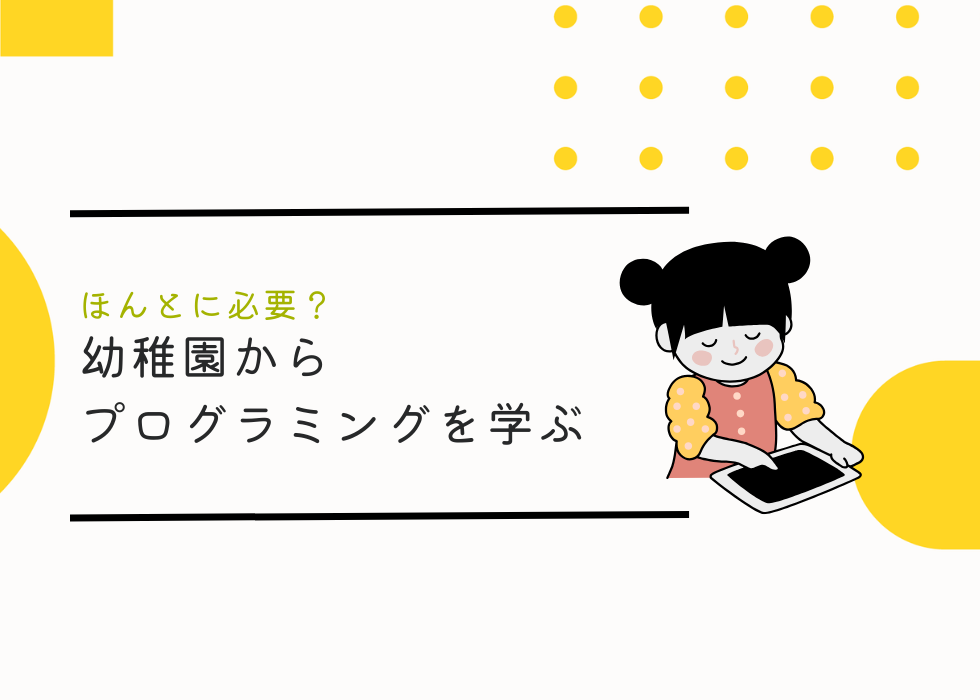
-
プログラマーから見たあやふやな世界
コラム詳細を見る▶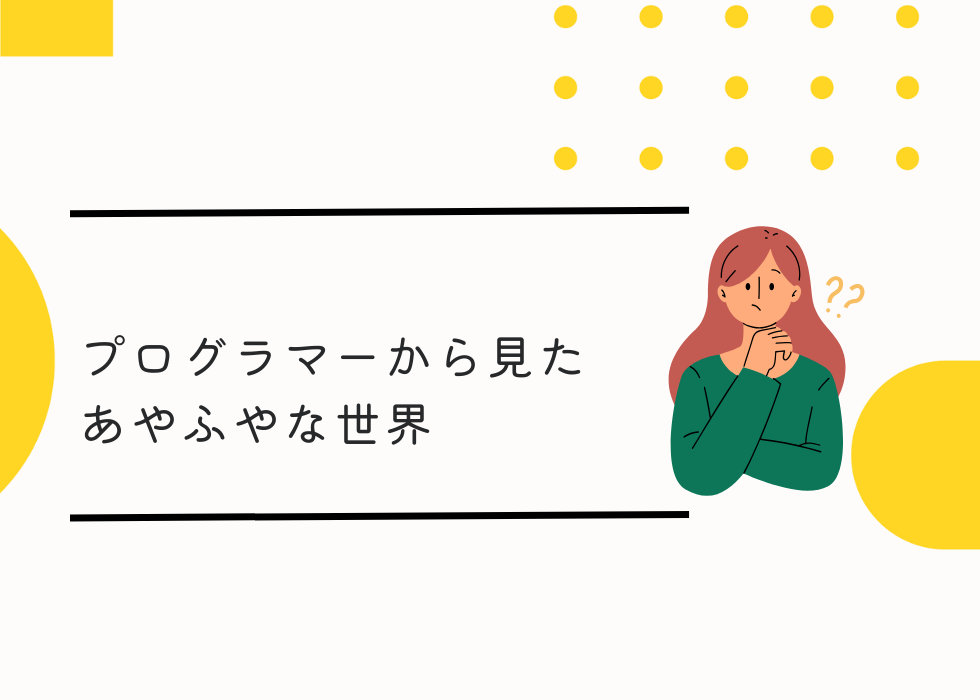
-
機械だって言語を持っているのだ!
コラム詳細を見る▶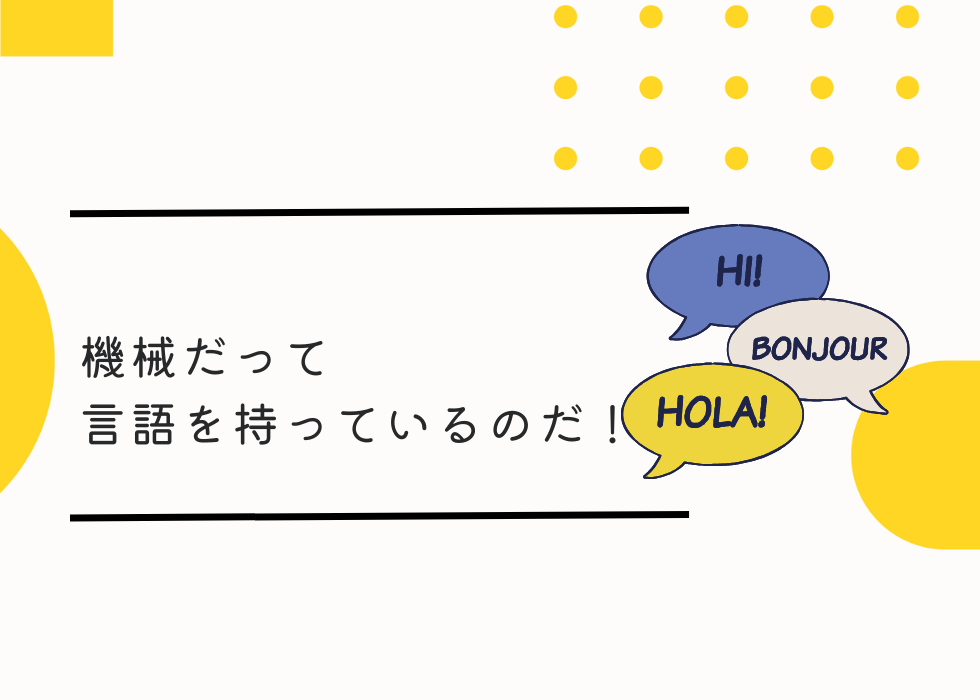
-
ロボットは人間の友達となり得るのか
コラム詳細を見る▶