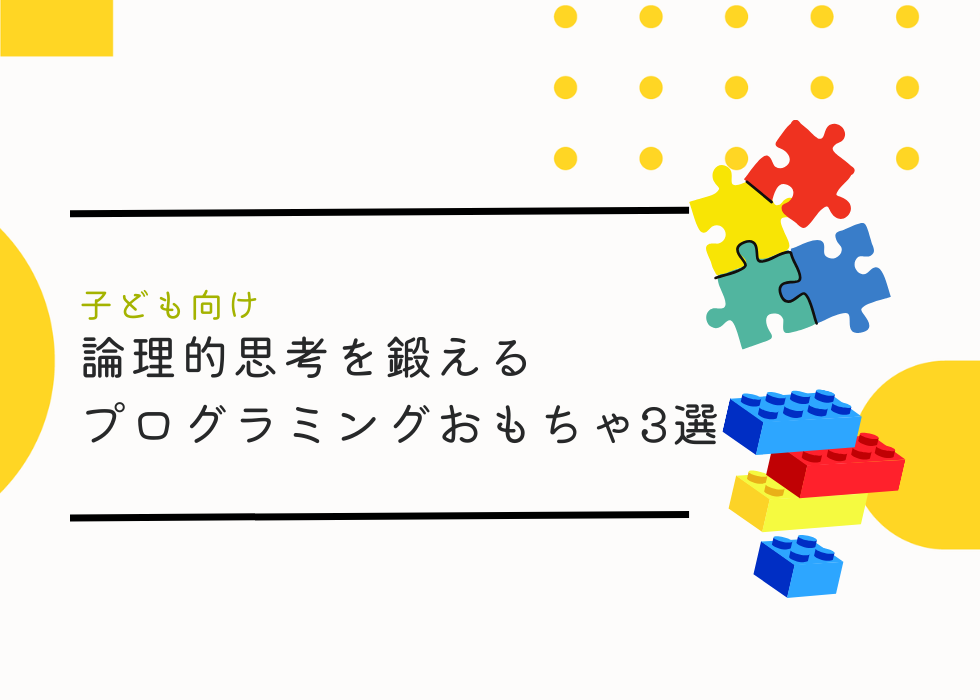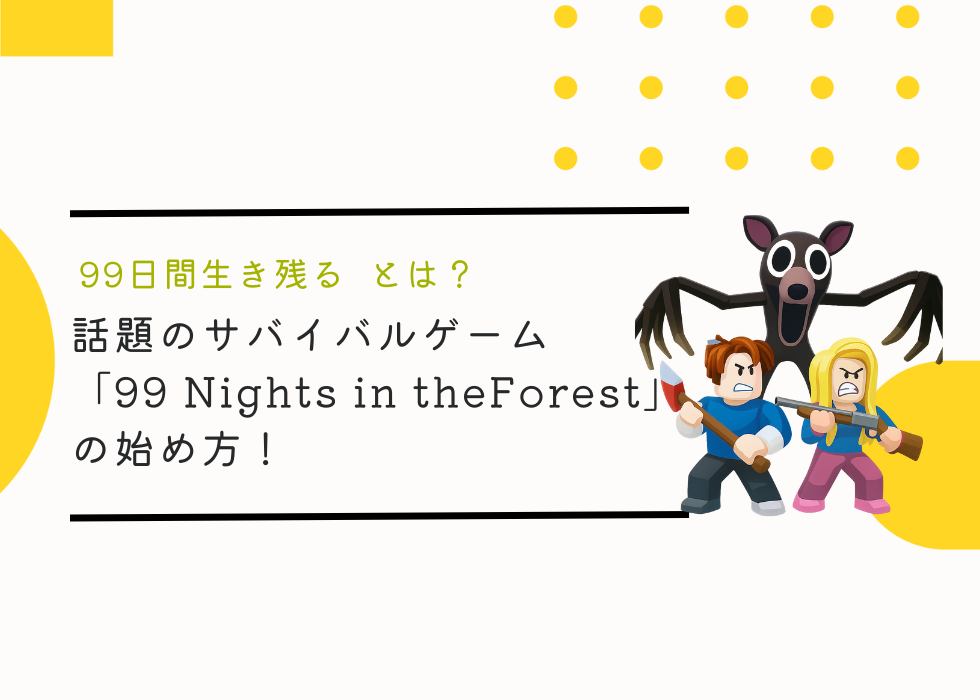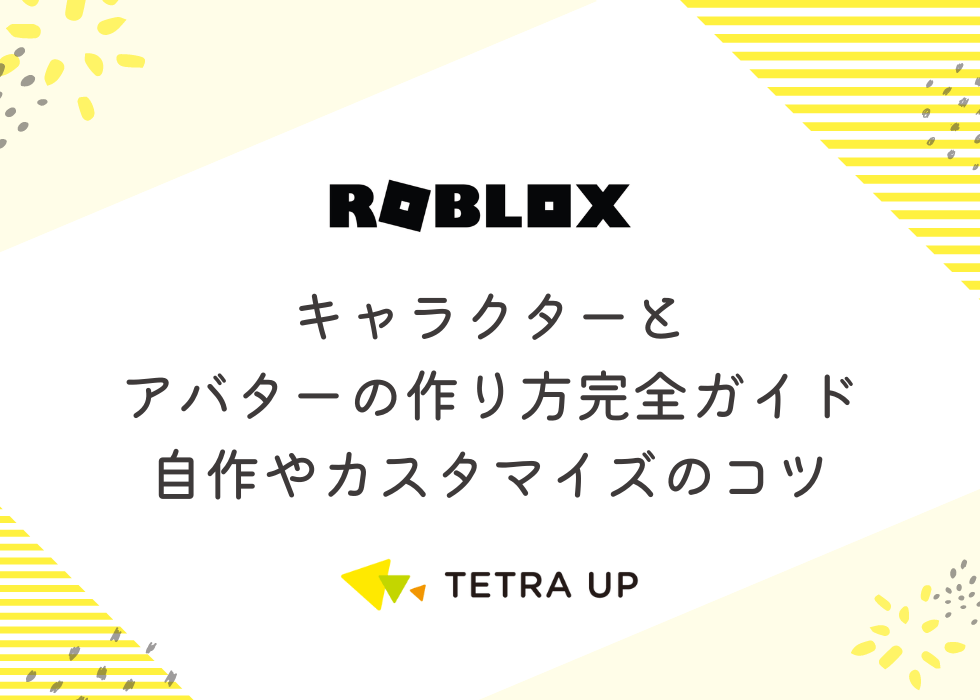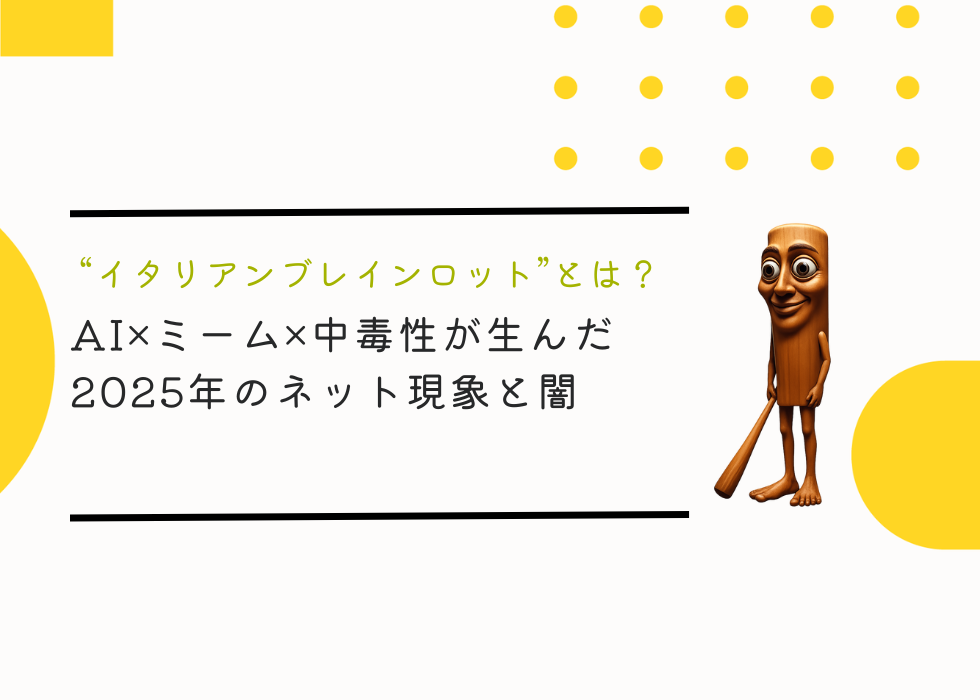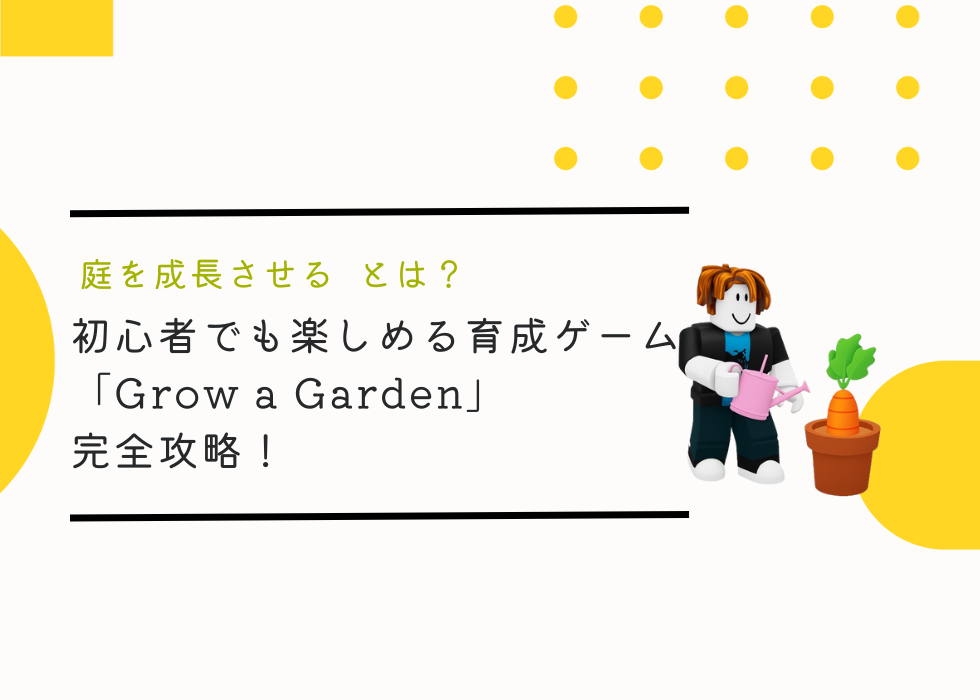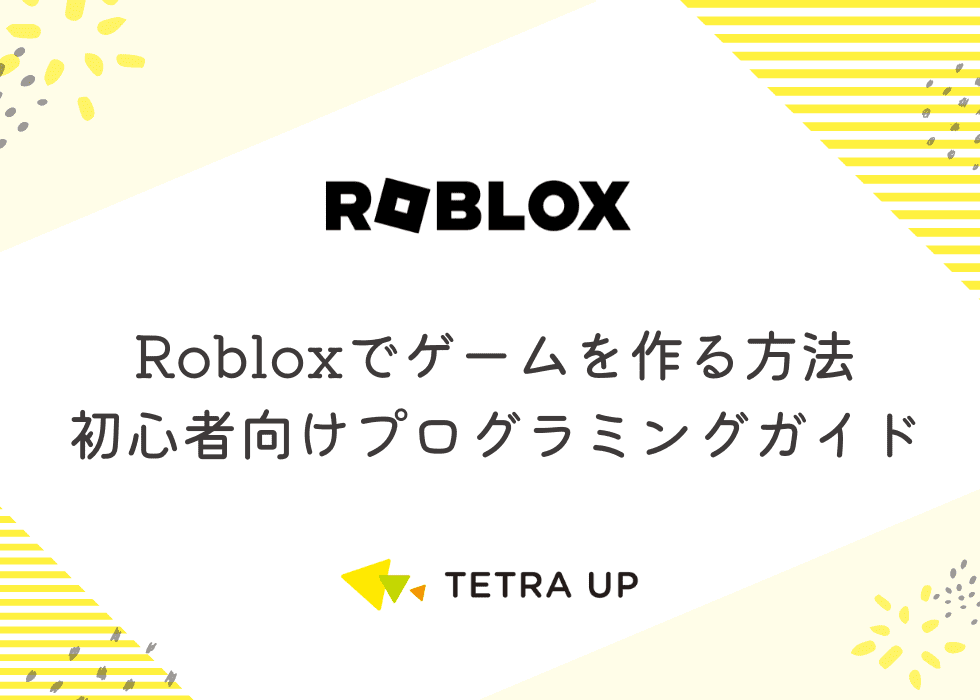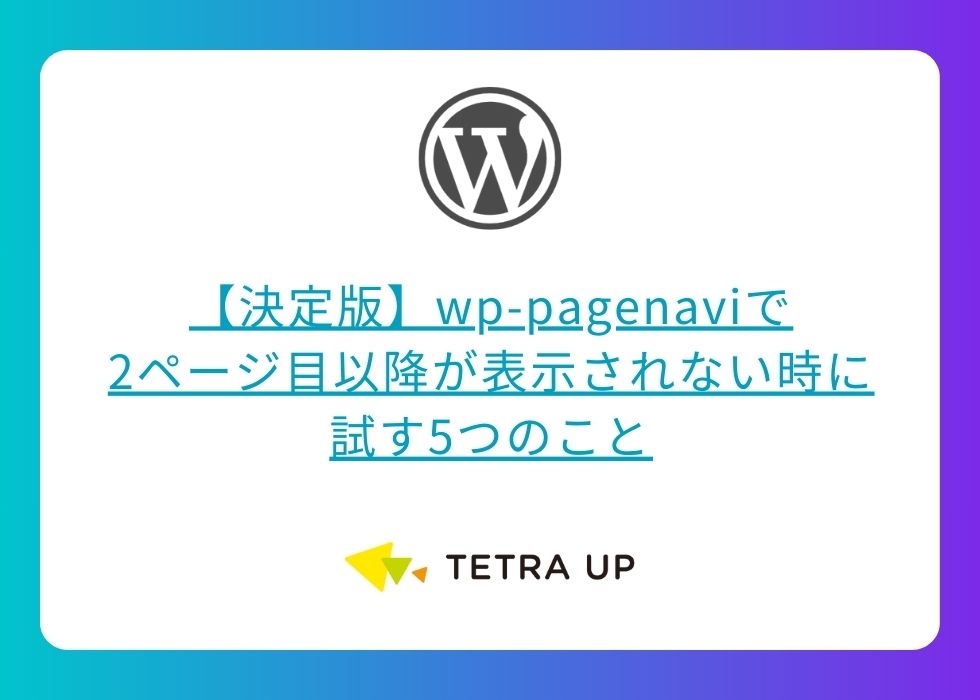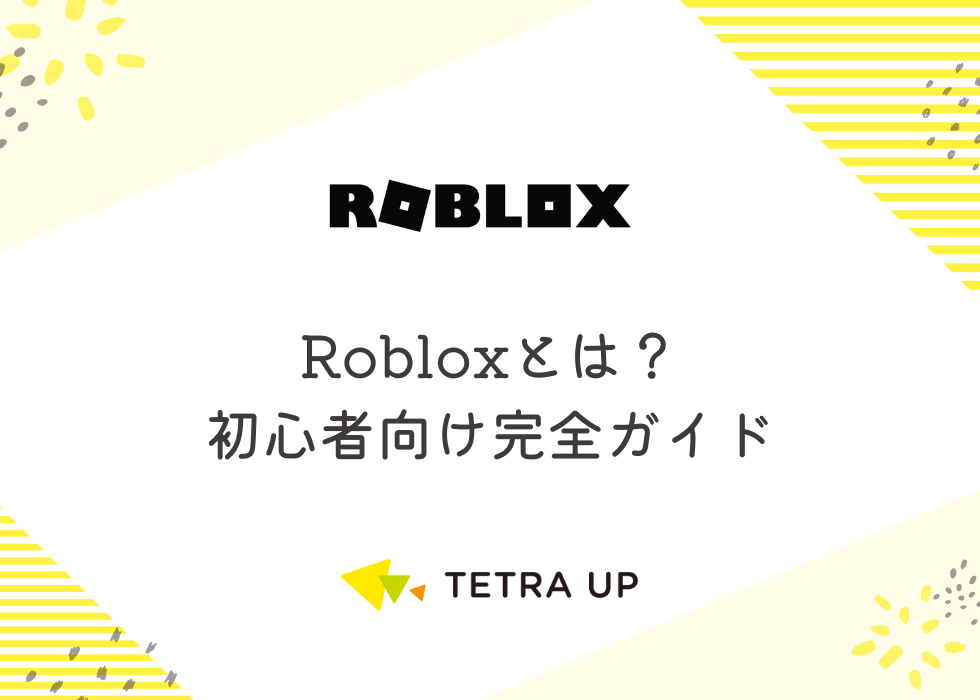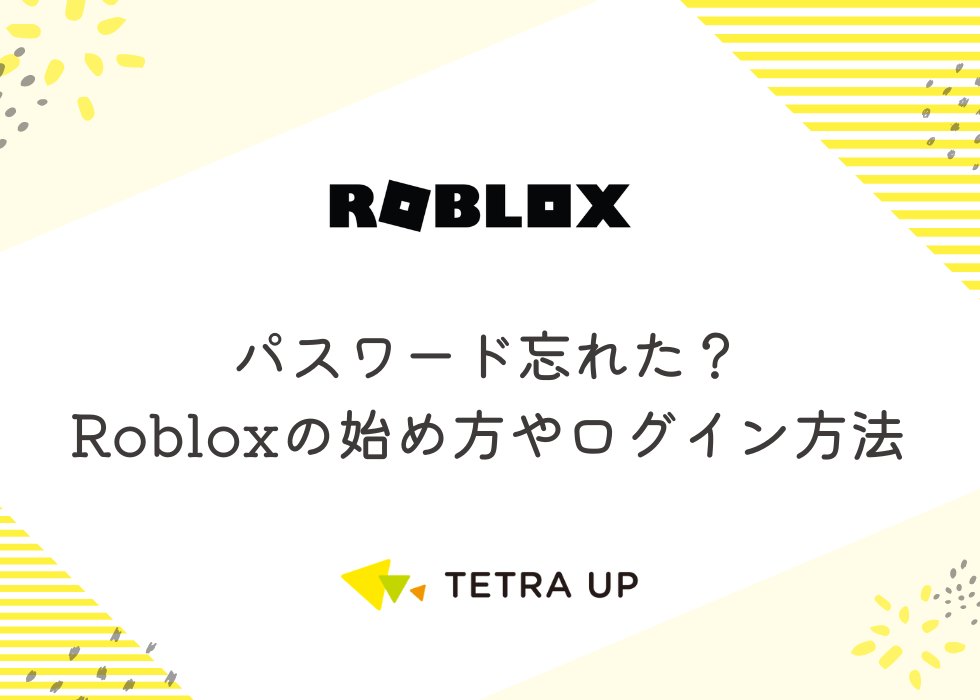-
子どもがプログラミングに興味を持たない理由と楽しく学ばせるコツ
コラム詳細を見る▶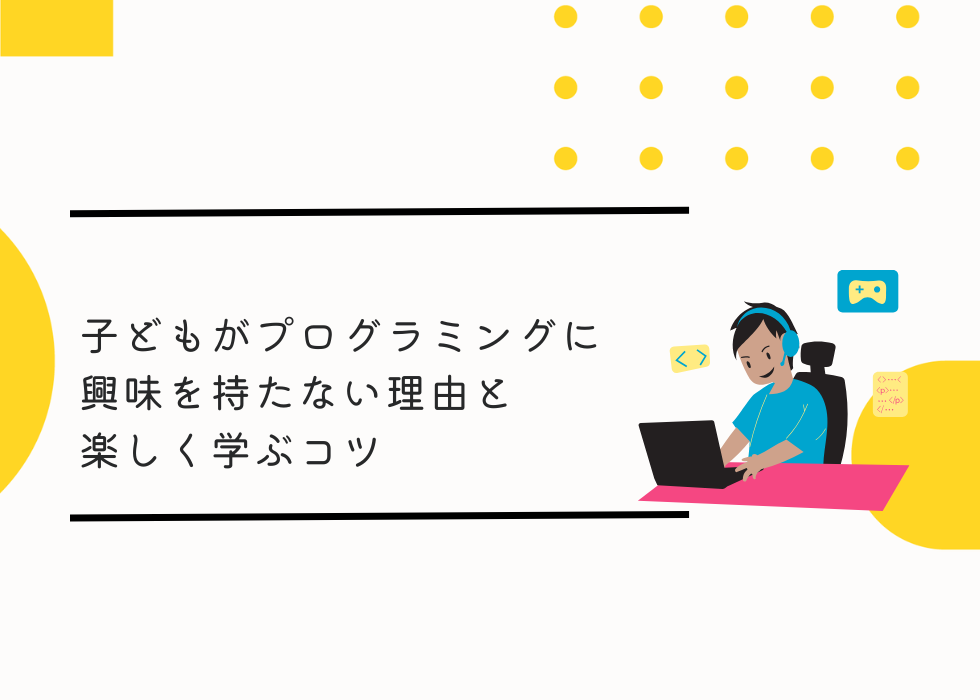
-
TETRA UPが世界へ提供する、海外駐在ファミリーの子ども向けプログラミングレッスンの3つの魅力
コラム詳細を見る▶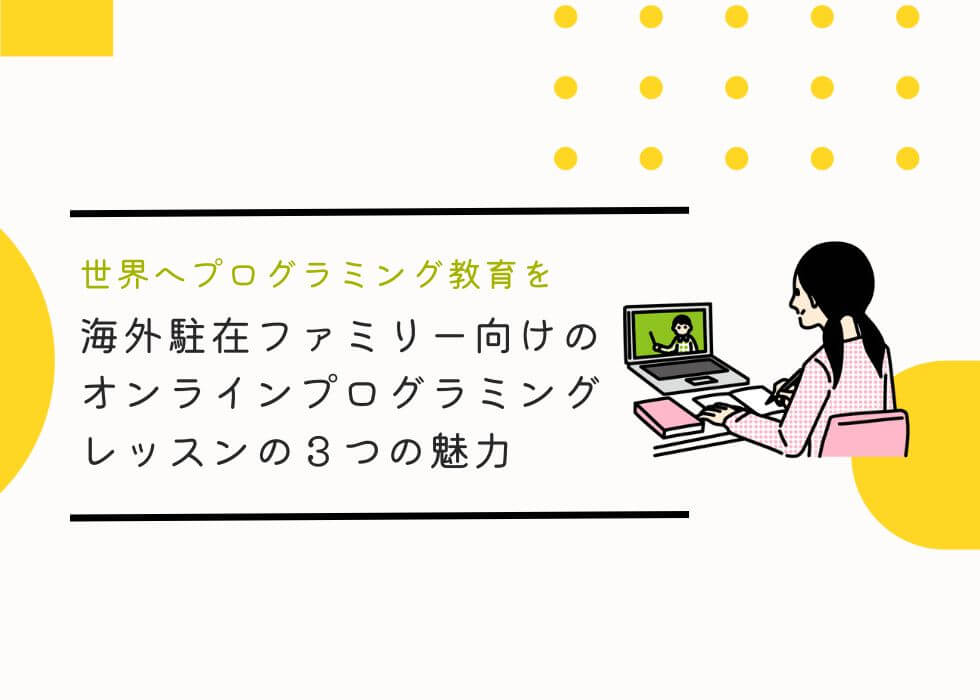
-
子どもの未来を育てる!少人数制で学ぶScratch、Unity、ロボットのプログラミング教室の魅力
コラム詳細を見る▶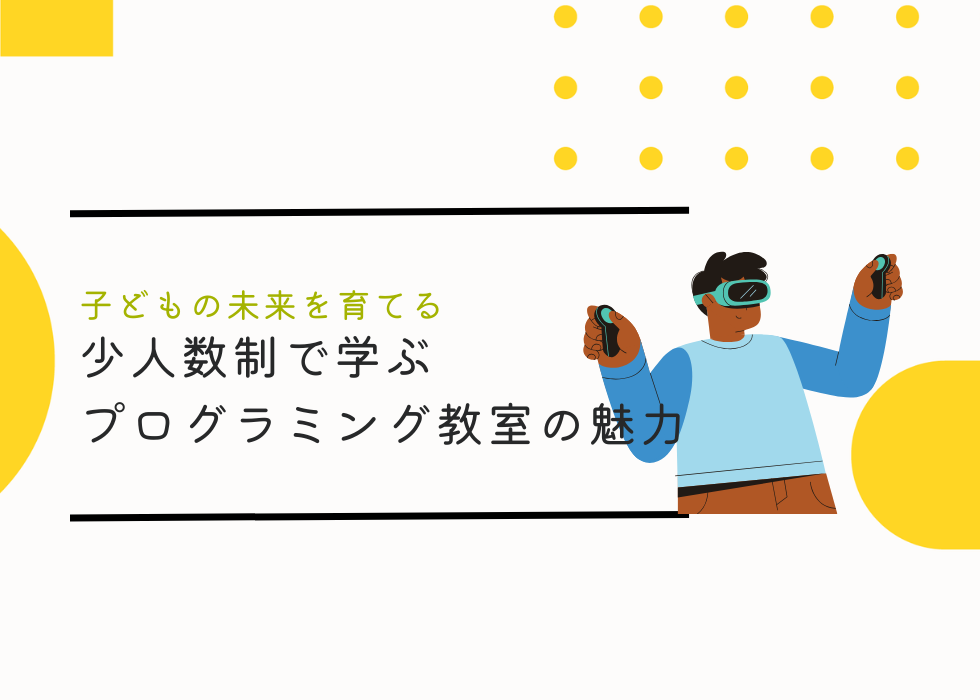
-
プログラミングが子供の問題解決能力と創造性に与える影響
コラム詳細を見る▶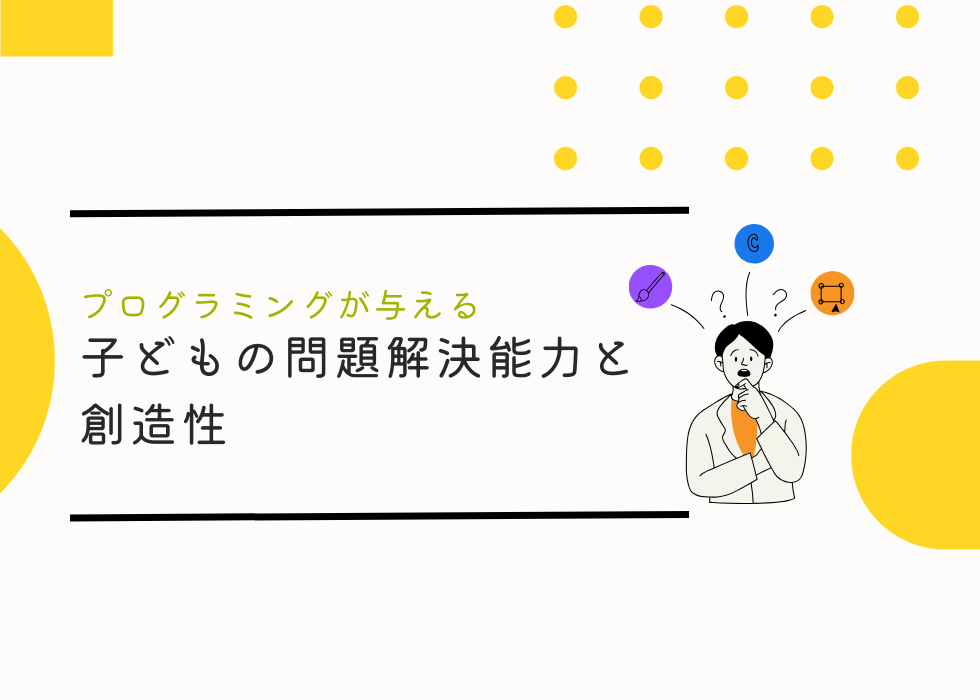
-
プログラミングで社会貢献!テクノロジーの力で世界を変える方法
コラム詳細を見る▶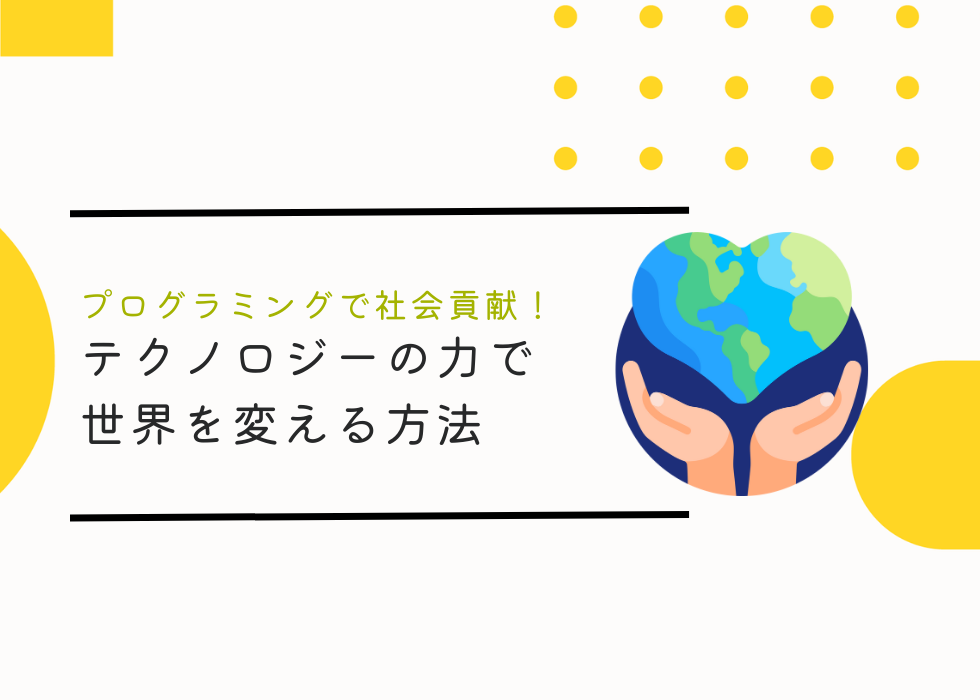
-
プログラミングと創造性の融合!アートと技術を結ぶプログラミング活用術
コラム詳細を見る▶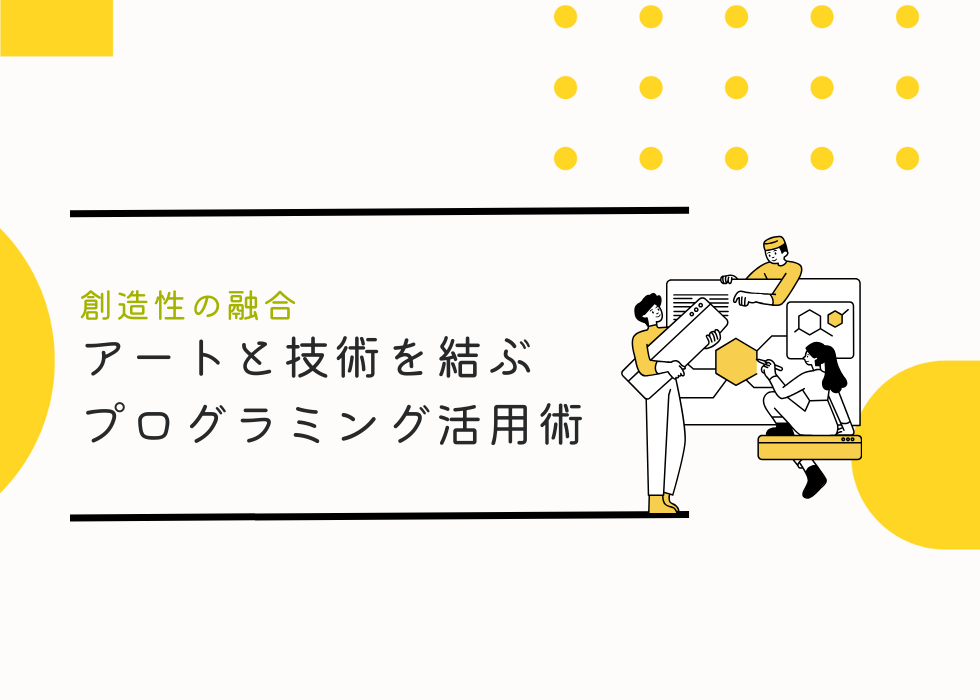
-
小学生がロボットプログラミングを学ぶメリットとは?
コラム詳細を見る▶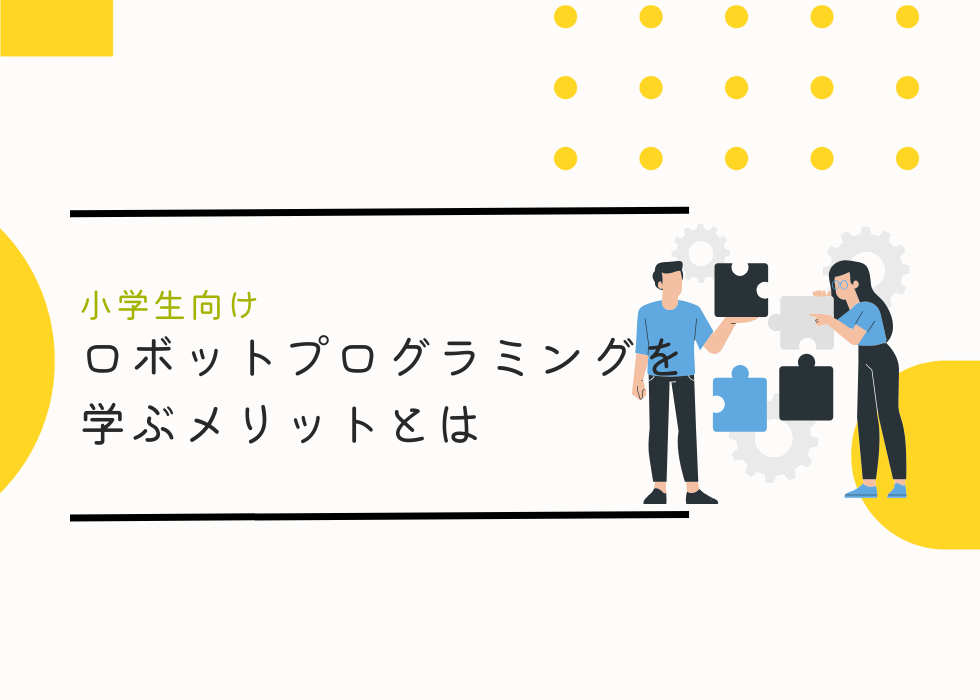
-
小学生向けプログラミング教材の選び方とおすすめ
コラム詳細を見る▶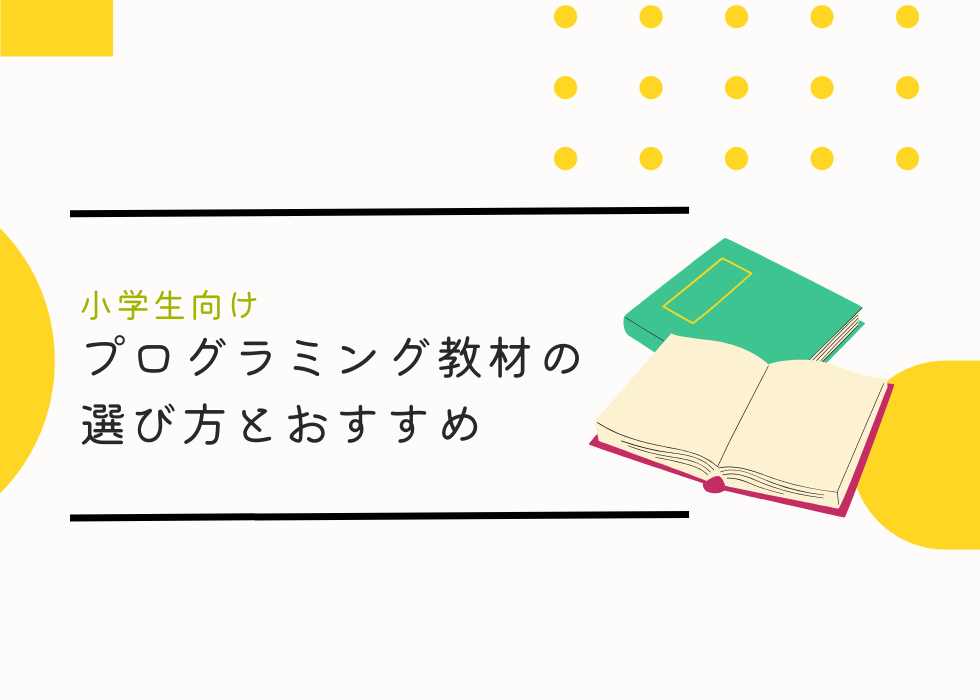
-
今問われるプログラミングの力
コラム詳細を見る▶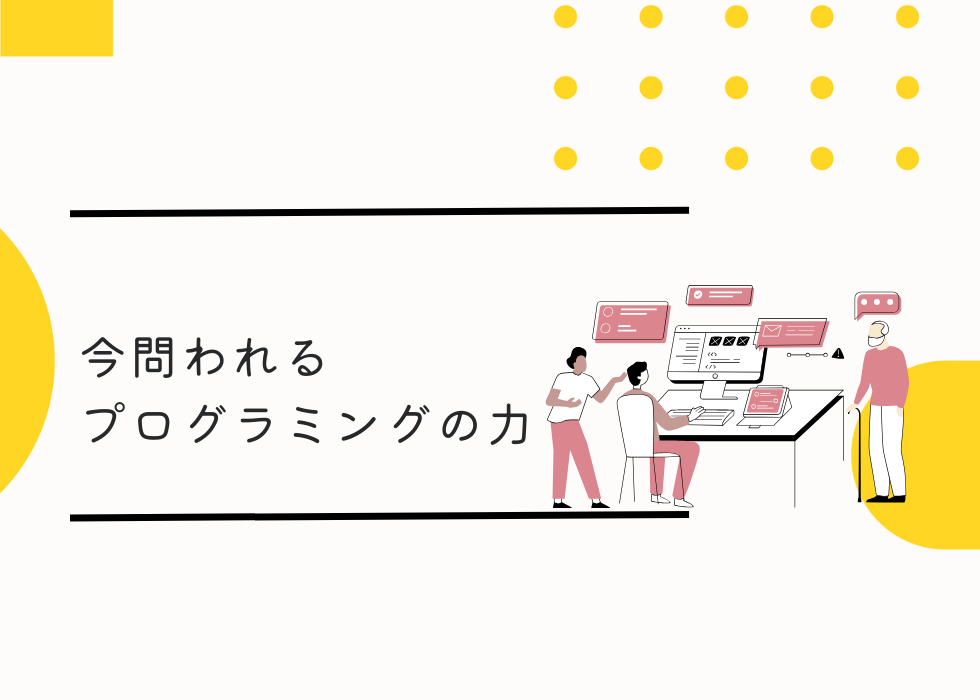
-
【子供向け】論理的思考を鍛えるプログラミングおもちゃ3選
コラム詳細を見る▶