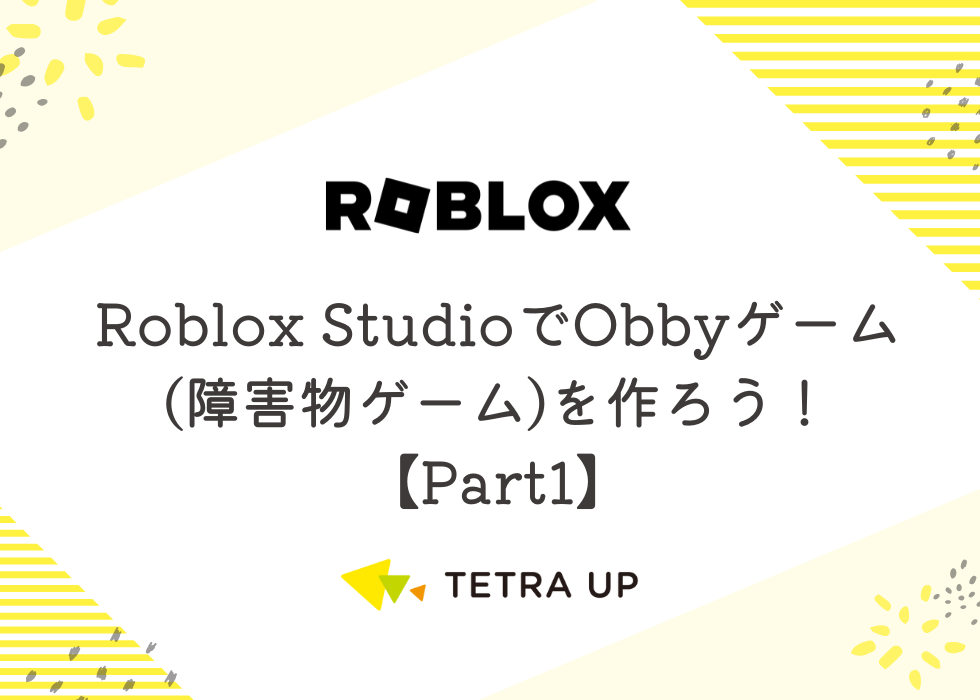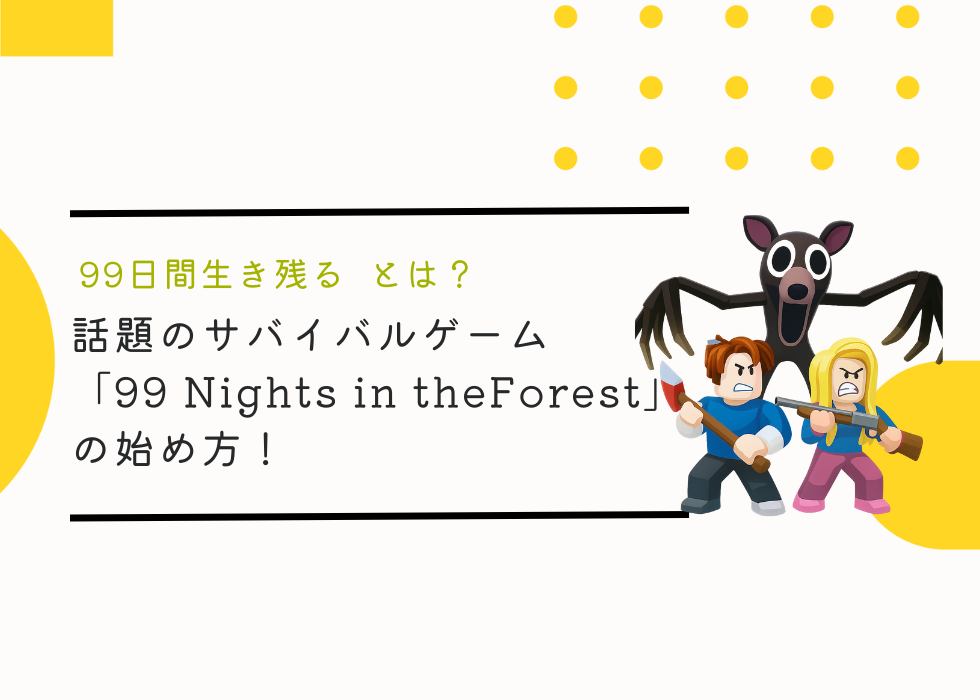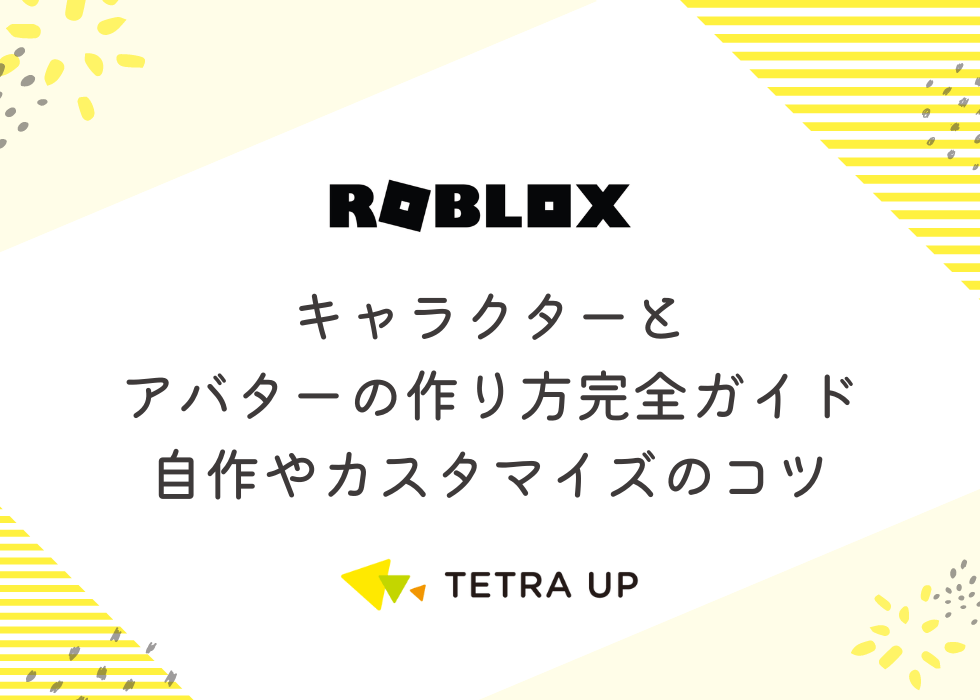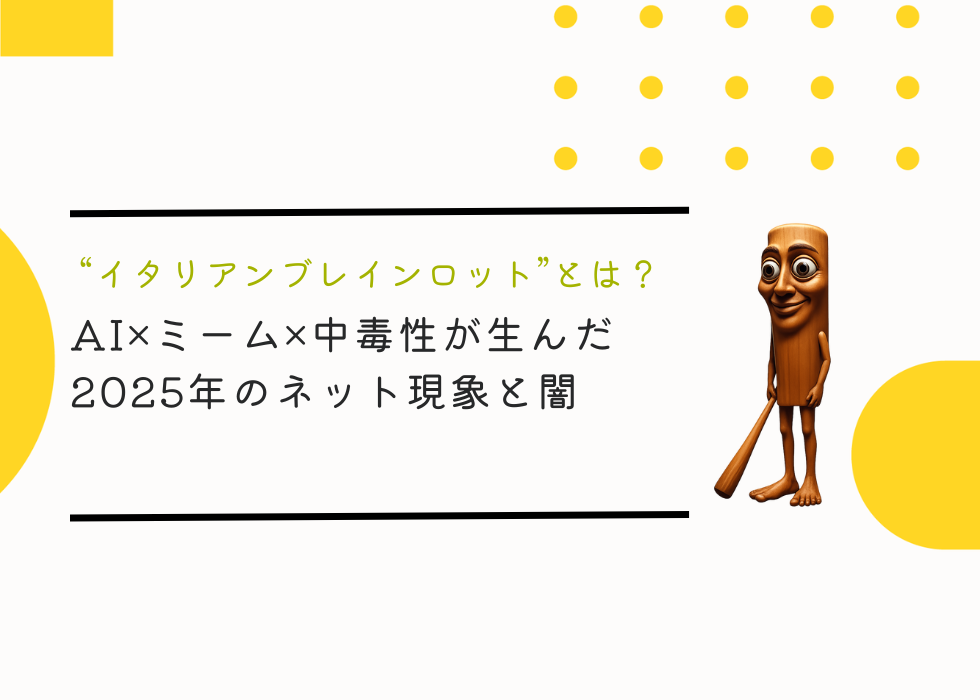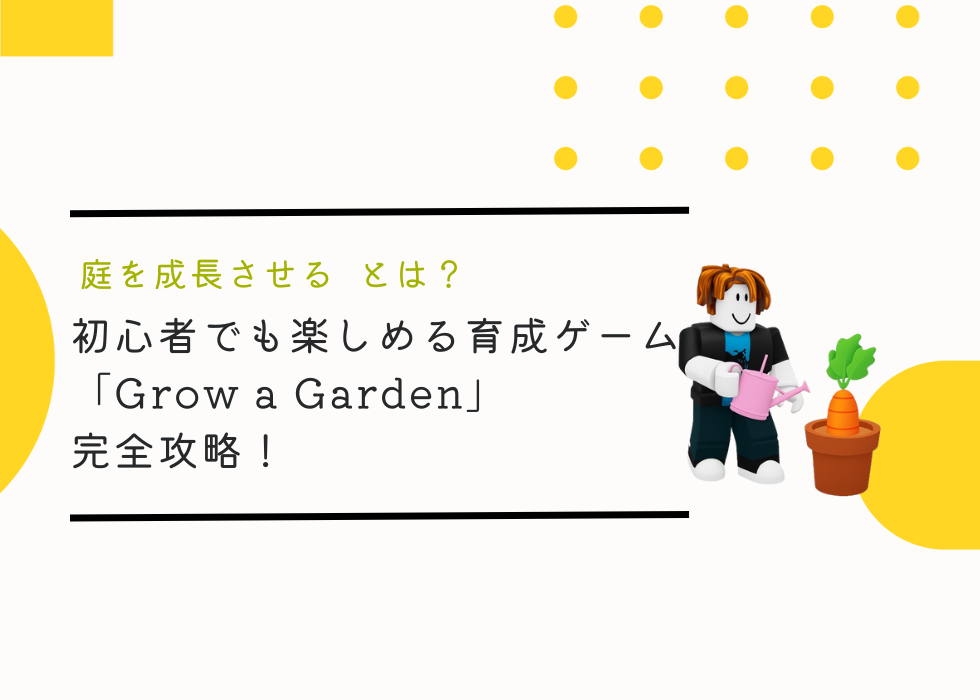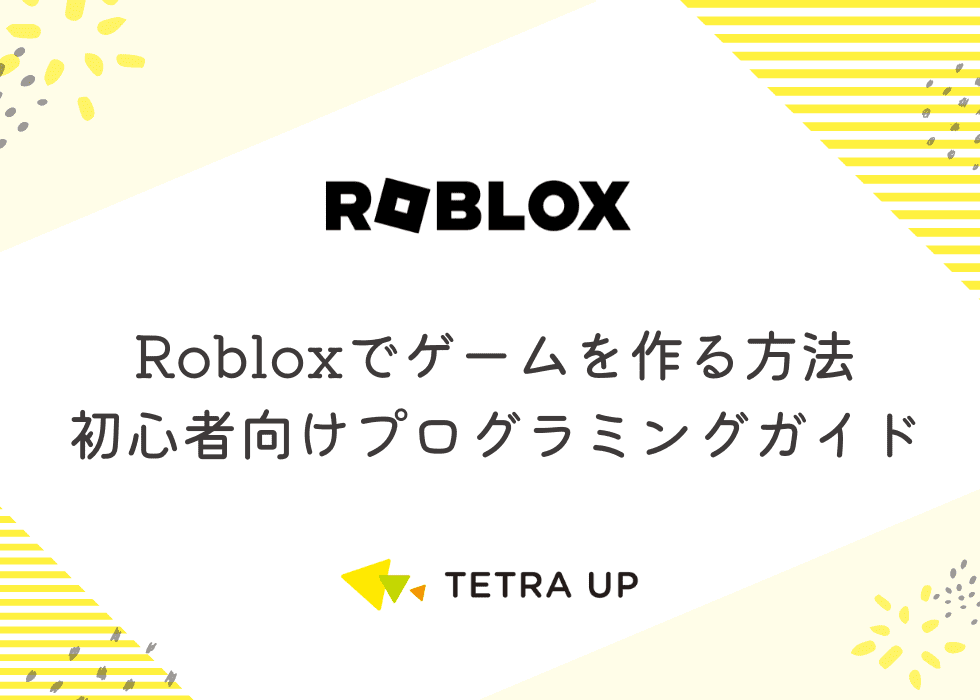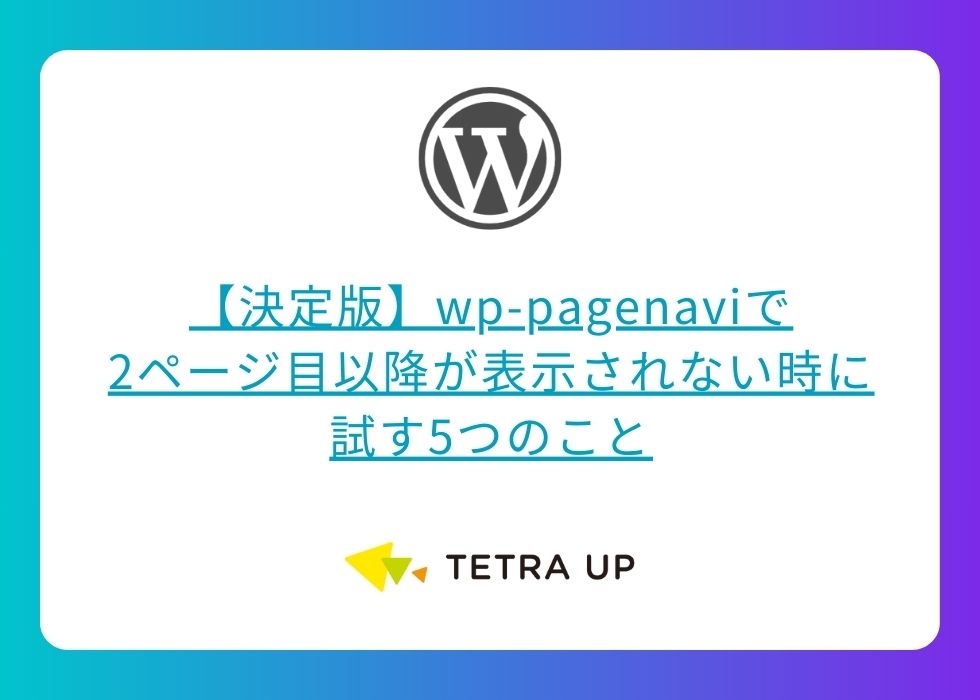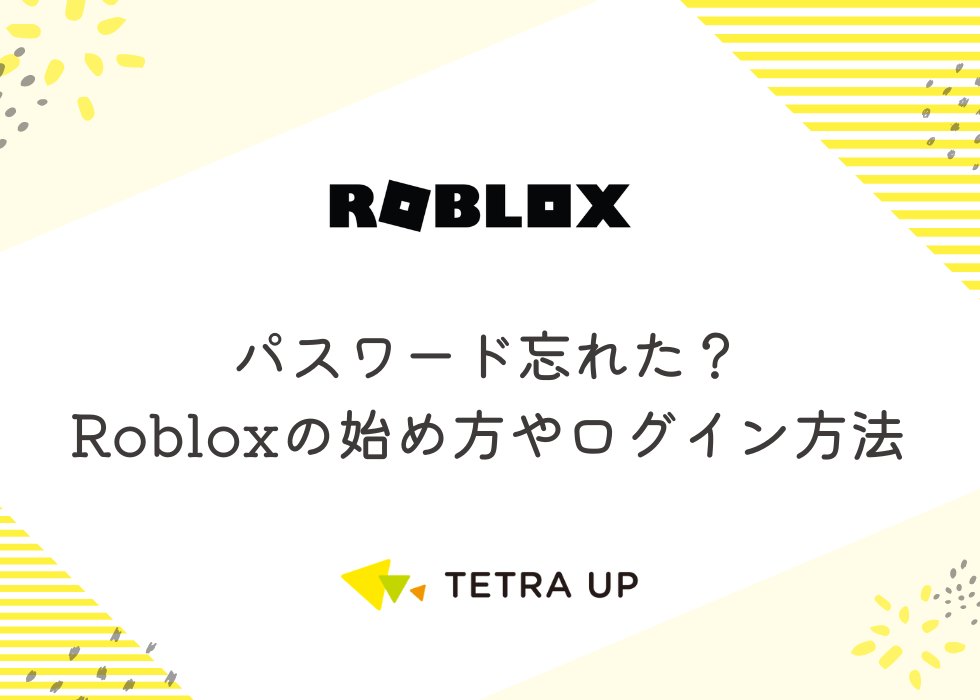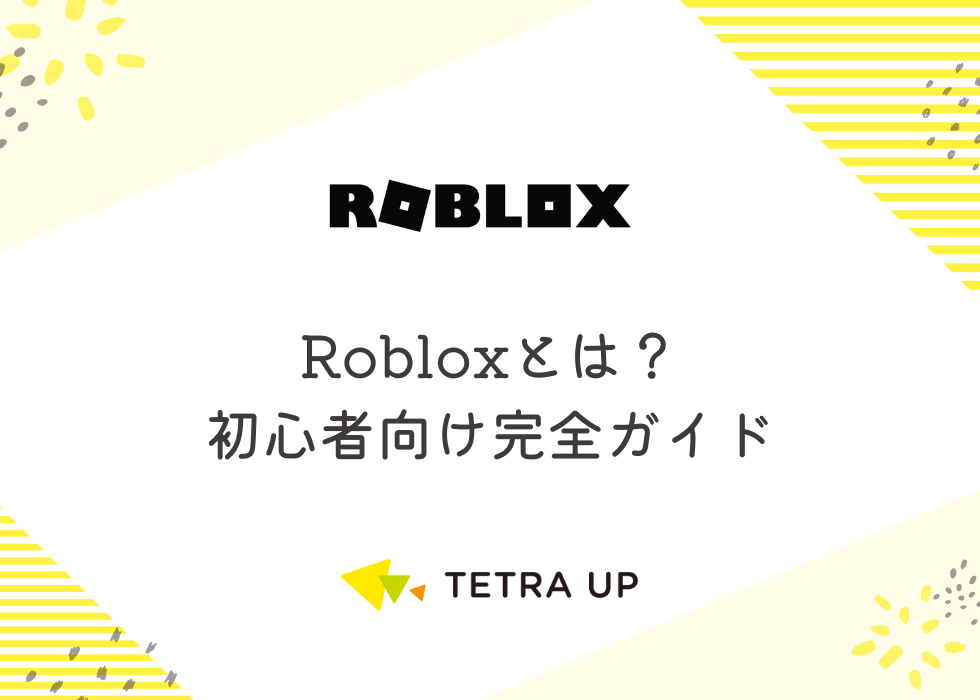-
プログラミング教育新聞 2025年12月号|TETRA UP
お知らせ詳細を見る▶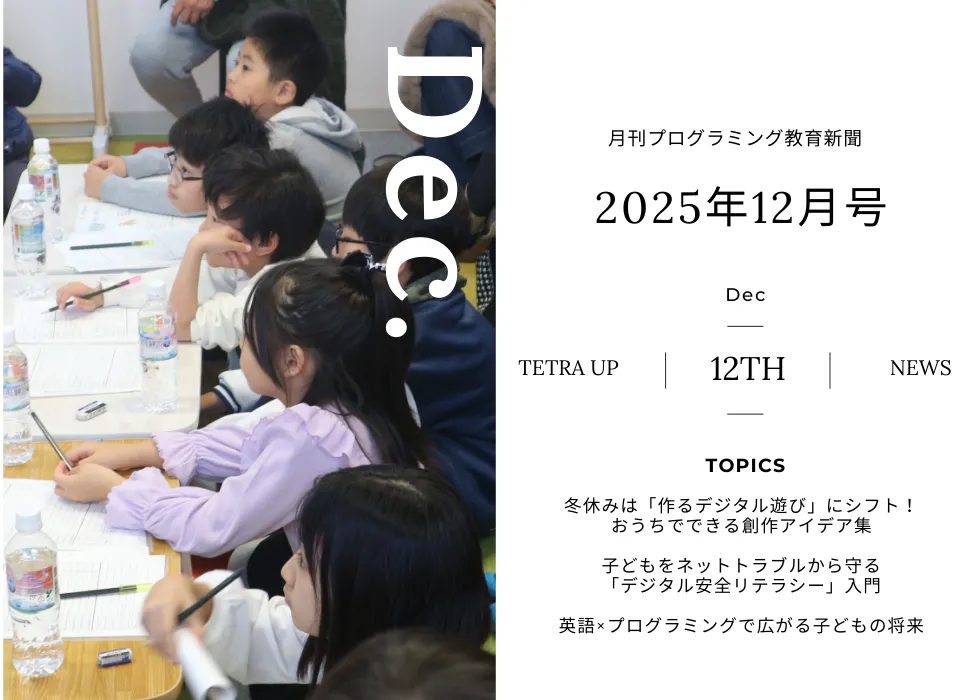
-
Unityで「2Dオブジェクトが作れない」ときの対処法
コラム詳細を見る▶
-
Unity 6.2正式リリース!Unity AI Betaが開く新たなゲーム開発の可能性
コラム詳細を見る▶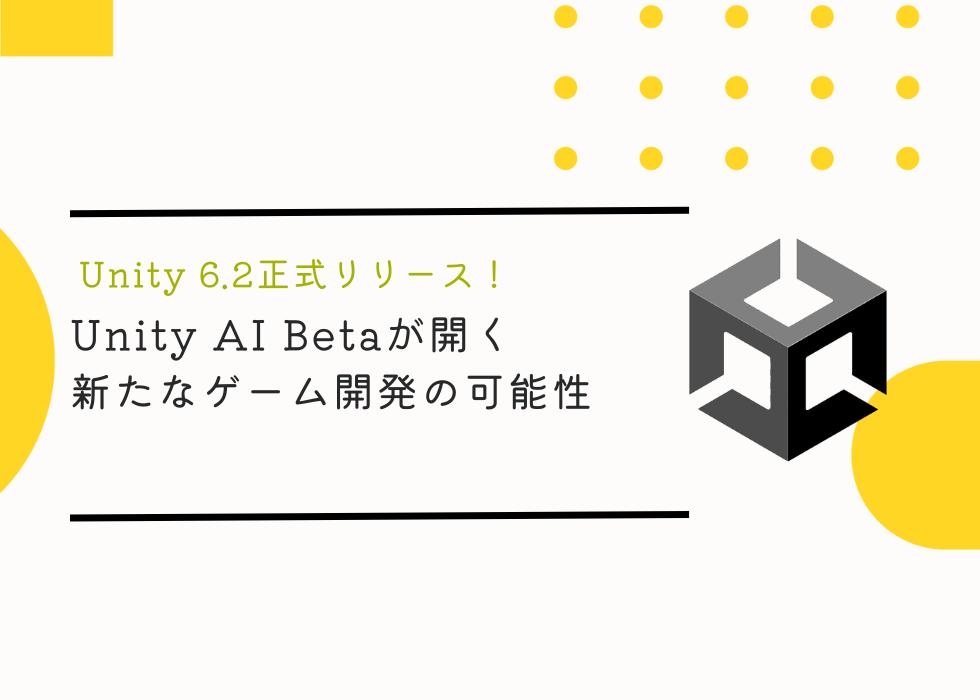
-
プログラミング教育新聞 2025年9月号|TETRA UP
お知らせ詳細を見る▶
-
「褒める教育」の落とし穴──”幅”と”自分軸”を育てる視点
コラム詳細を見る▶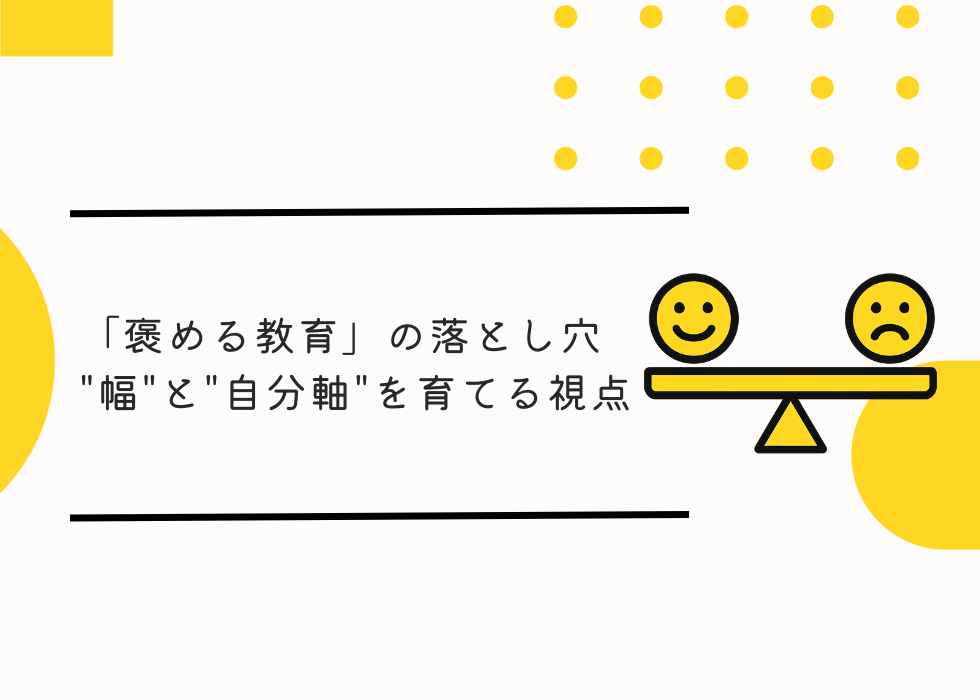
-
【早割でお得!】2025年夏の1DAYプログラミング自由研究イベント 予約開始!
お知らせ詳細を見る▶
-
プログラミング教育新聞 2025年6月号|TETRA UP
お知らせ詳細を見る▶
-
わが子に合うのはどれ?小学生向けプログラミング資格徹底比較ガイド
コラム詳細を見る▶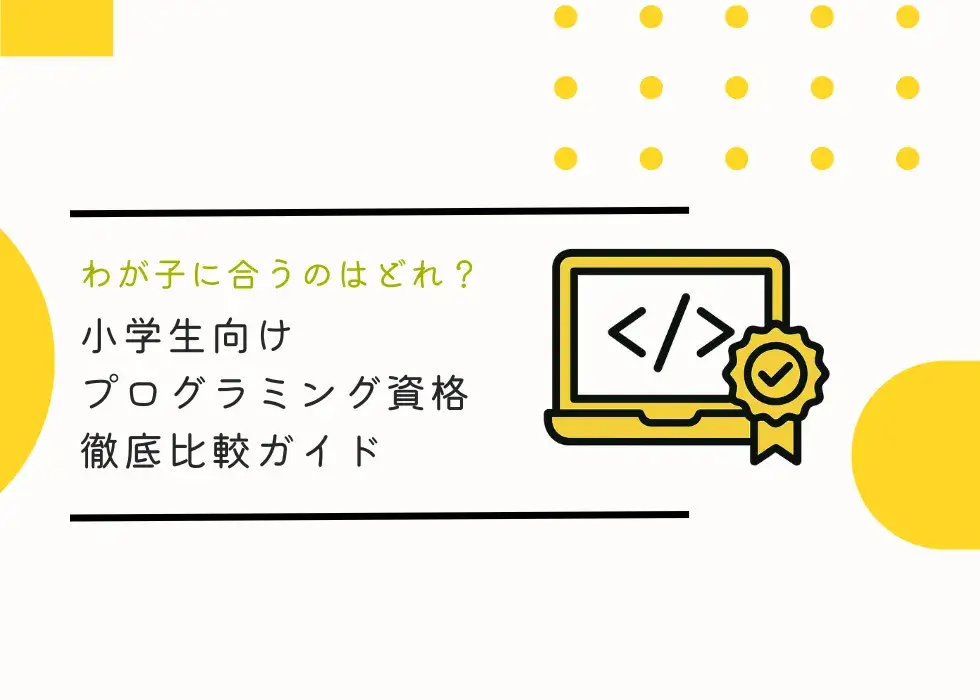
-
ゲーム×学びの新常識!Minecraft教育版の効果とは
コラム詳細を見る▶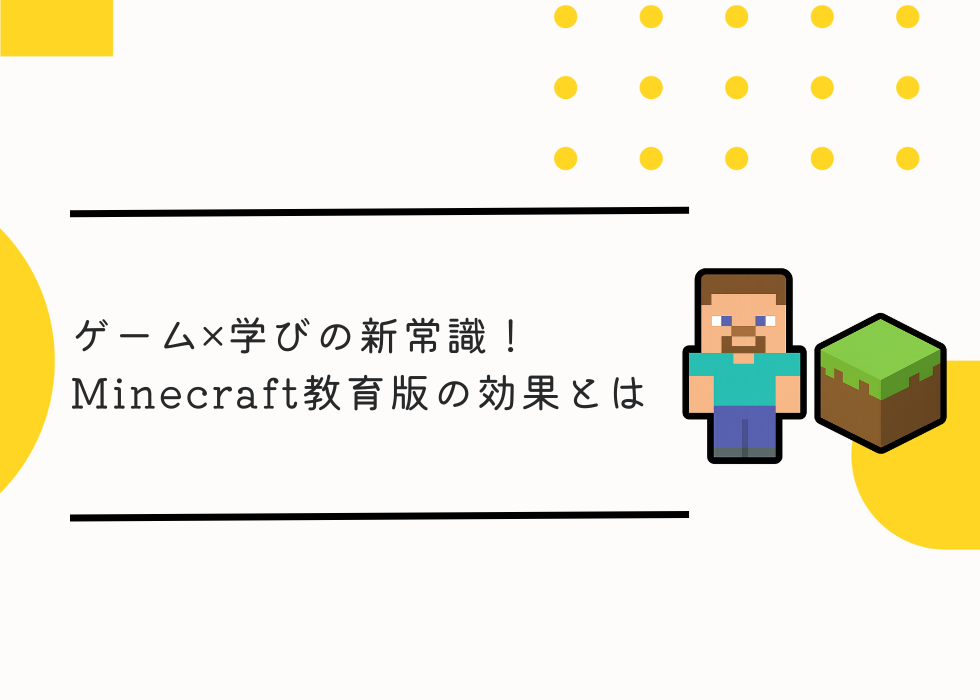
-
【簡単】Roblox StudioでObbyゲーム(障害物ゲーム)を作ろう!【Part1】
コラム詳細を見る▶