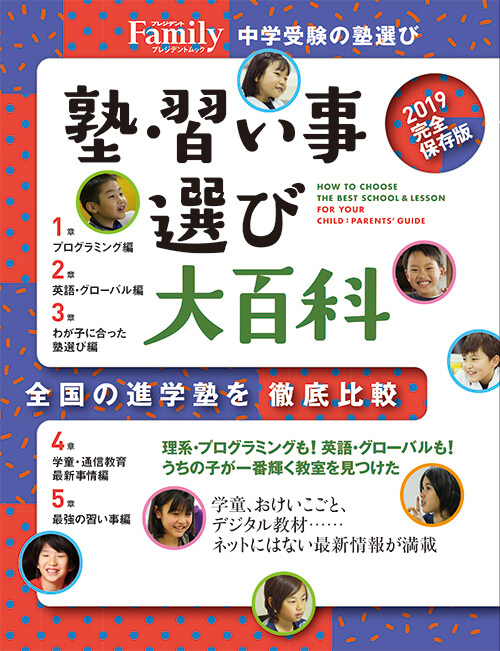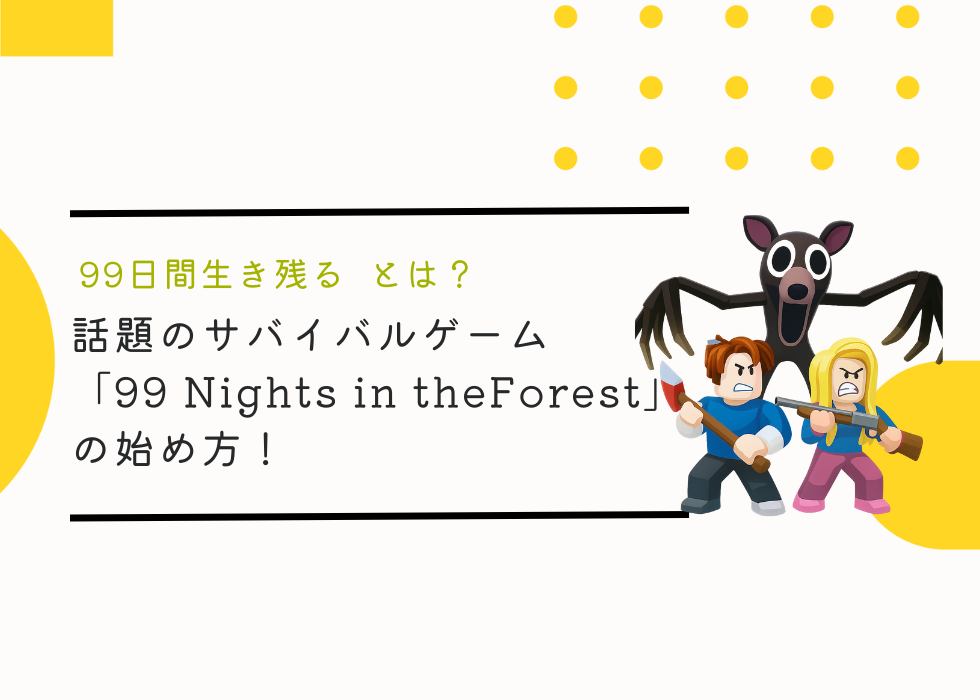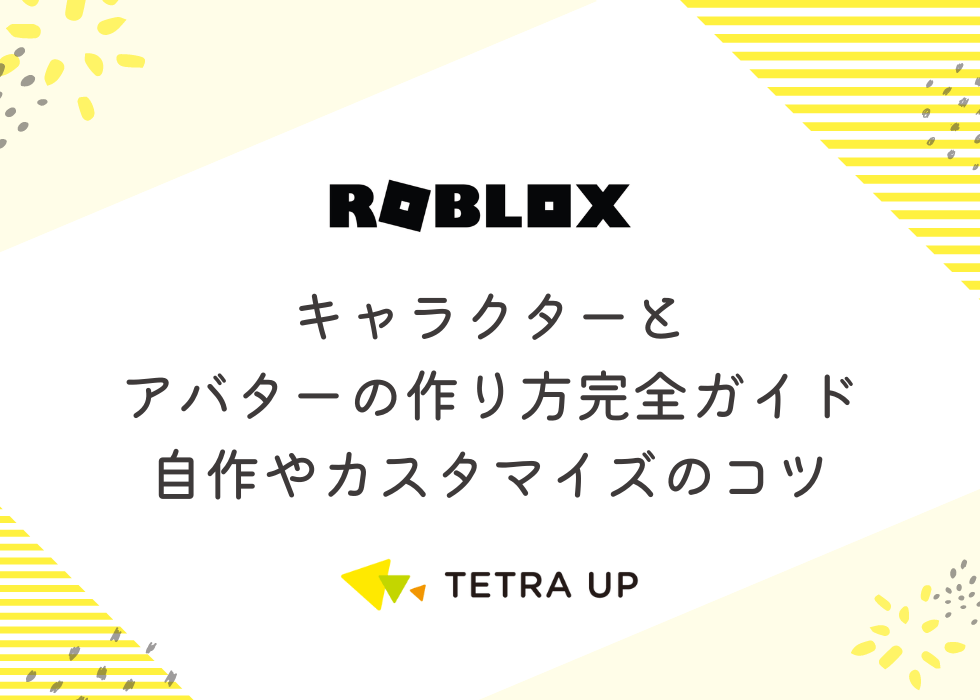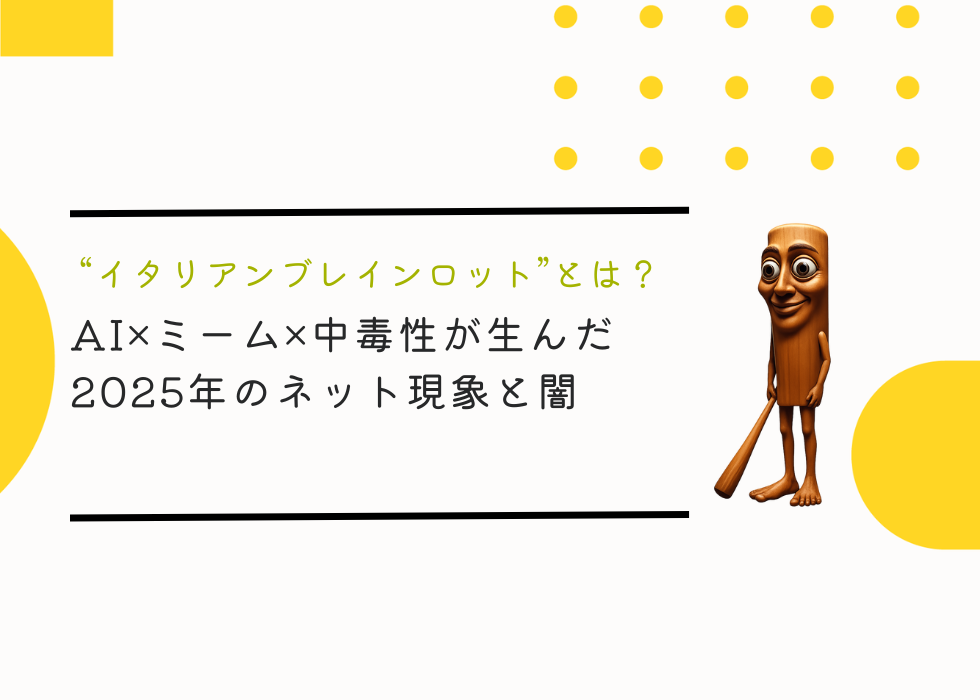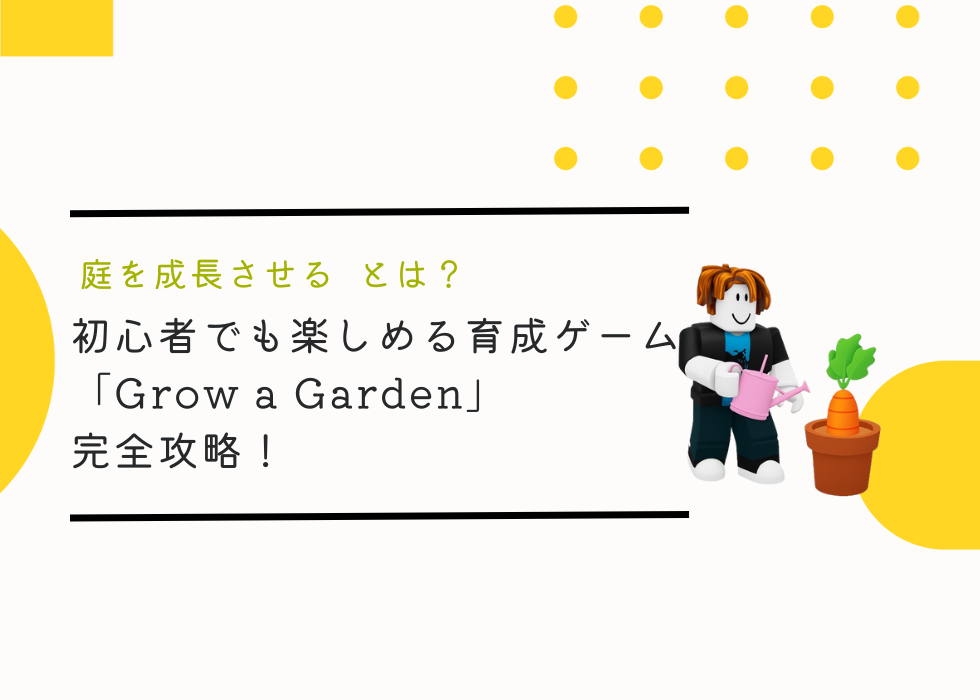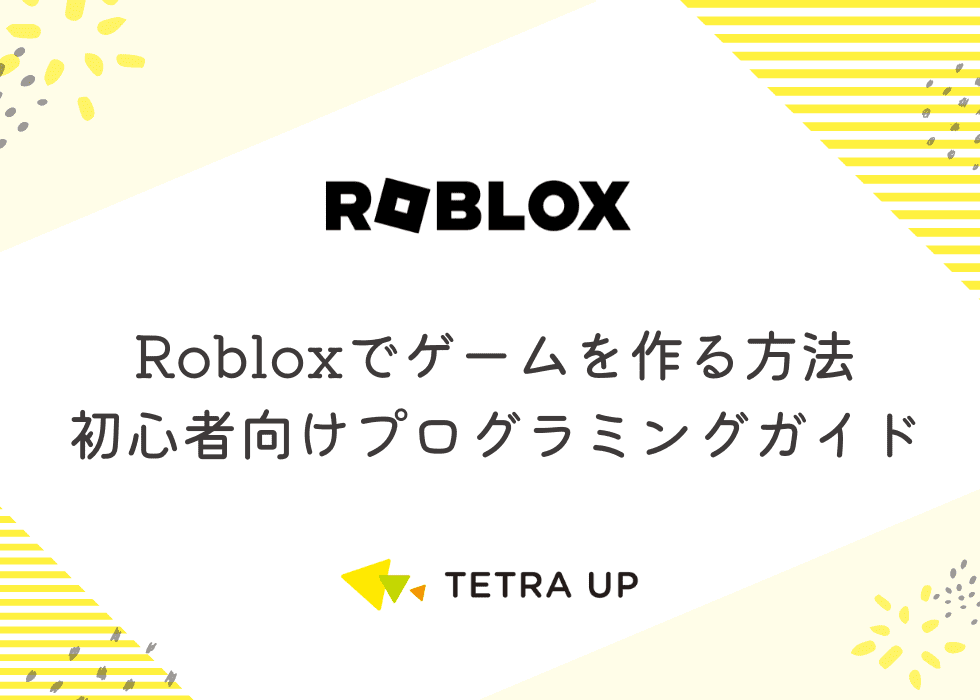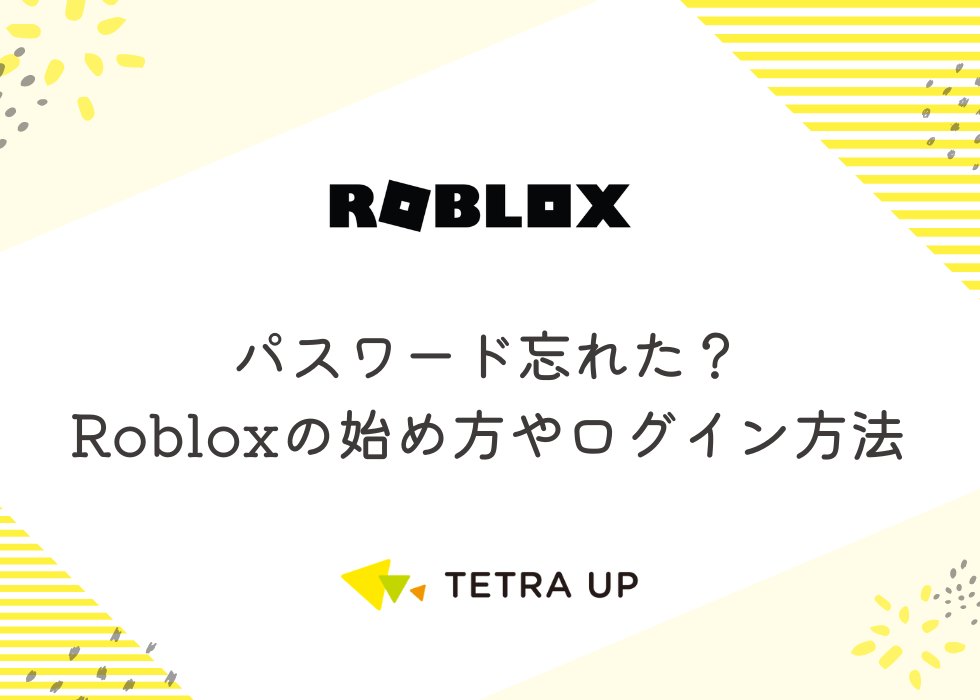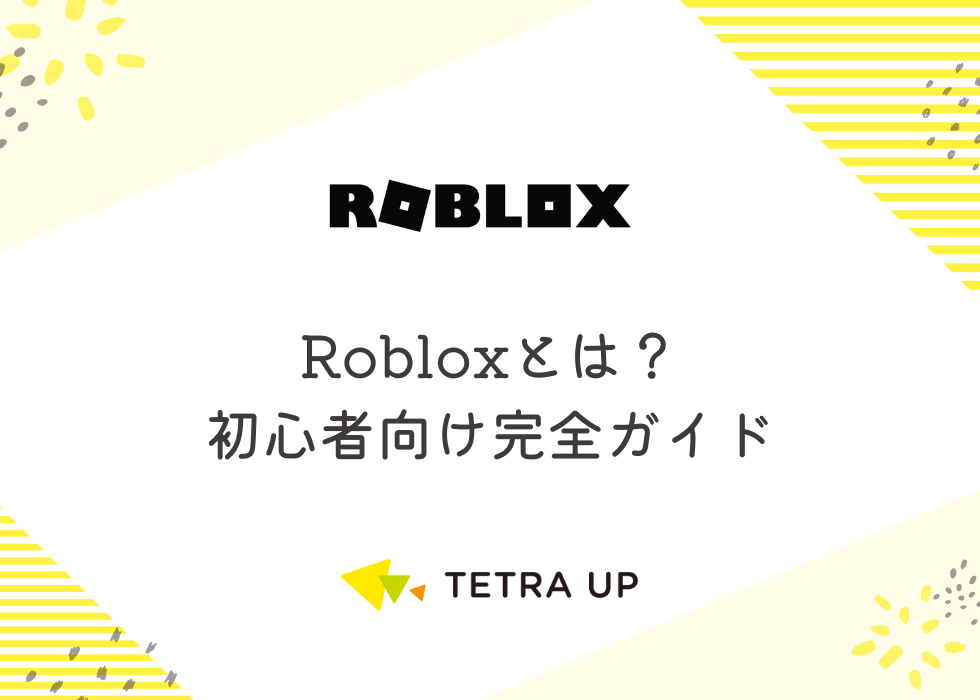-
【WordPress】Advanced Custom Fieldsを使いこなそう!【出力編】
コラム詳細を見る▶
-
【WordPress】Advanced Custom Fieldsを使いこなそう!【設定編】
コラム詳細を見る▶
-
【Scratch】ジャンプの作り方
コラム詳細を見る▶
-
【超入門】自然言語処理でネガポジ判定してみよう!
コラム詳細を見る▶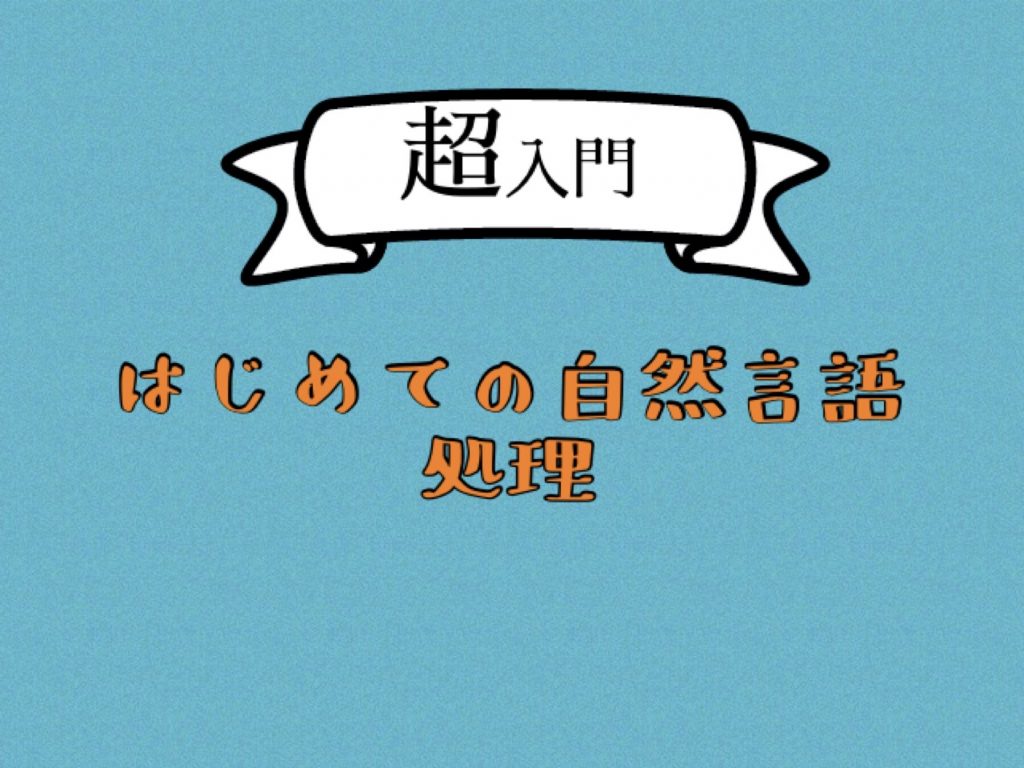
-
WordPress(ワードプレス)とは?メリット・デメリットは?
コラム詳細を見る▶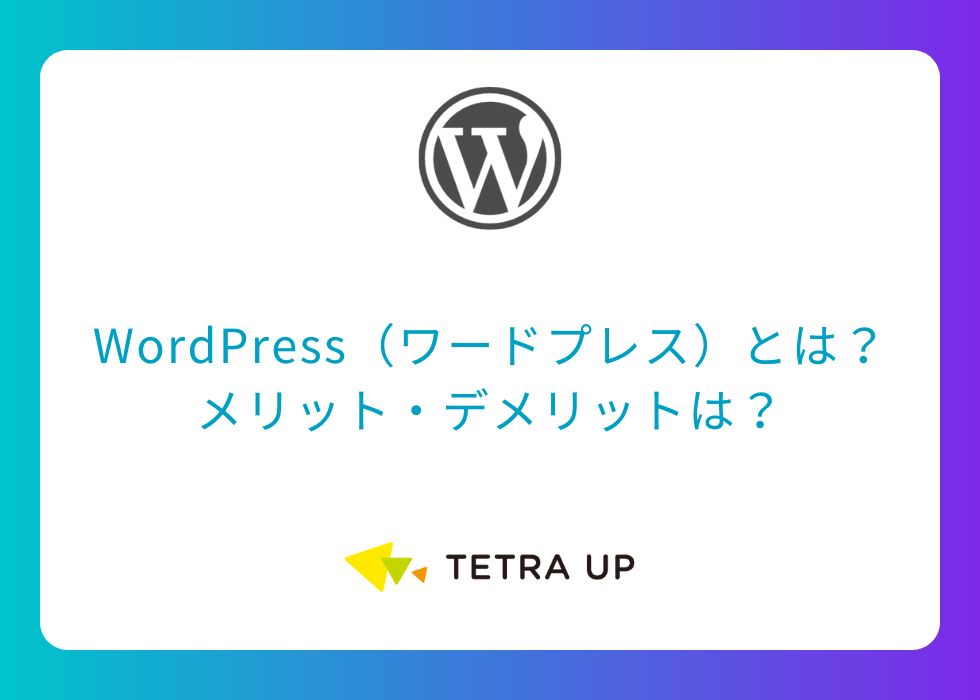
-
まだ使ってないの?!WindowsPCユーザー必読のショートカットキー35選
コラム詳細を見る▶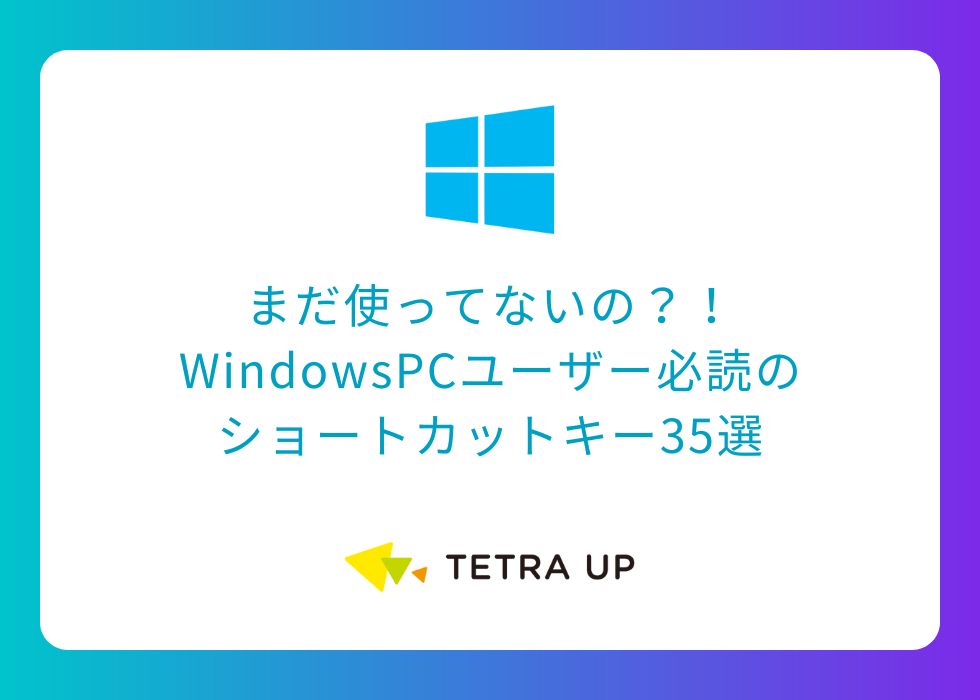
-
【Scratch】xざひょうを10ずつかえると10ほうごかすのちがい
コラム詳細を見る▶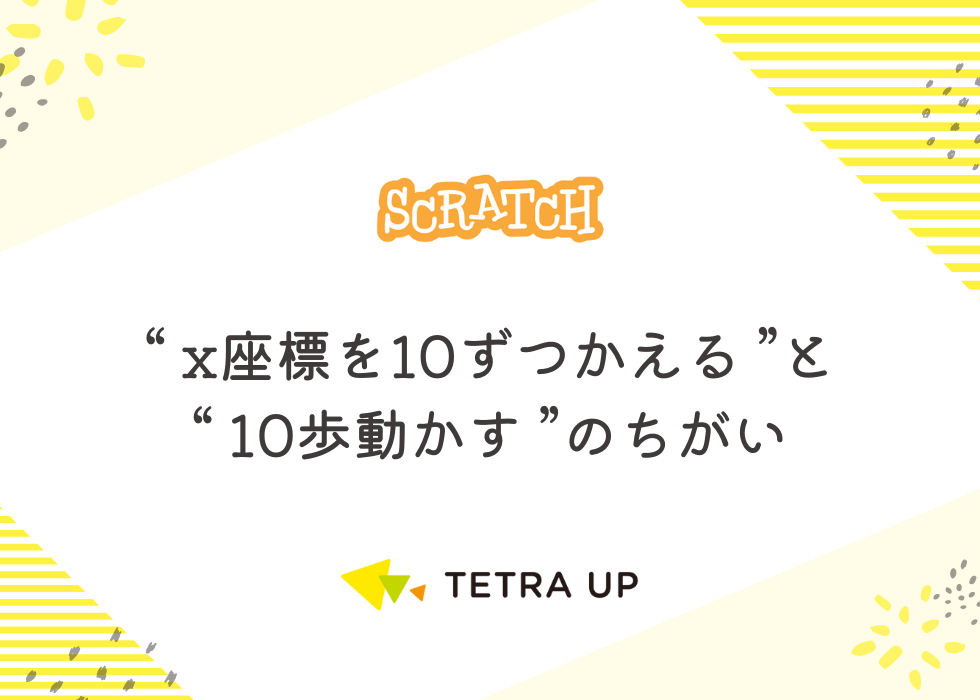
-
【決定版】wp-pagenaviで2ページ目以降が表示されない時に試す5つのこと
コラム詳細を見る▶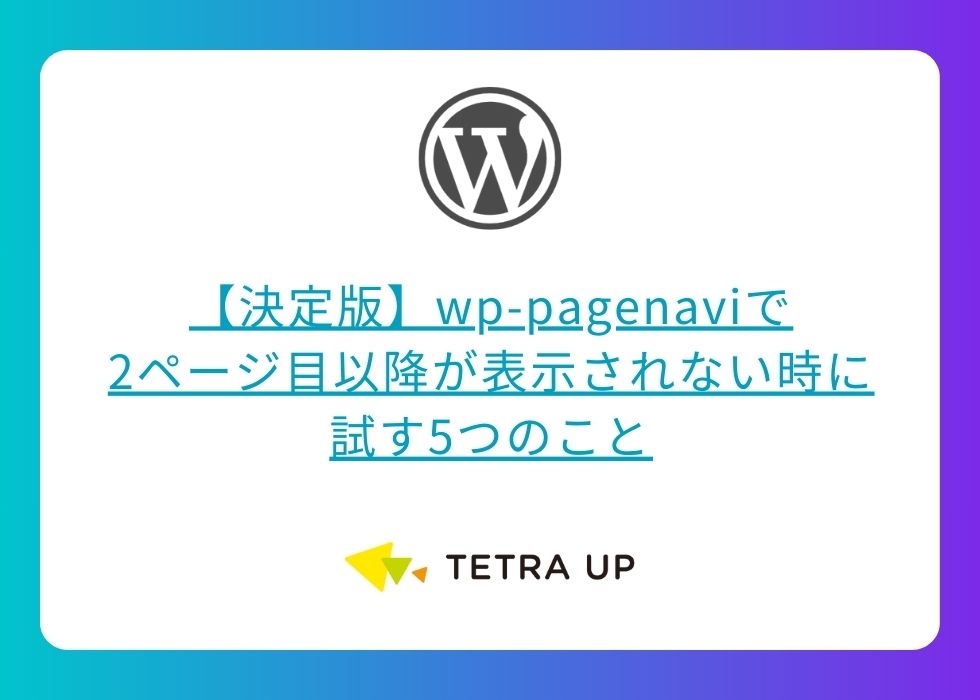
-
【決定版】Wi-Fiルーターの選び方とは
コラム詳細を見る▶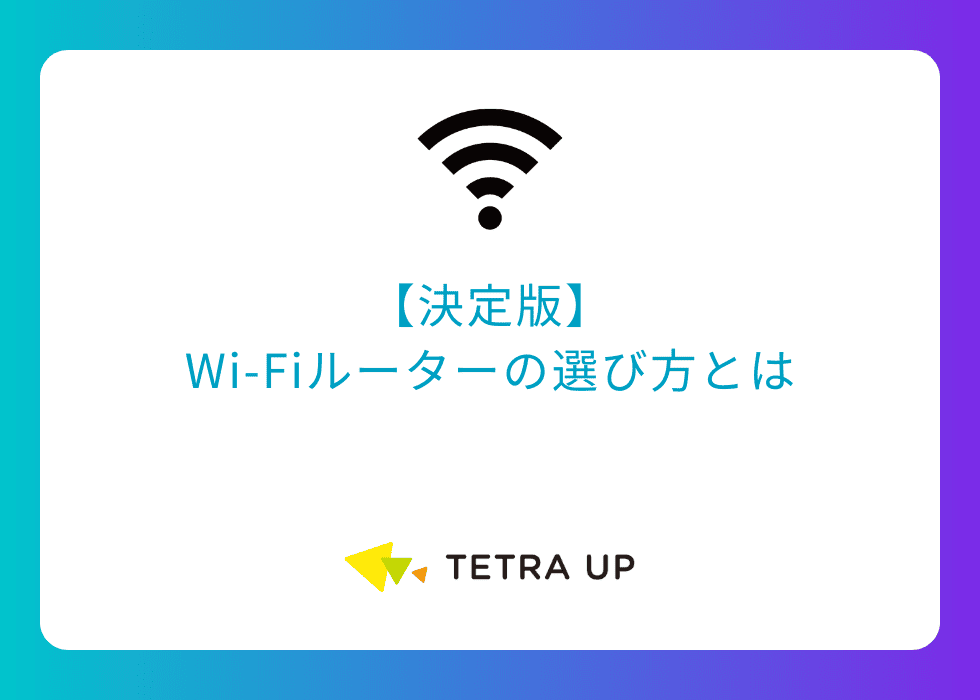
-
『塾・習い事選び大百科 2019完全保存版』に「Knocknote Education」を掲載していただきました。
マスメディア詳細を見る▶