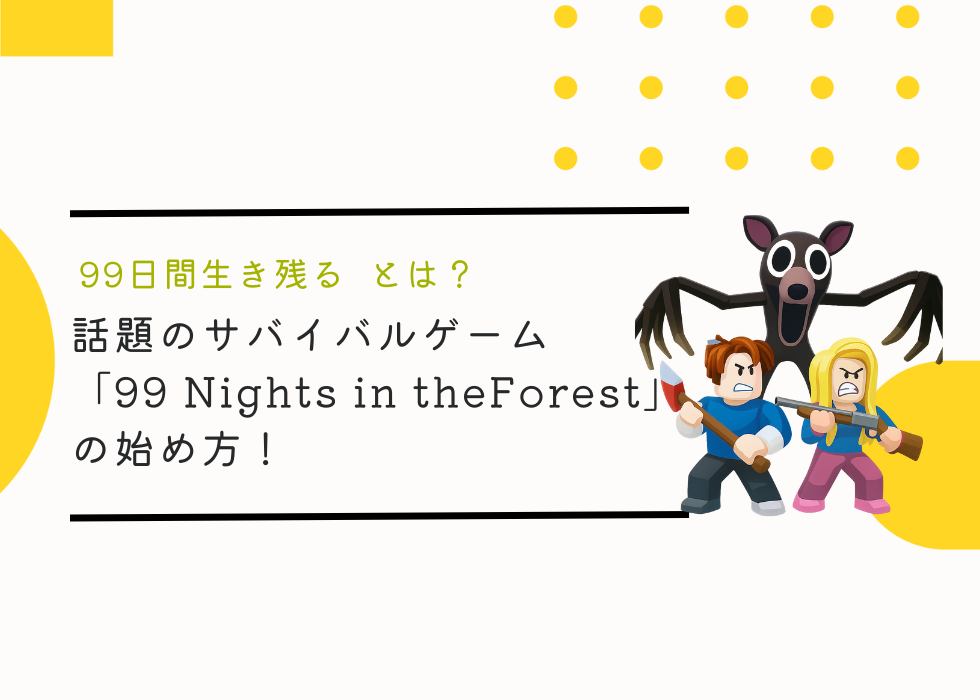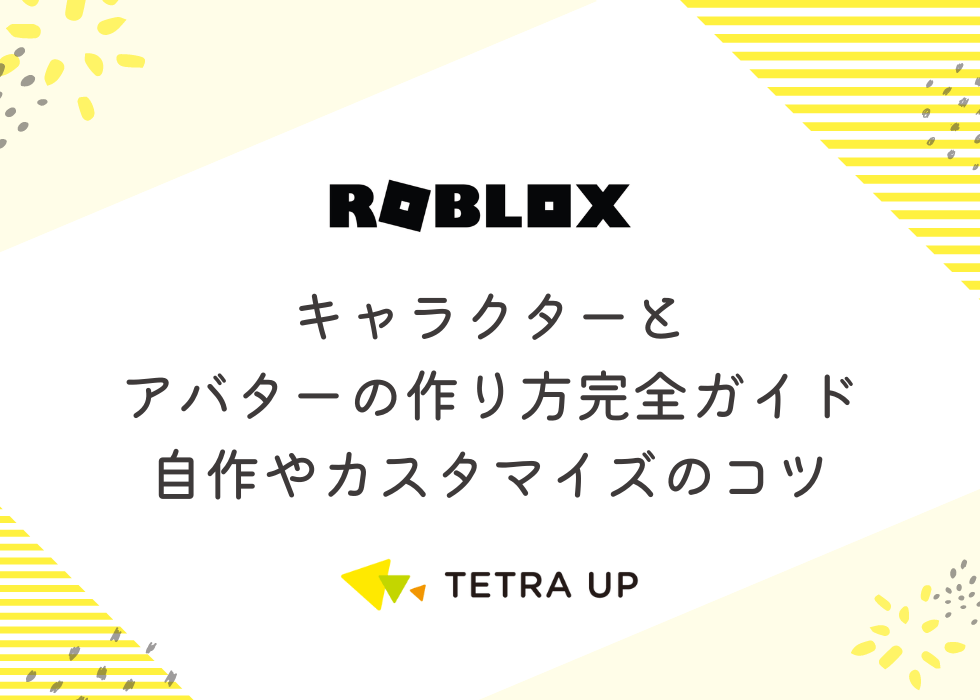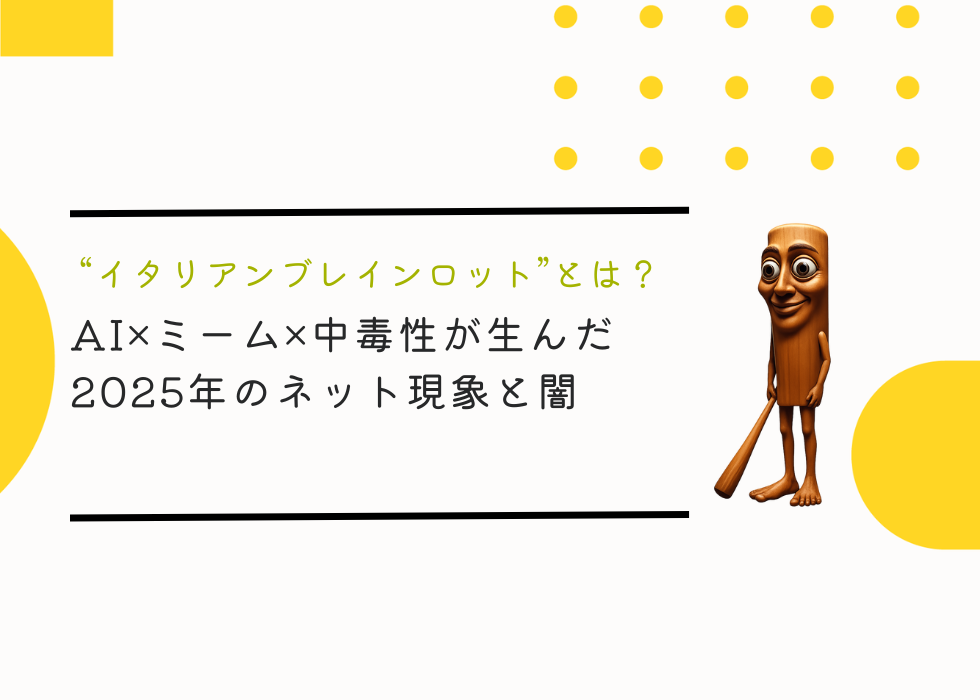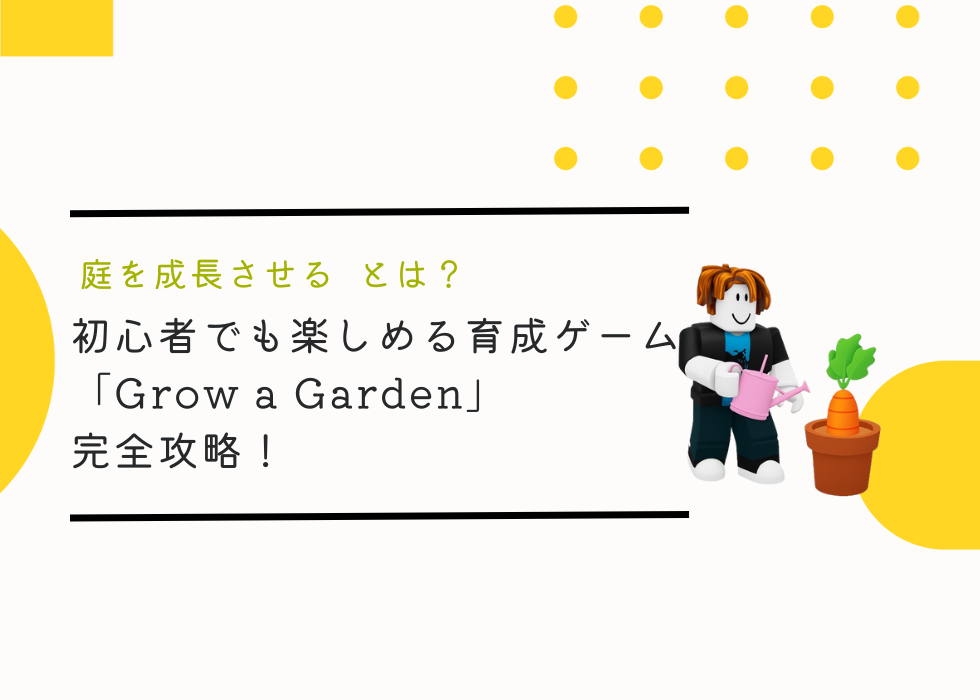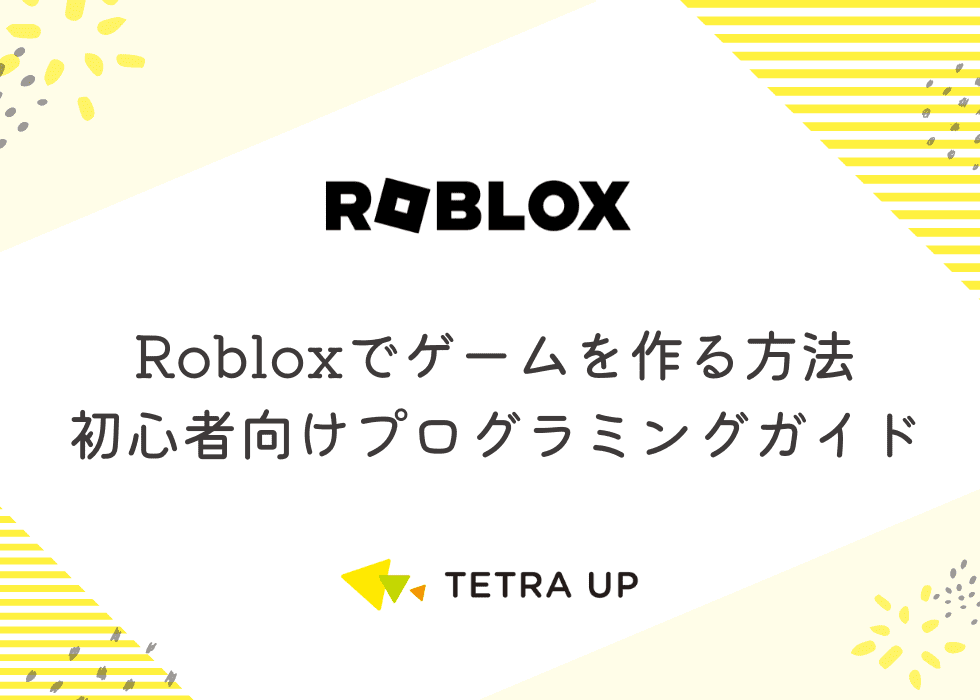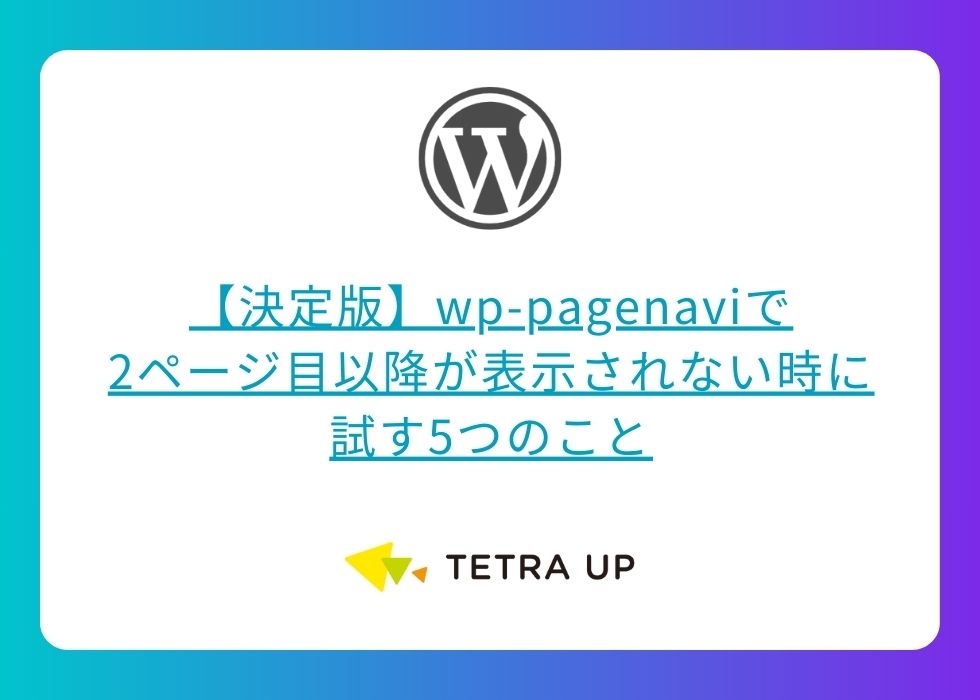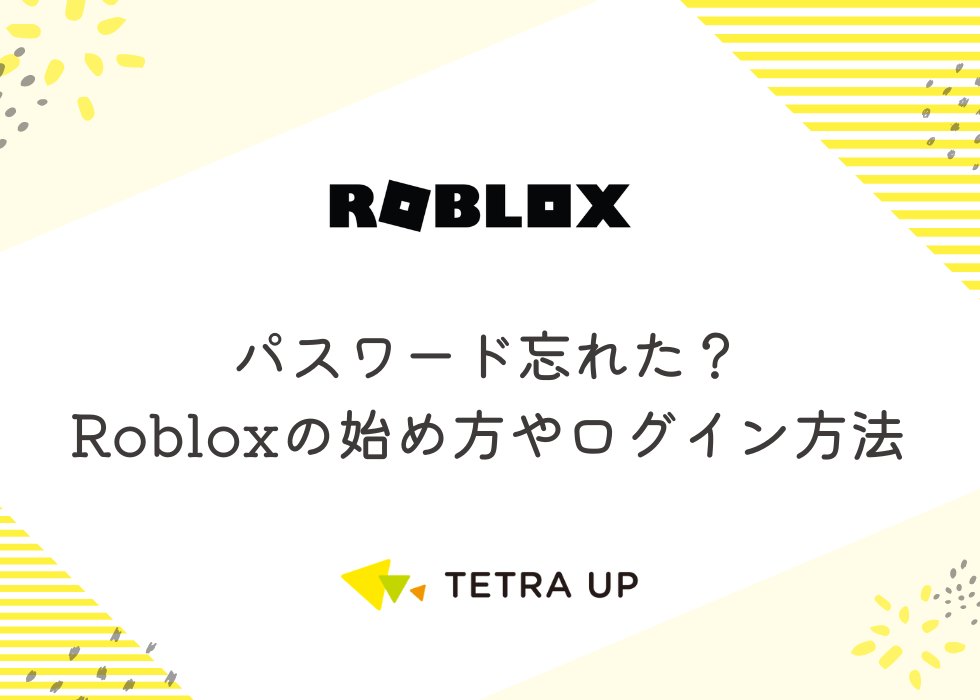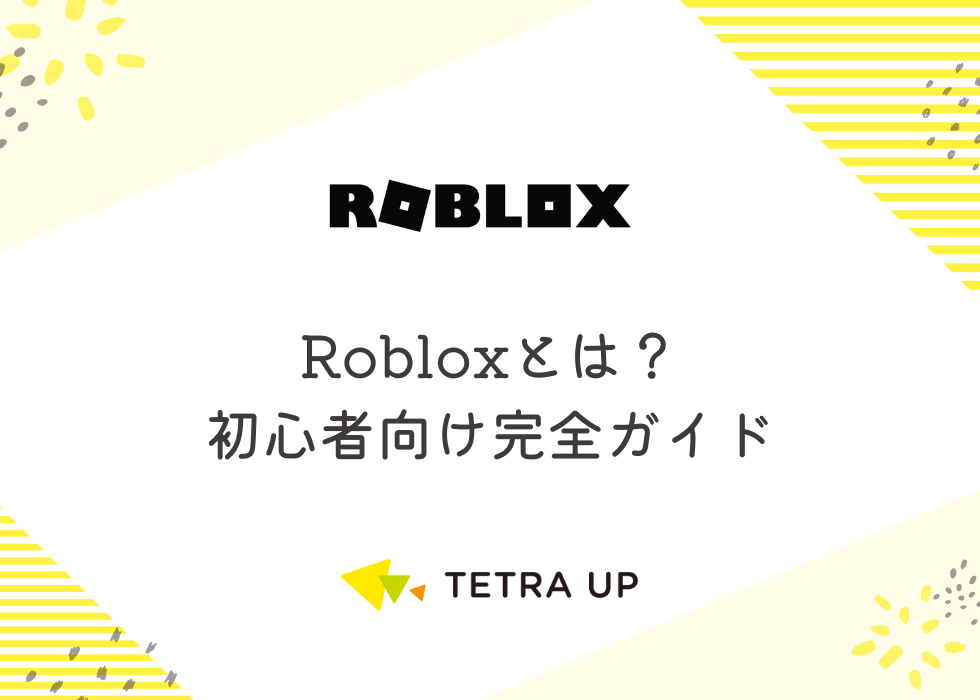-
WordPress初心者必見!よく使う関数まとめ【ブログ編2】
コラム詳細を見る▶
-
【夏休み】自由研究のまとめ方
コラム詳細を見る▶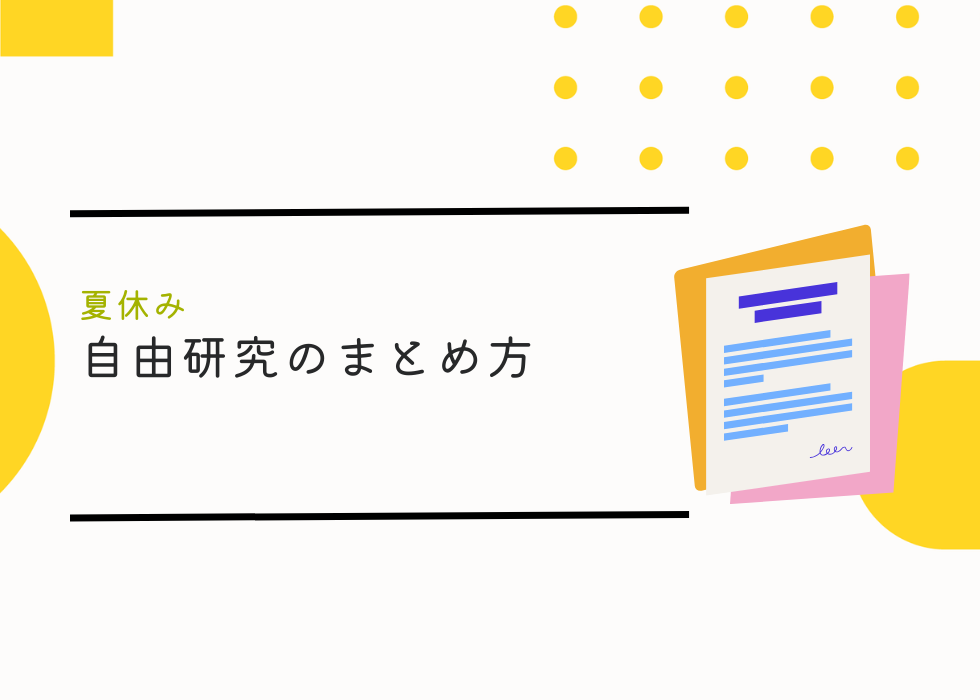
-
WordPress初心者必見!よく使う関数まとめ【ブログ編1】
コラム詳細を見る▶
-
【決定版】自由研究のテーマ選び
コラム詳細を見る▶
-
dl, table, ul,olの使い分けを理解する!!
コラム詳細を見る▶
-
【Android Studio】署名つきapkファイル作成する
コラム詳細を見る▶
-
【自由研究】プログラミングを使う
コラム詳細を見る▶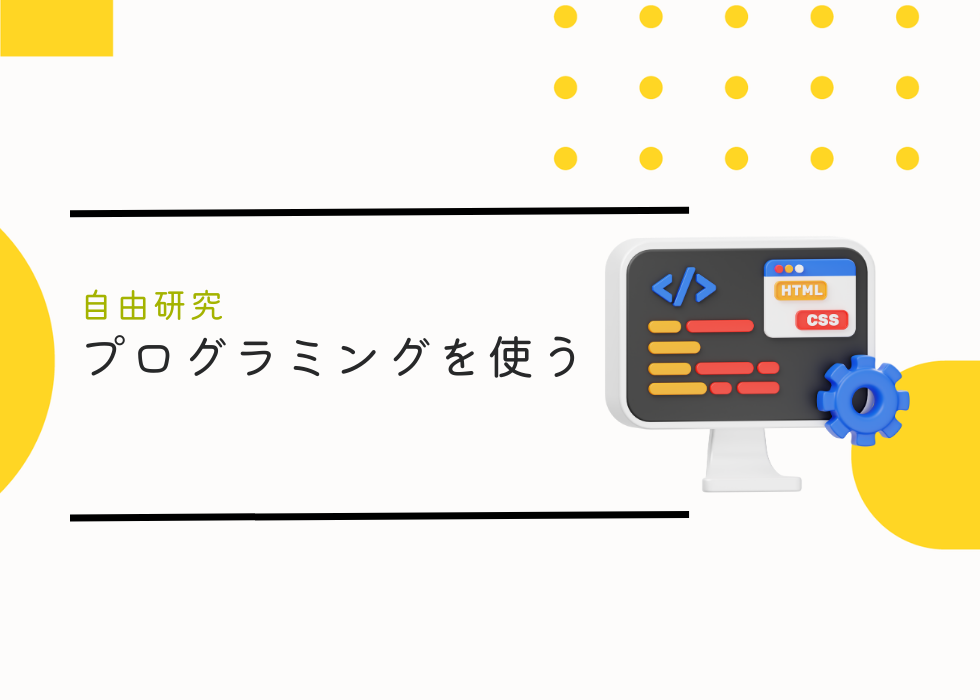
-
「令和」で予測される信じられない事
コラム詳細を見る▶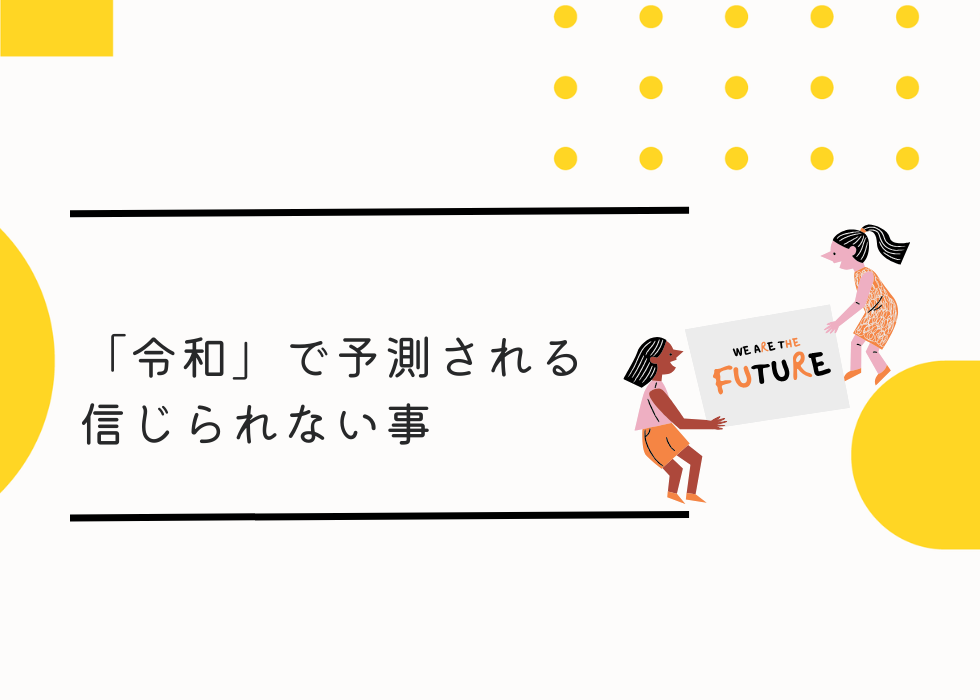
-
【決定版】プログラミングをするメリット7選
コラム詳細を見る▶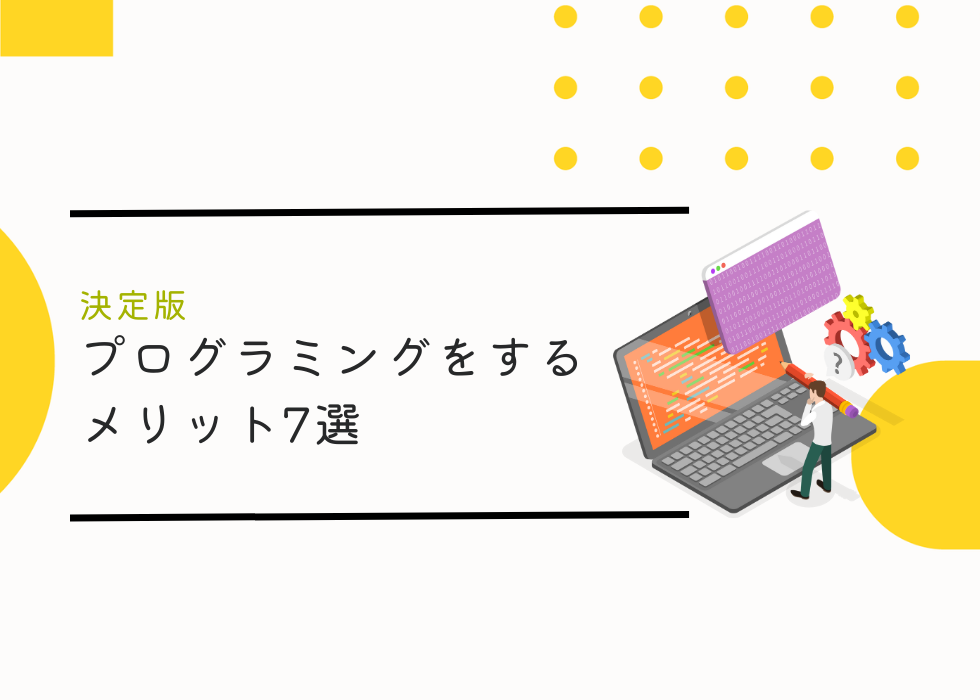
-
【最新版】iOSアプリの申請までの手順「後編」
コラム詳細を見る▶