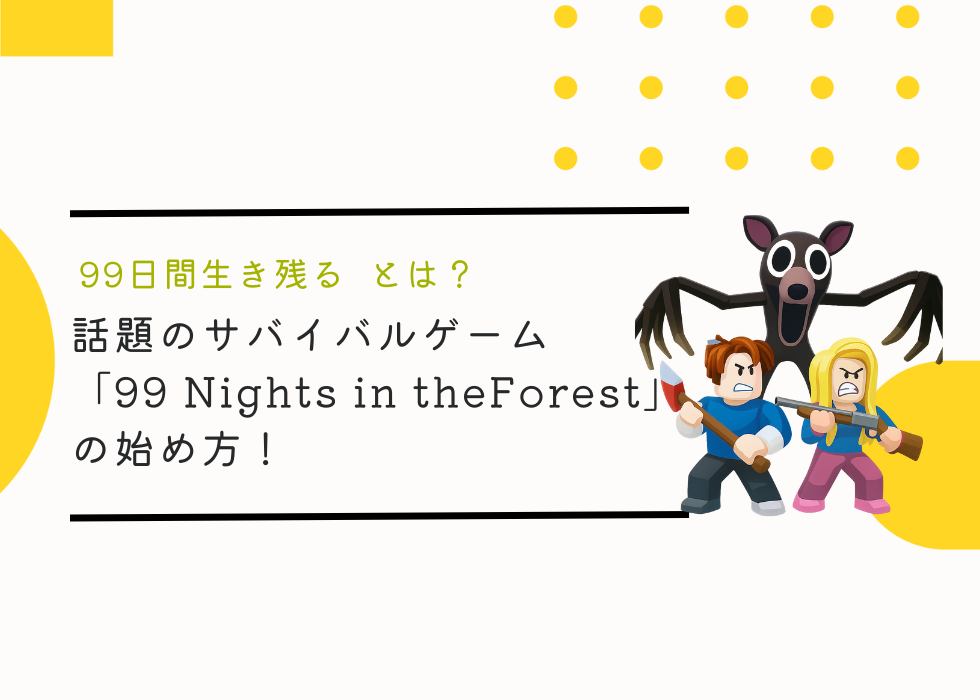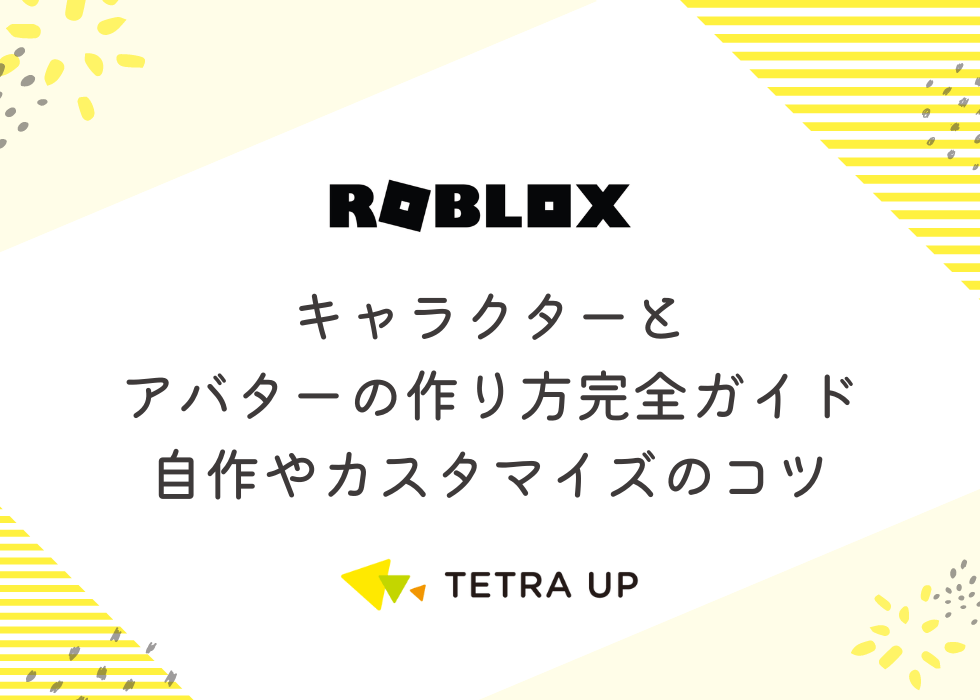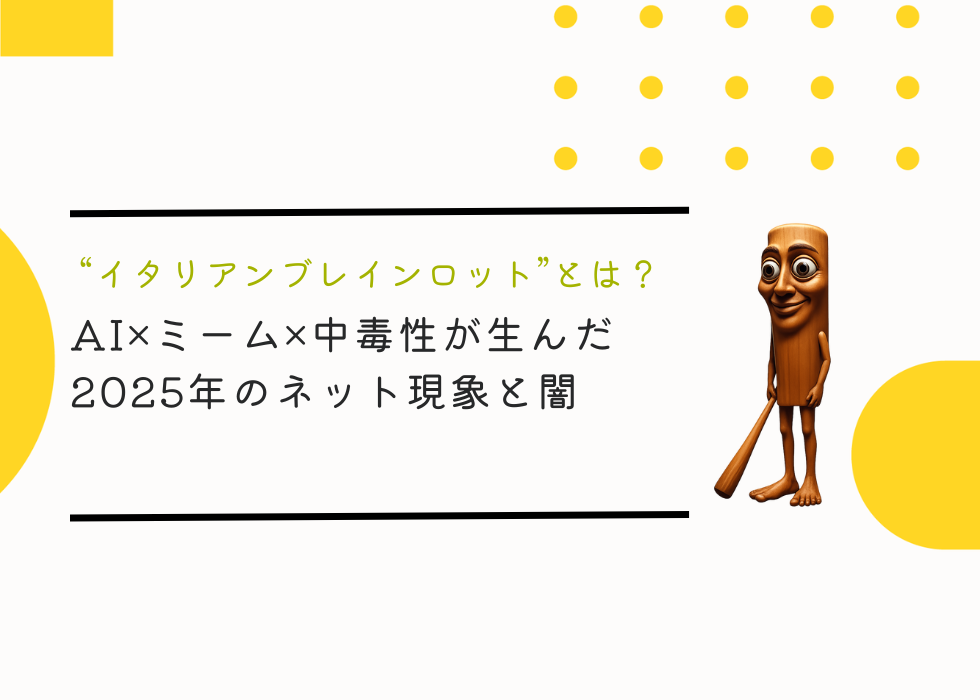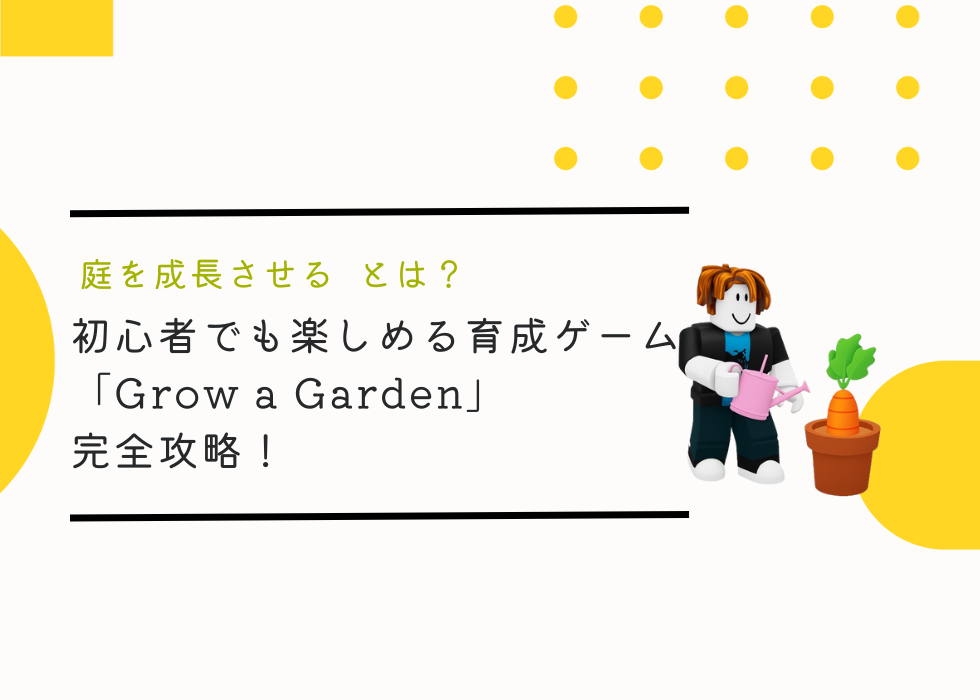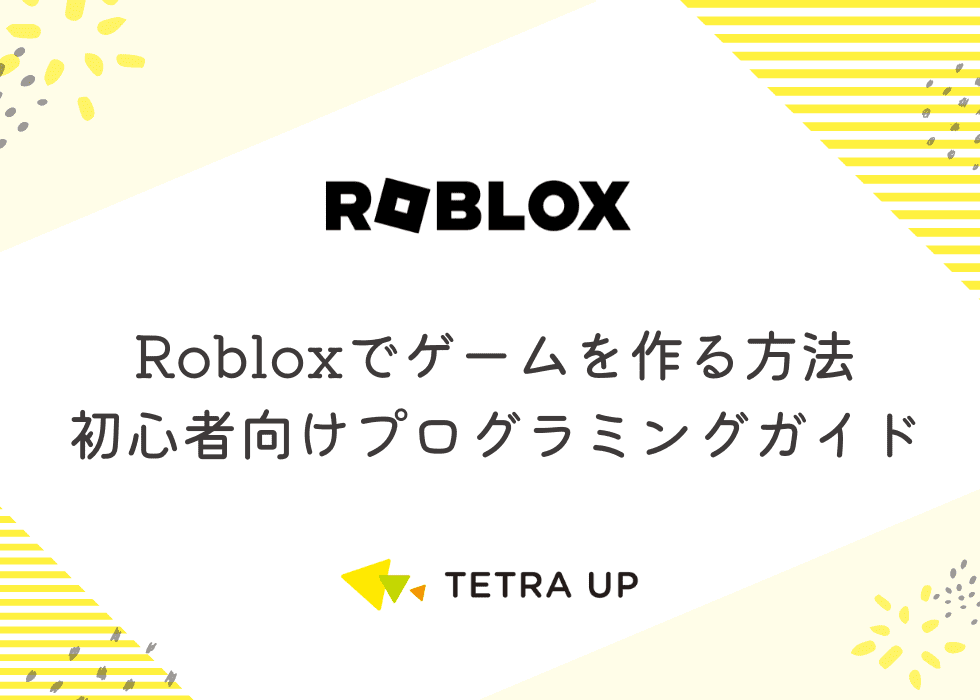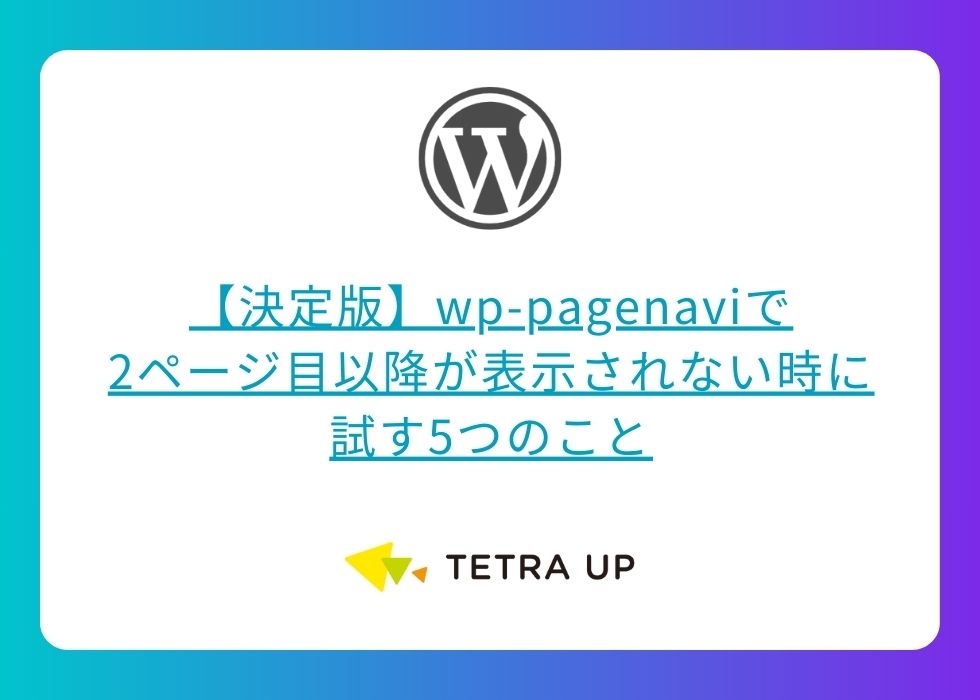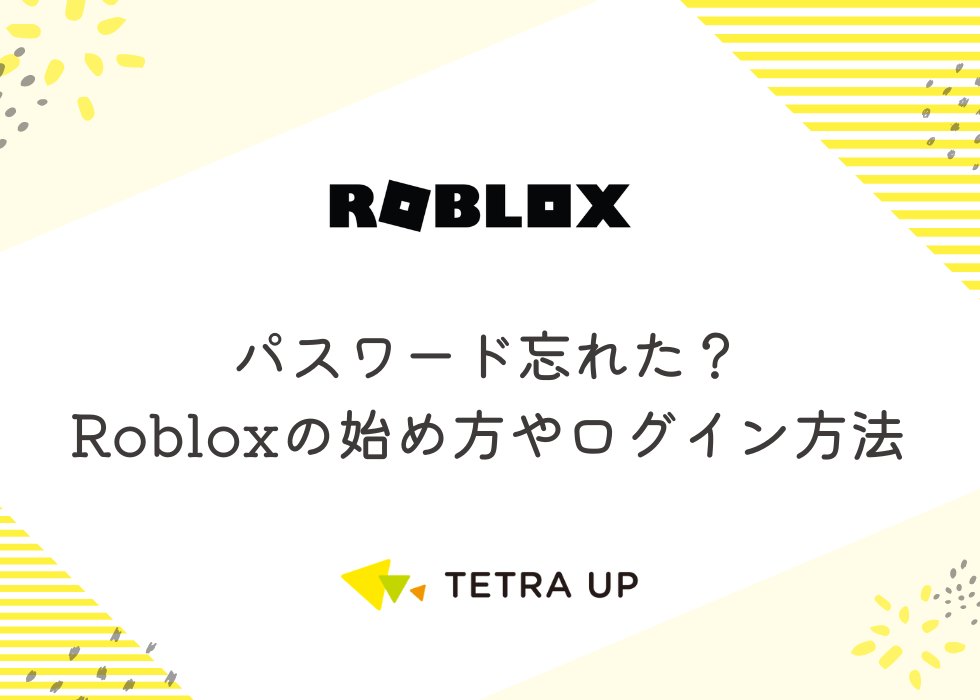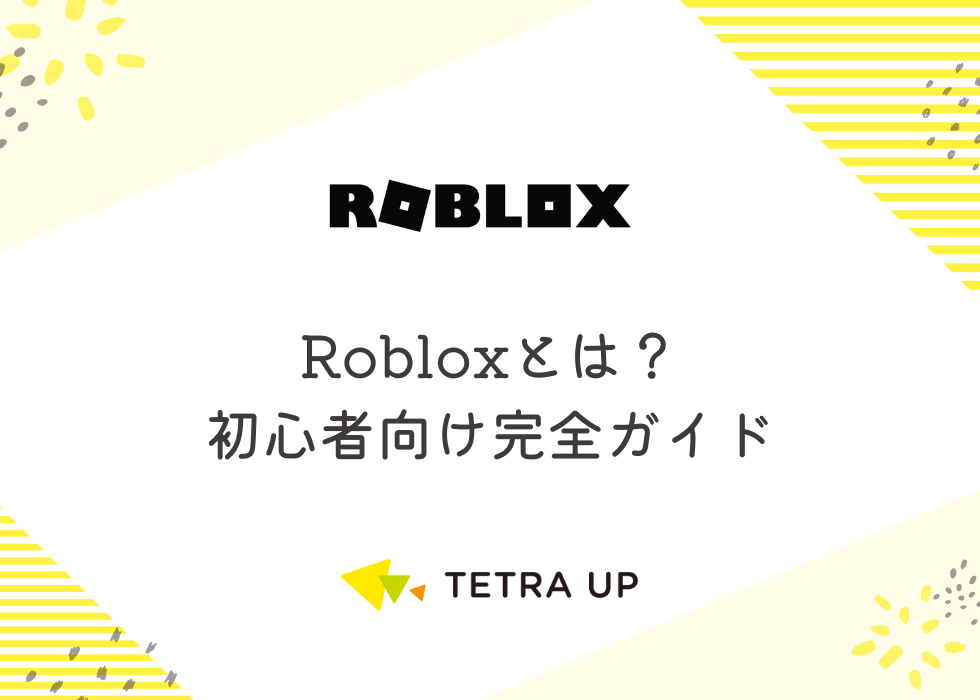プログラミング教育新聞 2025年5月号|TETRA UP
お知らせ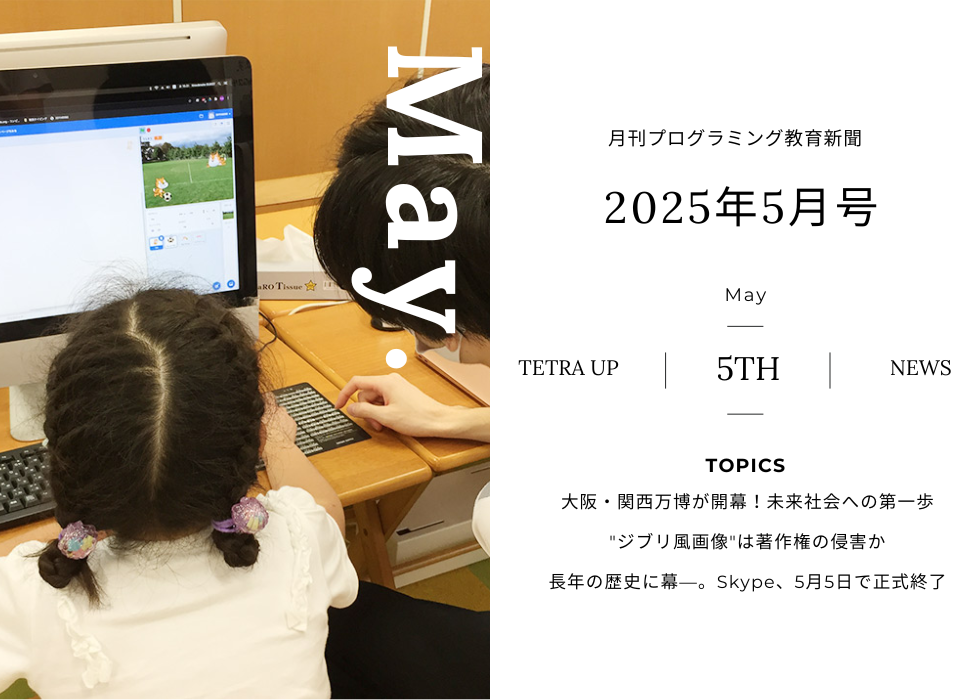
目次
🚀今月のTETRA UPニュース

当教室が約13,000教室掲載の中から選出されました!
このたび、当プログラミング教室が、教育ポータルサイト「コエテコ by GMO」が選ぶ
「2025年 コエテコセレクション」に選出されました!
▼セレクション特集ページはこちら:
https://coeteco.jp/best-school
全国に数多くあるプログラミング教室の中から、「指導内容」「通いやすさ」「満足度」などの観点で高く評価され、信頼できる教室のひとつとしてご紹介いただいています。
これは日頃より通ってくださっている生徒・保護者の皆さまのご支援のおかげです。
心より感謝申し上げます。
これからも、「楽しく、確実に力がつく」学びを大切にし、一人ひとりに寄り添った丁寧な指導を続けてまいります。今後とも、当教室をどうぞよろしくお願いいたします!
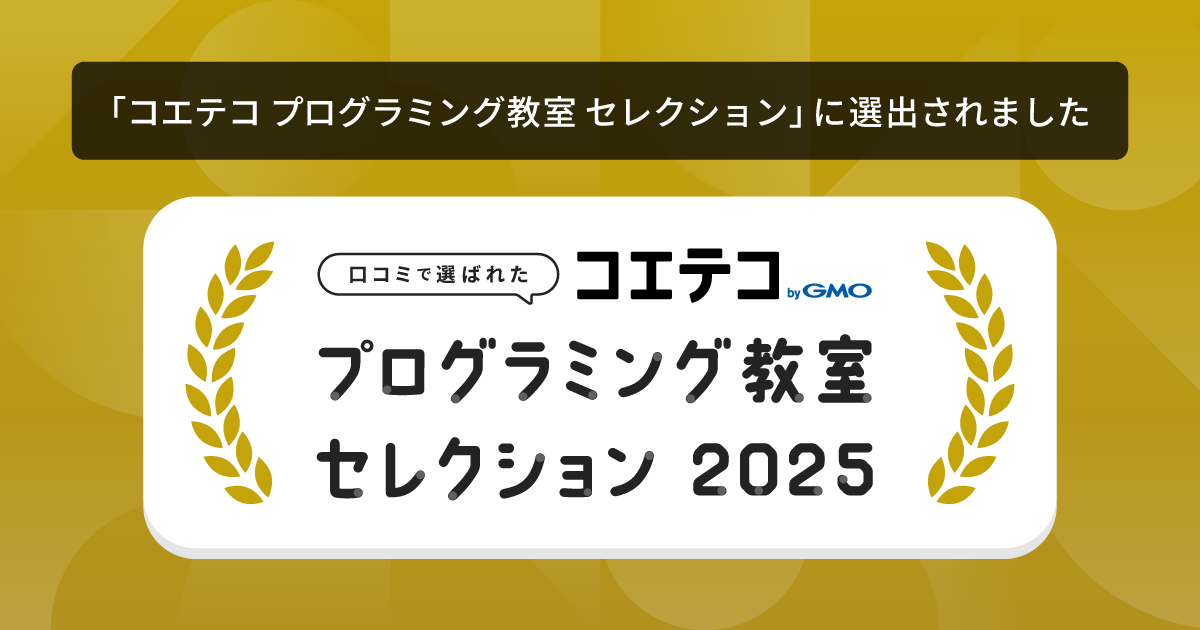
📰 プログラミング教育TOPICS

2-1.大阪・関西万博が開幕!未来社会への第一歩
2025年4月13日、大阪・関西万博が華々しく開幕しましたね!「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、AIやロボット技術、持続可能な移動手段など、最先端の技術が集結しています。開幕から11日間で来場者数は100万人を突破し、開催前は色々言われていましたが2005年の愛知万博を上回るペースでのスタートとなっているようです😊万博は10月13日まで開催されています。子ども達が世界の最先端技術を体験するよい機会になりそうです✨
2-2.”ジブリ風画像”は著作権の侵害か
皆さんは現在SNSで話題のジブリ風画像を知っていますか?
3月26日に行われたOpenAIのGPT-4oのアップデートで、画像生成機能が大幅に改善され写真をアップロードして「ジブリ風にして」と入力すると、アップロードした画像がジブリ風の作画になり出力されるというものです。これはジブリに留まらず、ゴッホ、ディズニー、手塚治虫、ワンピース、ドラゴンクエスト…絵画からゲームまでその作風に寄せることが可能です。
簡潔に言ってしまうと”作風”はアイディアの一部であり、新たな創作の促進を促すため著作権の侵害にはならないそうです。
とはいえAIの活用には引き続き注意を払っていくことが大切ですね。
参考:令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」文化庁著作権課公開資料
2-3.長年の歴史に幕―。Skype、5月5日で正式終了
Microsoftは、長年にわたり世界中で親しまれてきた通話アプリ「Skype」のサービスを2025年5月5日をもって終了すると発表しました。2003年の登場以来、ビデオ通話やオンライン授業、テレワークなどさまざまな場面で活躍してきたSkype。今後は、後継としてより多機能な「Microsoft Teams」への移行が促されています。
時代とともに変わるテクノロジーの流れを実感する出来事となりました。
私たちも、子どもたちに「使いこなすだけでなく、進化に適応できる力」の大切さを伝えていきたいですね。
👨👩👧 保護者向けコラム
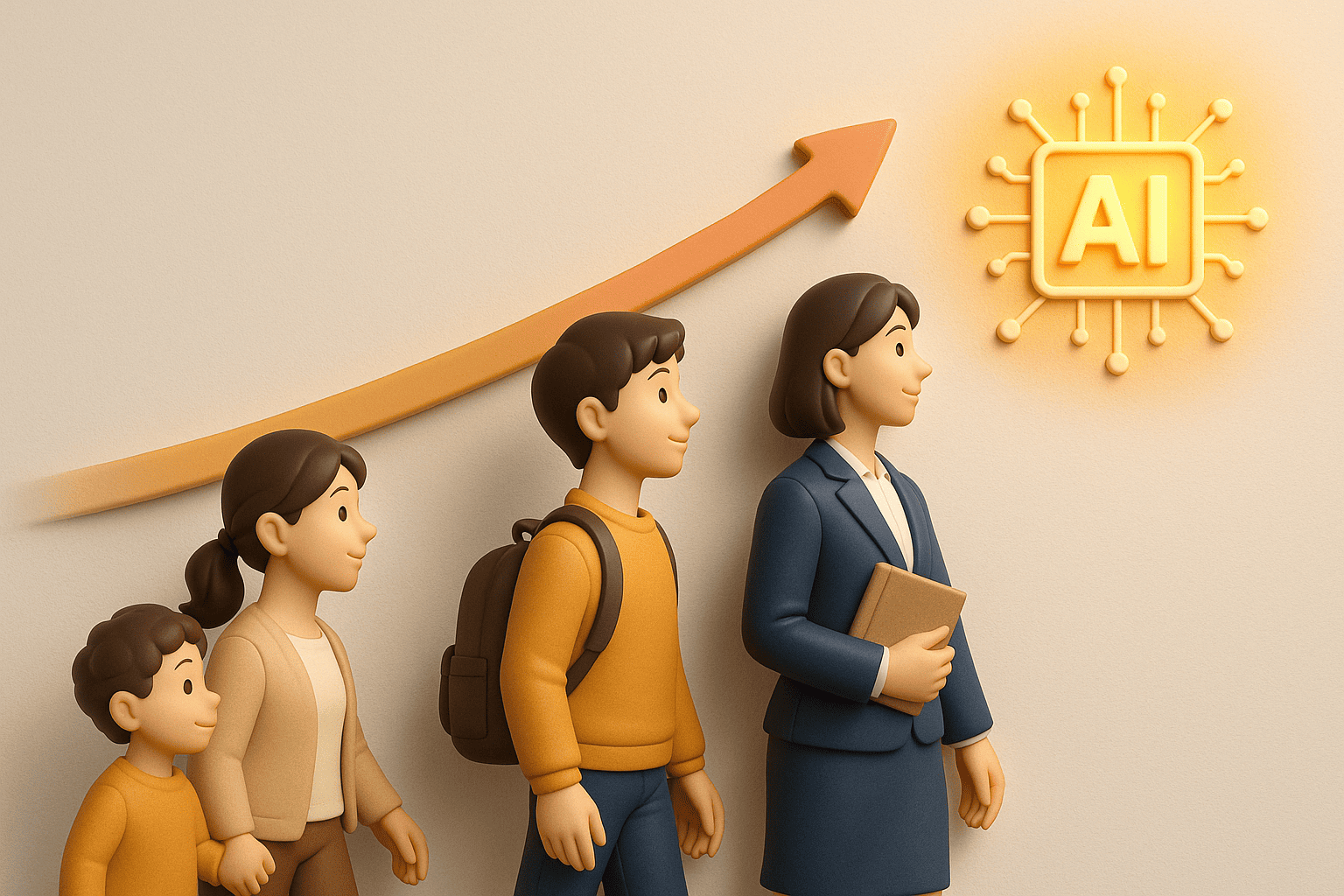
テーマ: AI時代を生きる子ども達への教育
最近ではAIの発達はどんどん加速し、これからはAIと共に生きなければならないとこの記事を読んでいただいている方たちは感じていると思います。
STEAM教育市場も広がる一方で、教育はどのように変化していくのでしょうか。
1. 「知識の定着」から「探究・対話・創造」への転換
AIが情報を即座に提供できる時代では、「暗記していること」そのものの価値が相対的に下がります。その代わりに、子どもたちは「問いを立てる力」や「情報を多角的に捉える力」、そして「仲間と対話しながら新しい価値を生み出す力」が求められます。
今後の教育現場では、AIを使って調べ、仮説を立て、議論し、表現する――という探究的な学びのサイクルを支援するツールとしてICT・AIが活用されていくでしょう。
2. 教師の役割は「教える人」から「学びの伴走者」へ
教師は「全てを教える人」から「子どもが学ぶプロセスを支援する人」へと役割が変わっていきます。生成AIは児童・生徒の質問に即答できる存在ですが、その答えを「どう捉えるか」「なぜそうなるのか」を一緒に考え、深めるのが教師の大切な仕事になります。
そのため、教員自身がICTやAIに慣れ親しみ、共に学び続ける姿勢を持つことがより重視されるでしょう。
参照:「AIと生きる未来をどう創るか」を考えるフォーラム レポート 前編/後編
3. 従来の学習スタイルとの違い
従来のプログラミング学習といえば、分厚い参考書を順番に読み進め、文法や仕組みを丁寧に覚えていくスタイルが主流でした。基礎からしっかり積み上げるという意味では大切なアプローチですが、学び始めたばかりの人にとっては退屈に感じたり、途中で投げ出してしまうことも少なくありません。
一方で、『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』(著:大塚あみ)で紹介されているのは、AIを活用しながら「作りたいものを、まず形にしてみる」という姿勢から始まり、動かしていく中でコードの仕組みや改善点を学んでいくという方法です。
プログラミングの醍醐味は、まさに「頭の中で描いたものが実際に動く」という体験です。AIのサポートを受けながら、自分のイメージを少しずつ形にしていく過程には、自然と夢中になれる面白さがあります。
このように、「とりあえず作ってみる」「動かしながら学ぶ」という新しいスタイルの学び方は、一見きちんと学べていないように思いますが、楽しさを感じながら自然とスキルが身につく、とても効果的なアプローチです。
私たちのプログラミング教室でも、こうした“作って学ぶ”スタイルを大切にしています。
参考書の丸暗記や、皆と同じカリキュラムを進行するだけではなく、自分のアイデアを形にする体験を通して、子どもたちは自信をつけ、主体的に学ぶ力を伸ばしていきます。
「うちの子に合うか気になる」「実際どんなことをやるの?」という方は、まずは体験授業にお越しください。
😌TETRA UP講師の想いーPart5 教育の進化ー

第5回は永田がお送りします。
今回の記事のように私たちは、子どもたちにプログラミングを教える立場であると同時に、子ども達と一緒にこれからの時代を歩んでいく“共に学ぶ存在”でもあると考えています。
かつての教育現場では、「知識を一方的に伝えること」が教師の役割でした。
しかしAIの進化により、知識が“教えてもらうもの”から“自ら得るもの”へと変わった現代。AIがそれを可能にした今、私たち教育者は「教える役割」から「学びを導く存在」へとシフトしていかなければならないと感じています。
子どもたちがこれから生きていく社会は、AIやテクノロジーと切っても切り離せない世界です。
そんな中で本当に必要とされるのは、AIに使われるのではなく「道具のひとつとして活用する力」とAIでは代替できない「人間らしさ」、そして「学び続ける姿勢」だと考えています。
私たちは、子どもたちにただプログラミングを教えるのではなく、こうした時代を生き抜くための“土台となる力”を育てたいと日々授業を行っています。
そのためには、まず私たち大人が、そして教える立場にある私たち講師が、時代の変化を恐れず、AIを学び、活用し、教育の在り方そのものをアップデートしていく必要があります。
これまでの「決まった答えを教える」教育から、「問いを立て、探究し、考え続ける」教育へ――。
私たち自身が学び続ける姿勢を見せることで、子どもたちにも「学ぶことって面白いんだ」と感じてもらえるはずです。
AIは、正しく使えば子どもたちの学びを支える強力な味方になります。
そして私たち講師はAIと共に走りながら、子どもたち一人ひとりの個性や興味に寄り添った教育をつくり出していく存在でありたいと思っています。
今後も、大人と子ども・講師と生徒という立場ではなく、子どもたちと同じ目線で未来を見つめ、共に成長していく教室であり続けたい――そんな気持ちで、引き続き講師一同全力で取り組みます!
国内外の幼児~小学校教育に携わり、現在子ども向けプログラミング講師として従事。
ただプログラミングを教えるだけではなく、子ども1人1人と保護者、そして教室と相互に関わり合い成長していけるように日々取り組んでいます!